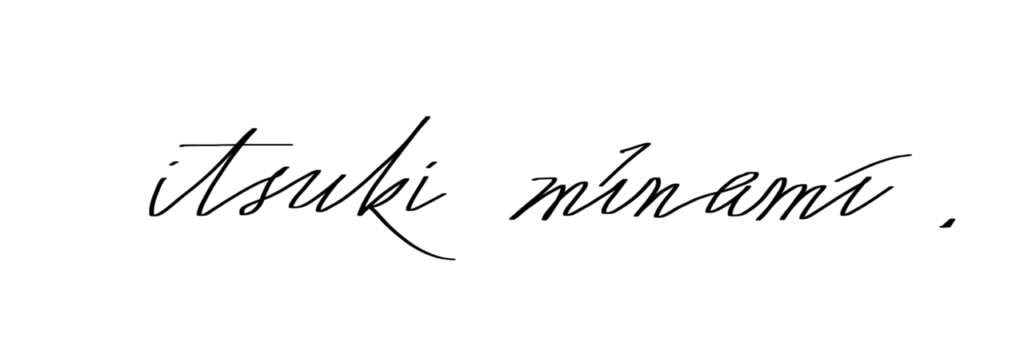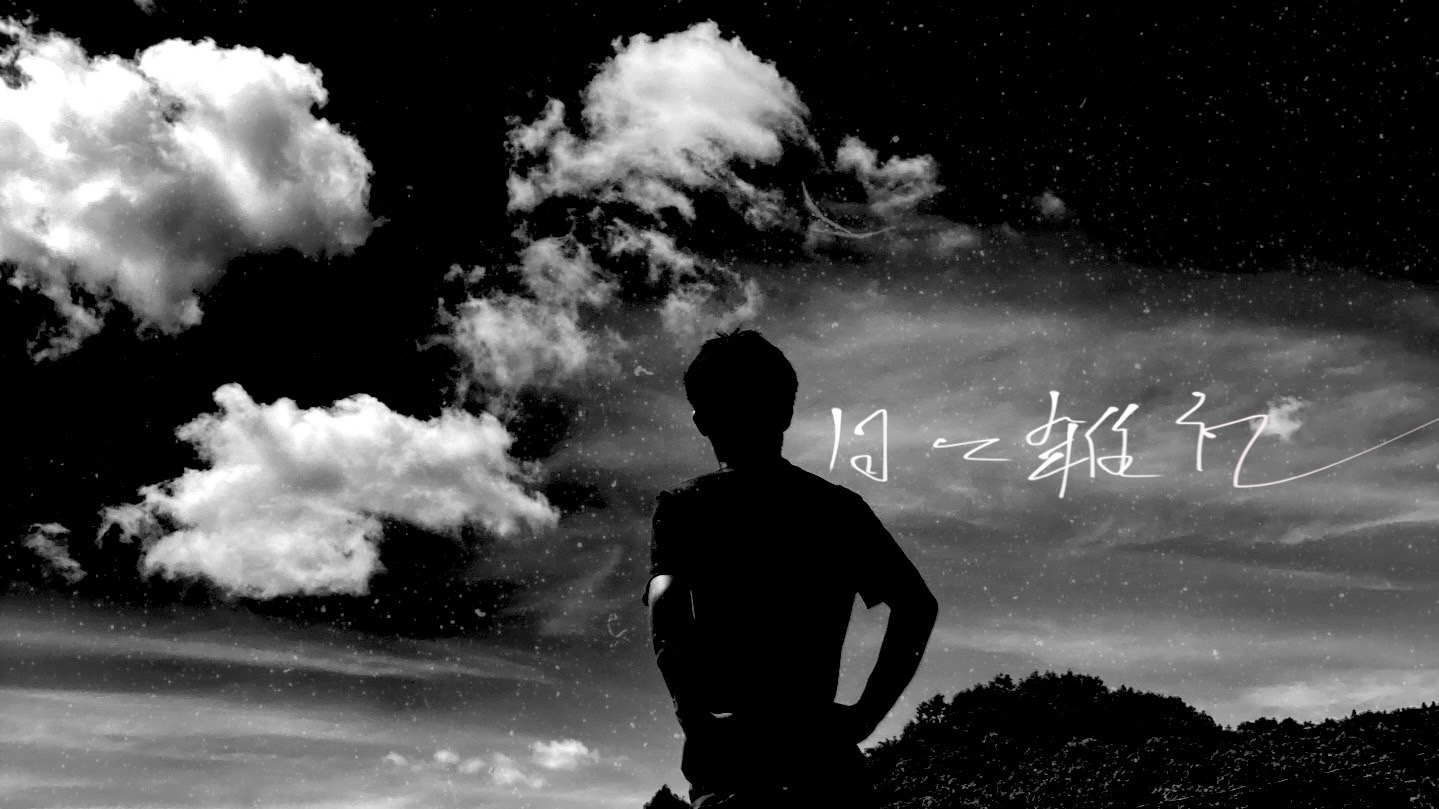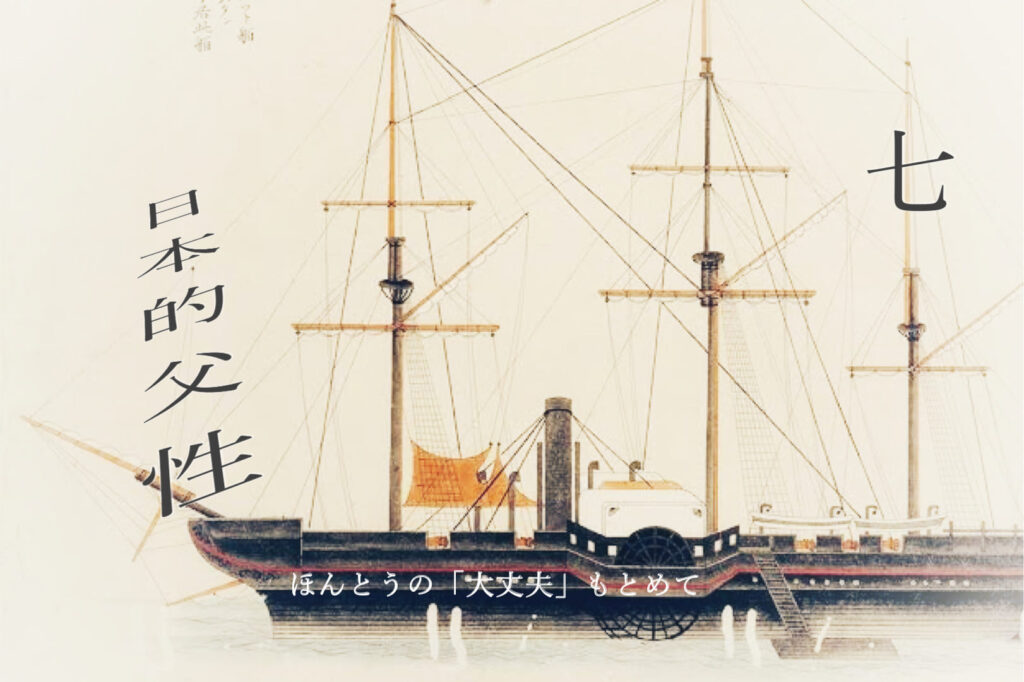
7.第二章「近代の守破離」
『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –
目次
-近代の発端
零、近代概念の誕生
十七世紀から十八世紀にかけてのヨーロッパは、一連の市民革命により大きな変革の時を迎えていた。
これらの市民革命は、「民主主義革命」や「資本主義革命」などとも呼ばれ、産業革命による繁栄からくる市民階級の政治的自由と権利を求める声が 封建制度 に挑戦していく形で進行していた。英国の名誉革命、フランス革命などがその代表例で、市民が自らの権利を主張し、「国家」のあり方に影響を与え始めることになる。
その後の資本主義社会の成立とともに、 社会契約論 や 自然権 の概念が誕生し、この時期は現代における多くの概念の画期となった。ジョン・ロックの『市民政府二論』(1689年)やルソーの『 社会契約論 』(1762年)など、新たな思想が誕生し、それらは現代社会の仕組みを築く重要な礎となった。
そもそも「資本主義」とは、資本家と労働者の二つの関係性、私有財産、競争といった原理が基盤にある社会構造である。人々は「金」「効率」「生産性」を重視し、組織や企業が生まれ、その拡大や 「豊かさ」 を追求する仕組みが整えられた。
それらに加えて、この時代には、近代の骨格をなす概念がいくつも生み出された。
私たちが普段から当たり前のように使っている「 人間 」「大衆」「主体」「個人」「社会」 「幸福」 「国家」「自由」「自然」などの概念は、全てこの時期に 西洋 から生まれたものであり、その歴史は実はとても短い。これらの概念は、現在でも「近代」の構造やイデオロギーを維持するための重要な役割を果たしているのは言うまでもない。
ここからは、これらそれぞれの概念をもう少し詳しく見てみよう。
まず、「個人」や「主体」といった概念は十八世紀のヨーロッパ、特にフランス革命の時期に啓蒙主義の影響を受けた思想家たちが中心となって創り出したものである。彼らは、「個人」「主体」といった概念を通じて、「 人間 」の本性としての自由 意思 の存在を示した。
ルソーの『 社会契約論 』では、「 人間 」が自然状態から社会状態へ移行する過程が描かれている [9] 。それにより、「 人間 」は「個人」としての「自由」と自己決定性を保持しつつ、「主体」として共同体の一員となる。こうした「個人」と「主体」の概念は、資本主義社会の基盤となる「私有財産」の存在を説明するための重要な概念でもあった。
また、「 人間 」という概念そのものもこの時期に成立したという見方もある。「 人間 」は、個々の「個人」や「主体」を超えた、普遍的な存在として捉えられる。資本主義社会では、生産力や効率が重視され、神や国王への信仰や忠誠といった封建的な価値観が徐々に衰退した。その結果、「 人間 」は、「個人」が共有する普遍的な価値や権利を表す概念としてより強固に位置づけられるようになった。所謂「 人間 中心主義」の始まりでもある。
これらの概念は、「自己」と「他者」、「 人間 」と「自然」を明確に区分する思考を支え、資本主義という新しい社会体制の理論的基盤を形成した。特に、カントの「道徳法則」やベンサムの「功利主義」など、「 人間 」の「自由」と「平等」を前提とした道徳哲学や政治哲学が発展したのも、この「 人間 」概念の影響が大きい。
この「個人」「主体」「 人間 」といった概念は、その後の近代「社会」において多くの新たな概念を生み出す源流となった。
「個人」という概念の創出と共鳴するように、「大衆」や「国家」といった概念も歴史の表舞台に登場した。この概念が、近代というエポックを特徴付ける主要な要素の一つであることは、ホッブズの『リヴァイアサン』(1651年)やルソーの『 社会契約論 』など、多くの古典的な政治哲学の著作で見て取ることができる。そこでは、「個人」が集まって「大衆」に変容し、「国家」が生まれ、社会契約の一環として個々の権利が制限されるという思想が提唱されている [10] 。
それと平行して、「民主主義」という新たな政治体制が生まれ、それに伴い「人権」「自由」 「幸福」 「社会」といった概念が導入された。アメリカ独立宣言(1776年)やフランス人権宣言(1789年)など、その時代の重要な文書は、個々の市民が享受すべき基本的な権利を明記しており、これが「個人」の概念を強化した [11] [12] 。
この新たな概念は、資本主義という経済体制と深く結びついていた。アダム・スミスの『国富論』(1776年)など、資本主義経済の理論は、効率や競争を通じて個々の 「幸福」 を最大化することを主張した [13]。これは、個々の「合理性」や「意味」を追求するという近代的な思考回路を強化した。
一方、「自由」は市民革命の重要な動力源であり、その達成は、 封建制度 からの解放と、「個人」の権利の確立という形で実現された [14] 。「自由」は他者の「自由」との衝突を生む可能性があるため、「社会」という 「枠(囲い)」 の中で一定の規制が必要とされ、この規制の基準となるのが、例えば「公共の福祉」という概念である。ロックの『市民政府二論』では、「自由」が一人一人の「自由」な行動を可能にする一方で、「他者の同じ『権利』を侵害しない限り」という条件が付け加えられている [15] 。
「人権」の概念は、「自由」と密接に関連している。人々が「自由」に生きるためには、一定の基本的権利が保障される必要がある。それは、 生命 、「自由」、財産の保護など、個々の「 人間 」が「社会」の一員として享受すべき「権利」とされてきた [16] 。
これらの概念は、人々が 「幸福」 を追求する目的と繋がっている。それは、「社会」が維持され、個々の「自由」が保障され、「人権」が保護されることによって実現されるとされている。この理論は、ジェレミ・ベンサムの功利主義やジョン・スチュアート・ミルの自由論など、さまざまな思想家や哲学者によって展開されてきた [17] [18]
一、明治維新と文明開花
日本 では、江戸時代後期、列強との対峙により開国へと舵を切り、明治維新を経て近代化へと至ることとなった。この過程において、吉田松陰や高杉晋作、坂本龍馬、西郷隆盛、橋本左内などの幕末の志士たちは、様々な立場でその知見を元に国の未来を考えるものの、彼らは明治維新後の新たな制度設計期を迎える前に亡くなった。その後を継いだのが、薩長主導の生き残りの志士たちで、彼らは「富国強兵」「殖産興業」のスローガンの下、近代化を推し進めた。
明治維新に伴い、 西洋 から学んだ近代概念を基礎とした制度や思想が国全体の仕組みとして導入され、これにより 日本 は外からの圧力に立ち向かう「国家」としての基盤を築き上げていった。
この過程では福沢諭吉や西周といった啓蒙思想家たちやそのグループである「明六社」などが概念の整備に中心的な役割を果たし、彼らは先ほど挙げたような 西洋 の近代概念を 日本 語に翻訳し、それを出版物として一般の人々に広めていった。
政府自体も、近代化のために 西洋 からの学びを重視していた。多くの留学生を欧米に派遣し、 西洋 の制度や思想を学ばせる政策を実行した。それらの留学生の中には後の政府高官や教育者、実業家となる者も多く、帰国後には近代 日本 の基盤となる制度や企業を創設し、官僚として国家運営に携わった。特に、伊藤博文や大隈重信などの留学経験者は、ドイツの法制度やイギリスの議会制度を取り入れ、明治憲法の制定や国会開設に大きく貢献した。
これらの改革により、 日本 は技術革新と制度革新を同時に進めることで、短期間で近代化を成し遂げていった。
産業では、繊維業などを中心に大量生産・大量輸出が行われるようになり、江戸時代に育んできた高度な技術力が活用された。
この結果、人々の生活様式も大きく変化し、「出稼ぎ」が増え、移動の範囲が大きく広がるなど、大衆文化が花開いた( 文明 開化)。
そんな流れの中で、 西洋 生まれの近代概念たちは 日本 人の生活に次第に浸透していくこととなる。
大隈重信や中江兆民といった自由民権運動の先導者たちは、近代的な民主主義の思想を広め、国民の権利意識を高めるための活動を行った。彼らは、国会開設の要求や地方自治の導入などを訴え、 日本 の政治体制の近代化に大きく寄与した。
以上のように、列強の外圧に端を発して急速に行われていった 日本 の近代化は、内外の状況の変化に対応しながら、独自の道を進んだ。
その過程では、 西洋 発の様々な概念たちも 日本 人の生活にジワジワと入ってきて、 日本 の文化や「社会」に新たな色彩を加えていった。この結果、 日本 は近代国家としての地位を確立することができたとされている。
-近代の延長
二、日露戦争から終戦
日露戦争(-1905年)の勝利後、 日本 の「社会」構造は、その賛美と優越感の中で大きく変化した。明治維新直後の前近代的な価値観と近代化による 西洋 的価値観が共生していた雰囲気から、一種の全体主義へと向かう流れが生まれた。この全体主義の萌芽は、明治維新以降の「欧化」政策や、日露戦争前後の国家主義的な教育政策と連携し、「社会」の全体化と国民の一体化を推進していった。
特に教育の変化は、その全体主義の流れを最も象徴していた。
明治初期の「復古」と「欧化」の間で揺れ動いた教育政策は、日露戦争後、森有礼文部大臣の指導の下で国家主義的な方向へと大きく舵を切った。この新しい教育政策は、儒学や漢学といった 日本 の教育史を千年以上支え続けてきた伝統的な学問を二の次にし、 西洋 の科学的知識を重視するものであった。その結果、 日本 の教育は「大衆化」し、「近代化」され、全体主義の思想が広く浸透する土壌が作られた。
この全体主義の浸透において、メディアの役割も無視することはできない。戦時中、新聞やラジオは政府のプロパガンダを広め、国民を一体化するために重要な役割を果たした。これらのメディアは、戦争の正当化と国民の士気高揚を図るために利用され、批判的な意見や異なる視点は徹底的に排除された。
このような全体主義的な流れの中で、 日本 は徐々に戦争へと没入していく。政府は国家主義的なイデオロギーを強調し、国民の統一と戦時経済の活性化を図り、言論の自由は制限され、政府の意向に反する情報は厳しく統制されるようになる。国民の犠牲と忍耐が強調され、個人の利益は国家のために犠牲にされるべきであるという考え方が浸透する。
その結果、次第に 日本 にとって不利な戦況となり、1945年には広島と長崎への原子爆弾投下により、 日本 政府はついに終戦を宣言することになる。
その後、戦争の歴史を分析する研究は数多積み重ねられてきた。だが、これらの分析よりも前に我々が受け取らないといけない根本的な示唆は、「近代」によって作られたインスタントな「社会」制度やその基礎となっている概念そのものが、 日本 的な自然観や風土に根ざしていないために中身がないままに「暴走し、限界が生じた」という一つの大きな史実なのではないだろうか。
三、戦後GHQから高度経済成長まで
戦後の 日本 は、連合国(主に米国)による占領下に置かれ、政治、経済、教育、文化など、あらゆる面で大きな変革が行われた。
その一つが「日本国憲法」である。この憲法は、「大日本帝国憲法」とは一線を画すものであり、戦前の 日本 「社会」が持っていた近代的な概念を根本的に見直すものであった。
「大日本帝国憲法」は、天皇を国家の統治者と位置づけ、絶対的な権力を保持するという観念を内包していた。それに対し「日本国憲法」は「主権在民」を明確に掲げ、天皇の地位を「国家の象徴」へと大きく変えた。この憲法は、平和主義、民主主義、基本的人権の尊重という近代的な概念を強く打ち出し、戦前の 日本 「社会」に存在した封建的要素を払拭した。
戦後復興期には、全国的な復興計画が推進され、産業の再建と 都市 の再建が急ピッチで進んだ。特に1950年代から始まる高度経済成長期には、 日本 経済は世界でも有数の成長を遂げ、 都市 化が急速に進んだ。
日本 人の勤勉さや働き者の側面、敗戦による「意味」の喪失と新たな近代的 「豊かさ」 という夢の獲得、戦時中に画一化された国民観や大衆 メディア の存在は、大量生産大量消費に大きく貢献し、圧倒的な経済成長を生み出した。
この時期には、農村から 都市 への人口流動も進み、「社会」の構造自体が大きく変わった。
それと同時に、教育改革も行われ、六・三・三・四制が導入され、全国的に教育の機会均等が図られた。これは、教育を通じて「社会」全体を近代化し、民主主義の理念を広めるための政策でもあった。
この時期には、マス メディア の力も増大し、情報の流通が活発化した。テレビが普及し、新聞、雑誌の発行部数も増え、情報が広く一般に伝えられるようになった。これにより、国民全体が同じ情報を共有し、広範な議論が可能となった。これは、民主主義社会の形成に大きく寄与した。
しかし、高度経済成長が進む中で、 都市 化に伴う社会問題が次々と浮上してきた。公害問題、過密 都市 の問題、 都市 部と地方との経済格差の拡大など、急速な経済成長と 都市 化がもたらした負の側面が顕在化した。それに伴い、社会保障制度の整備や公害対策など、新たな社会政策が求められるようになった。
教育面では、従来の詰め込み教育に対する批判が高まり、より個々の能力や特性を伸ばす教育へのシフトが求められた。教育基本法の改正や新しい学習指導要領の導入など、教育改革が進められた。さらに、大学の民主化や学生運動の活発化も見られ、教育の場においても民主主義の理念が広まった。
このように、戦後から1990年までの 日本 「社会」は、戦前の封建的な「社会」から近代的な民主主義「社会」へと大きく変貌した。その中で、教育や メディア の変化が大きな役割を果たし、 日本 人の価値観や生活スタイルにも大きな影響を与えた。
より近代概念が「社会」を支えるようになり、 日本 人の生活や思考の隅々まで、近代概念が浸透していくことになった。それは一方で新たな社会問題を生み出し、常に新たな改革が求められる動的な時期でもあり、その繰り返しは「より良い社会を作っていく」という近代的な思想を一般的なものしていくことに大きく貢献した。
四、バブル崩壊から失われた四十年
バブル崩壊後の1990年代から現在に至るまでの 日本 は、大きな停滞期だと言われている。経済の停滞とともに、「社会」の停滞、人々の精神的な停滞感もまた深刻であった。
1990年代に入ってからの情報技術の発達は驚異的で、インターネットが普及し、情報社会が到来した。しかし、画一化された教育や社会制度により、ソフトウェアの時代に適応できなかった 日本 ではイノベーションを生み出す力が衰え、新たな価値観や視点を持つ人々が「出る杭」として打たれ続けて、経済成長は頭打ちとなった。
二千年代に入ると、「ゆとり教育」が導入され、個々の能力や特性を伸ばす教育へのシフトが試みられた。しかし、画一的な教育環境で育てられた既存の教師のマインドセットに、この新たな高尚な教育理念を浸透させるのは想定以上に難しく、結果として「ゆとり教育」は半ば「失敗」とされた。
同じくこの時期、家族構造の変化も顕著であった。核家族化が進行し、地域社会のつながりが希薄になった。この結果、祖父母世代からの「継承」が途絶え、 日本 の文化や伝統が失われる原因となった。この核家族化で失われたものは、実は文化や伝統以上にもっと根深い可能性については後で詳述する。
こうして「近代社会」が成熟し、情報技術が発達する中で、 日本 人は 西洋 生まれの概念や思考性に支配され、 日本 の前近代的な自然観はほぼ消失した。
「 人間 」「大衆」「主体」「個人」「社会」 「幸福」 「国家」「自由」「自然」、今日、私たちの生活や秩序の支えとなっているのは、 西洋 生まれの近代的な価値観や概念であり、それが私たちの「社会」を形成している。こうした概念は、日本的自然観とは全く異なる環境・歴史から生まれ、インスタントに翻訳されてきたものであり、その歴史は極めて浅く、短いのだ。
以上のように、 日本 社会は明治維新以降、 西洋 生まれの近代的価値観や概念に基づいて発展してきた。令和に入った今でさえ、この国は依然として「近代の延長」上にあるのだ。
“The German people were a mature race.
If the Anglo-Saxon was say 45 years of age
in his development, in the sciences, the arts, divinity, culture,
the Germans were quite as mature.
The Japanese, however, in spite of their antiquity measured by time,
were in a very tuitionary condition. Measured by the standards of modern civilization,
they would be like a boy of 12 as compared with our development of 45 years.”
-マッカーサー Senate Committees on Armed Services and Foreign Relations (1951)
-七十年代の沼
「近代」を批判的に見る動きは、六〇年代から八◯年代にかけて活発化し、リオタール、デリダ、フーコーをはじめとした思想家を中心にポストモダニズムの哲学や思想として流行した。
ガルトマンやフランクフルト学派をはじめとした社会学者たちは資本主義の皺寄せを非難し、アートの分野でもポストモダンアートが流行し、レイチェルカーソンに見られるような環境問題に問題の根幹を見出す意識も高まった。
フェミニズムや反植民地主義などもこの時期に広まりを見せ、医療教育分野への批判もイヴァンイリイチをはじめとした学者たちによってまとめられた。
日本 でも、学生運動や新左翼運動が活発化し、三島由紀夫や吉本隆明、西田幾多郎など、様々な分野までその流れは広まっていった。
しかしそうした批判と同時に挙がってくるオルタナティブの多くが、近代で生まれた問題を近代以降に作られたゲームの中でどのように解決するかという視座に立っているものだった。このゲームの構成要素が、近代概念とその背景にある 西洋 の歴史そのものであるという全体俯瞰からの完全な脱却( 脱構築 )が図られることはほとんどなかった。
三島由紀夫は自衛隊に見出そうとした希望さえ打ち砕かれて 切腹 したし、イヴァンイリイチのコンヴィヴィアリティには日本的自然観への直覚は存在しなかった。環境活動はこの「社会」に更なるルール(規制)を増やすという方向にしか働かなかったし、あらゆるパンクな取り組みはニッチなヒッピー文化に閉じ込められた。
また近年の「社会をよりよくするために」生まれてきている様々なオルタナティブたちもまた、よりその傾向が強いものとなっている。
数多の自己啓発本や、ビジネス書、流行している新たな概念の数々もまた、その流れを汲んでいる象徴のような存在になっている。
そうした「 七十年代の沼 [19] 」とも言うべき取り組みに熱を上げている人たちの煌めいた主張は、更にこの「社会」の隅々に「息苦しさ」を生み出すことに繋がっている。
「ダイバーシティを!」
「インクルージョン!」
「人権人権!」
「自由自由!」
「誰一人取り残さない!」
「より幸福に!幸福な人生を!」
「私は私、あなたはあなた!」
「Win-Winな関係を!」
「SDGs!」
「男女平等!」
などなど、こうした 西洋 発祥の概念たちを守破離していない取り組みは、真剣に取り組めば取り組むほど、「 人間 」の「認識」の層を分厚くし、解像感を上げていくことに貢献している。 虚構 に 虚構 を重ねることで 虚構 の穴を埋めようとする 沼 なのである。
このように私たちの身近なところにはたくさん「近代」のフレームに無自覚に内包されたものが浮遊している。
脱近代を目指すためには、まず近代を形作る 「フレーム」 「概念」「幻想」の存在を常日頃から意識することが重要だ。特に、 日本 人にとっての「幻想」を見極める必要がある。
近代に「近代」で立ち向かっても問題の根幹が解決されないのは、「近代」をしっかりと守破離した上で、 日本 的な歴史と自然観に基づいたオルタナティブがいつまでも提示されていないからではないだろうか。
また、あらゆるサプライチェーンがグローバル化し、一人一人の生活がそうした近代的な資本主義の構造に支えられ、近代的な国家構造によって「安全」が守られている現状を鑑みると、こうした近代の延長を唐突に破壊して江戸時代に戻そうとか、近代概念を全て悪と捉えようという流れもまた、 くだらない ニッチな限界のある所業なのである。
「近代の守破離」とは、近代を否定して葬り去るのではなくて、「近代」というフレームを溶かして、もっと広く 手触り感 をもって物事を考えよう、というだけのことなのだ。
例えば、「自由」という概念は、非常に素敵なイメージ( 風景 )を持つ。心がスーっと晴れやかに風通しが良くなる感じがするし、みんながイキイキと目を輝かせているようにも感じる。ただ、とてつもなく曖昧な概念だ。「選択肢の 沼 」でも前述した通り、「自由」を追い求めても、「そこには何もなかった」という事態は頻繁に発生している。「自由」という概念そのものを消すのではなく、そこにある素敵なイメージ( 風景 )を掴み取って、心のノートに留めておくだけで良いのだ。
それさえできれば、誰かと認識的に何かをやりとりするときに、こうした圧縮率の高すぎる概念を使うことに躊躇いを感じるようになり、より 手触り感 のある身近な言葉を使い始めるようになるだろう。
そうして一つ一つの近代概念を守破離することが、「これから」を考える「はじめの一歩」になるのである。
本稿で全ての近代概念の守破離を詳細に描くことは難しいため、こうした近代概念の守破離は各人にお任せしたい。守破離のコツは、ありとあらゆる視点と視野、表現方法で対象を捉えて、あらゆる可能性を探り続けることだ。
言葉で遊ぶのではなく、 風景 から言葉を紡ぐことだ。本当に貴方が伝えたいことが、その言葉で表現できているのか、一言一句、諦めずに、決めずに、考え直し続けることだ。
子曰、君子欲訥於言、而敏於行。
-「論語」里仁第四24
(つづく)