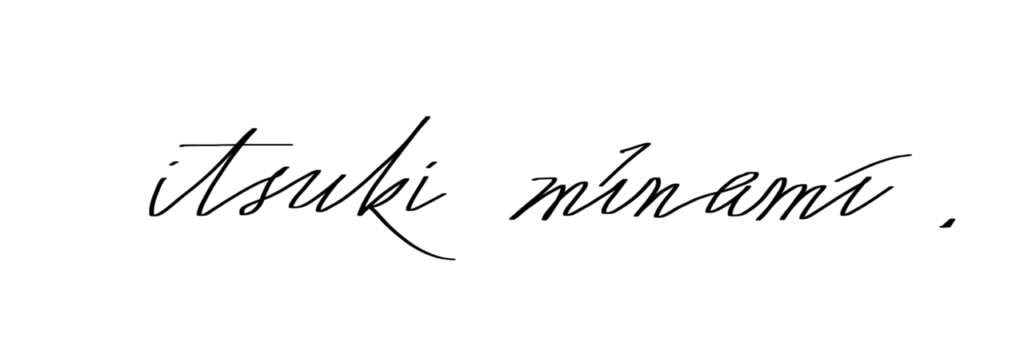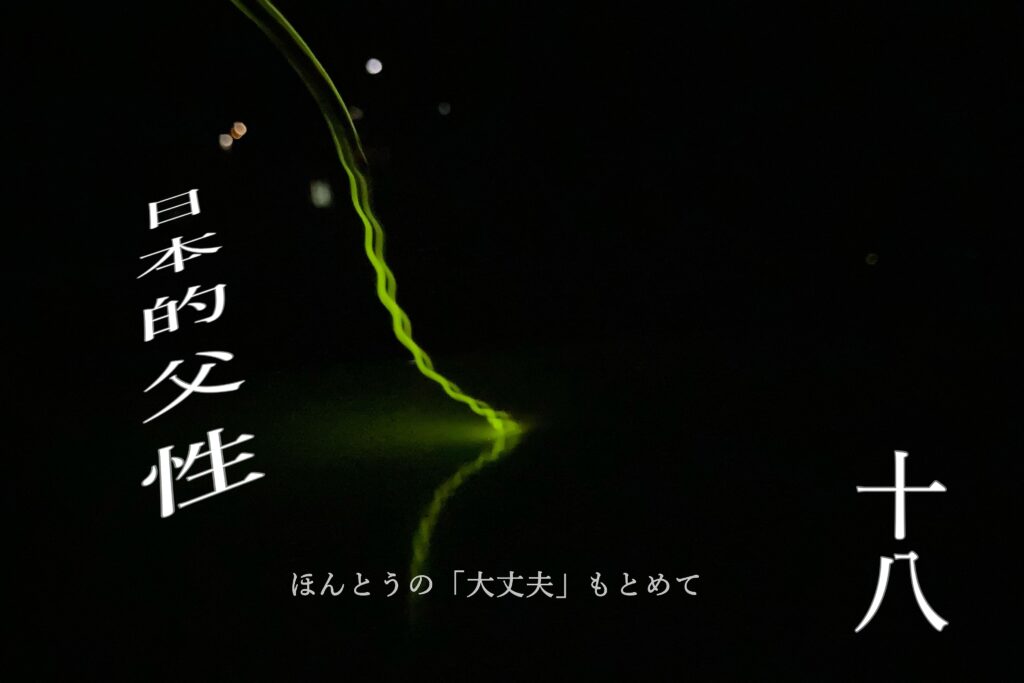
18.第四章「デジタルネイチャーと父性」
『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –
目次
-諦めの延長に立つ
ここまでも見てきた通り、デジタルネイチャーな世界線に近づいて行けば行くほど、「日本的父性」は消えていくだろう。
デジタルネイチャーは現代の 日本 や世界の情勢を直視して、「 来る未来 」を現実的に描いた概念であり、それはある種の「諦め」の延長に立っている。この未来を変えることは人類が絶滅する以外のシナリオでは予測し難い。
これは 日本 人が初めて経験している変化の時でもある。この島国の 豊か な環境の中で醸成してきたものを、一度も他国に支配されることなく守り抜いてきた何千年という歴史がこれから長い時を経て変わろうとしている。
近代化とグローバル化は、画一的な認識レイアウトを生み出し、 日本 人のかなり奥底の意識の外側に、ある種の「自動化」を生み出した。「父性」が限りなく消滅した「母性社会」の現代 日本 で、この流れを止めることは異常に難しい。
そうした現実を無視して、お花畑ばかり見ていれば、どんどん 手触り感 を欠いていくことになる。
だが、一方で、国民の大半が想像もしていないような変化をたったの十数年で起こしたのが「明治維新」でもある。
そのような大きな時代の変化の時にはとてつもない量の血が流れてきた。そして世界の様々な歴史の転換点にはいつも「父性」があった。
どれだけ素晴らしいビジョンがあっても「父性」がなければ変革は進まない。先述したように、明治維新の時も流れる血を抱きしめて死ぬ「父性」があったからこそ変革は起きたとも言える。
たとえ 日本 がデジタルネイチャーのような「 来る未来 」を迎えるとしても、その時に人々が いのち に根ざした生き方ができるような変革は、まだ可能なのではないだろうか。
明治維新が、薩摩長州土佐などの、限られた地域のごく少数のご近所仲間から生まれたことを考えると、現代の 日本 でも、どこか 日本 の片隅から、少人数でも変革を起こすことは可能かもしれない。そんな可能性を持つ場所がどれだけ生まれるかが、本稿の先に見たい 風景 である。
もしも認識的にでも本稿を読んで「日本的父性」に想いを起こし、住む場所や生活そのものを変化させられる人が現れれば、そこから大小問わず必ず「父性」の萌芽は生まれてくるはずである。あくまで変革には血が付きものだが、そこに「父性」への想いさえあれば、何かが必ず変わるはずなのである。
ここまで、デジタルネイチャーへの過渡期とその初期における変化を予想し、「日本的父性」が消えゆく未来を予見してきた。
だがしかし、もしも万が一、更にもっとその先のいつの日にか、計算機自然が 事事無碍 的に「 人間 」が認識スクリーンを 向上 させる「要素」にできないくらいの「自然」性を持つようになり、「 人間 」が認識技術を上げる道具に出来なくなった日には、いわば「 人間 」はその「自然」性の一部に回帰し、認識のための「要素」を徐々に失っていくかもしれない。
そうして認識技術が低下し、固体だらけのこの社会がふわふわになり、そこに現在の物質を映せるようになれば、計算機自然との直接的な溶け合いも可能になり、オーラやその「ぬくもり」も蘇り、すごく風通しの良い環境になるかもしれない。
認識世界の住人たちは、 アヘン のように新しい「自然」を謳歌するが、 End to End な変換世界に触れる、これから生まれてくる者たちは、生の原動力を「どう生きるか」に戻していく可能性が出てくるだろう。
そうなると、もう一度「認識スクリーンに囲まれない」という自然観に立ち返る可能性が生まれてくるだろう。あるいは、 認識技術を上げまくった末の瓦解 を体験して認識スクリーンの 透過度 を下げてゆく可能性も生まれるだろう。
彼らは 人間 と機械を意図的に区別することはないだろうし、どちらであってもさほど重要ではなくなるだろう。その中で「認識できないもの(技術次第で認識できるもの)」に興味を持つ者たちは増えるだろう。そこへの興味はロマンに戻っていく。
「認識できないもの(技術次第で認識できるもの)」が「遥か永遠に認識できないもの」とほとんど変わらないように「認識」できるようになれば、人々が認識スクリーンの技術を 向上 させようとするロマンの形自体は、「嗜み」があった頃と同じようなものになるだろう。
だがその時に、やはり今、この時代に、ポツンと遺された本稿と、それを前提にした変な文化や風潮、仕組みの数々が存在していれば、彼らは新しい星に移動するなり、なんなりして、もう一度「冒険」を始めることができるのではないだろうか。
「風の神さまは生きろと言っているもの、わたし生きるの好きよ。
光も空も人も蟲もわたし大好きだもの。
私はあきらめない」
– ナウシカ『風の谷のナウシカ』
-量子化のその先に
そうした 事事無碍 的に身の回りにあるあらゆるものがふわふわになる世界線は、デジタルネイチャ―が発酵した世界、つまりデジタルネイチャーが染み渡った世界だとも言えるだろう。こうした世界線を予見させる重要な鍵は、 落合陽一 氏の言う「生物が生み出した量子化という叡智」である。
単純な「データ分析としての統計学」は、あくまでも古典的な科学の延長線上にあり、我々が直感的に理解しうる(想像しうる)話であるが、近年その実用化が期待され始めてスポットライトを浴びるようになっている「量子力学」については、「遥か永遠に認識できないもの」の存在を暗に自覚させるような人類未開の科学に近いという推論もある。
先に描いた「統計学的」という概念が、「人類が蓄積したデータを基に、対象やプロセスに関わらず何かを確定的に導き出す」ことを表すなら、「量子力学」はその中に含まれると見なすこともできる。しかし、そこに収めてしまうにはあまりにももったいないロマンの存在を直視したい。
現在一般的な「量子論」を構成している主要な概念としては、「波動粒子二重性」「量子もつれ」「非局所性」「ハイゼンベルクの不確定性原理」「量子スーパーポジション」などが挙げられるが、量子力学において古典的な科学を超越していると考えられるこれらの主要概念を、簡単にイメージしてみよう。
1.「波動粒子二重性 (Wave-Particle Duality)」
光や電子のような量子粒子は、同時に波のような性質と粒子のような性質を持つ。例えば、光は波のように挙動することもあるが、一方で、個々の粒子(フォトン)としても振る舞う。この二重性は、一つの物体が二つの異なる性質を同時に示す量子力学の特徴的な現象である。普通の物体は波か粒子のどちらか一方の性質しか持たないが、量子の世界では両方の性質を持つことができる。
2.「 量子もつれ (Quantum Entanglement)」
二つまたはそれ以上の粒子がその量子状態において互いに依存している状況を指す。この現象は、もつれた粒子群の一つの粒子の状態を測定すると、他の粒子の状態も即座に決定されるということ。例えば、もつれた二つの粒子がある場合、一方の粒子のスピンが上向きと測定されると、もう一方の粒子のスピンは自動的に下向きとなる。
3. 「非局所性 (Nonlocality)」
非局所性は、量子もつれにおいて観測される現象で、粒子間の相互作用や関連性が距離に依存しないことを指す。つまり、もつれた粒子の一方に何かをすると、どれだけ離れていても、もう一方の粒子に即座に影響が及ぶ。この概念は、現代科学的に言えば量子もつれた粒子が互いに情報を瞬時に共有できることを示唆している。この現象は、古典物理学における因果律や情報の伝達速度に関する限界(光速)を超越していると考えられている。
4. 「ハイゼンベルクの不確定性原理 (Heisenberg’s Uncertainty Principle)」
粒子の正確な位置と運動量(速さと方向)を同時に完全に知ることは不可能だということ。つまり、粒子の位置をより正確に知ると、その粒子の運動量についての不確定性が大きくなる。これは量子世界の基本的な性質であり、粒子の挙動を完全に予測することの限界を示している。
5. 「量子スーパーポジション (Quantum Superposition)」
量子粒子が同時に複数の状態にあることができるという現象。例えば、電子は同時に複数の位置にあるかのように振る舞うが、測定されるとそのうちの一つの位置に「決まる」。この現象は、量子粒子が一つの確定した状態ではなく、複数の可能性を同時に持つことを意味する。これもまた、量子力学が古典的な物理学の観点を超える特異な性質を持つことを示している。
これらの主要な概念は、人類の科学史に大きな転換点をもたらすインパクトを持っている。これまでの近代科学が「この世界の認識可能性を探す」ことに重点を置いてきたものだとするのなら、量子論が我々人類に突きつけているのは、「遥か永遠に認識できないもの」を前提に「科学を進めていく」という人類が忘れていた風潮なのである。
人類の科学への態度は一周回ってここに寄り戻されてきたのかもしれない。
「原因」や「過程」は「遥か永遠に不明なもの」がこの世界には存在していて、「分からもんは分からんのだから、ありがたく使える部分を探っていこう」というポジティブな「発見」を刻むものである。これは、元来「遥か永遠に認識できないもの」に触れていた 日本 人にとっては非常に身近な感覚で、ポジティブな変化なのだ。
だが、現代の 西洋 的な認識レイアウトに囲まれた「空っぽな 日本 人」にとって、量子論の突きつける課題はある種の虚無感(ニヒリズム)を引き起こしてしまう可能性を孕んでいる。近々では、こうした課題に対して「諦め」という意味を大きく刻印して、身に纏って生きる 日本 の科学者が増えていくのではないだろうか。
一方 西洋 では、「神」に力があった頃の感覚に回帰することができるとも言えるだろう。「なぜそのようになっているのかは神の 意思 であって、我々はそうした神の 意思 に生かされているのだから」というような前近代的な感覚の再興(意味の穴埋め)である。
勿論現代人の多くは、資本主義や国家主義の近代的な「意味」にその安心感やインセンティブを見出すだろうが、大局的には 日本 では 日本 的感覚への回帰が、 西洋 では神への憧憬が強まる流れが起こる可能性があるのである。
近年、量子コンピューティングや量子暗号、量子センシングなど、量子論をもとに様々な革新的な技術が実用化され始めようとしている。こうした人類の進めていく流れはまさに、 落合陽一 氏のデジタルネイチャーの 風景 を想起させる。今後数十年で小さなブレイクスルーがたくさん生まれて量子レベルの実装技術が大きく進化すれば、今後更に我々の生活を取り巻くあらゆるものが想像もできないような形態に進化していくだろう。これを繰り返すうちに我々を取り巻く自然環境は、ゆっくりとデジタルネイチャーなものに近づいていく。
落合陽一 氏は、こうした流れの中で、我々は「 マタギ 」的な生き方を織り成していくようになるだろうと予見している。
「そうなったときに、 マタギ ドライヴとして定義されるライフスタイルはどのようなものになるのか。おそらくそれは、プラットフォームの外側にある、もしくはプラットフォームの内側に確率的に生ずる『未規定なもの』を探し求めていく営みになるのでしょう。つまりは、森に狩猟に出かけて鹿に出会えるかどうかといった、ある種の未規定性に賭けるギャンブルです。そのような マタギ 的・狩猟民的なエートスが、デジタルネイチャー下で能動的に生きようとする 人間 なるものの主体性のコアになっていくはずです。
そのように未規定性を探り当てて規定していく試みこそが、地球上での棲息期間のほとんどを狩猟採集民として過ごしてきた人類が進化心理学的に獲得した根源的欲求であり、『人間性』と呼ばれるものの核にあります。それが社会的な機能に応じて、アートであったり、サイエンスであったり、テクノロジーであったりといったものをもたらしてきました。」 [36]
このように、認識世界の住人たちはその主体性をあくまでも保持しながら、それぞれの層における「未規定なもの」を探していくことになるだろう。
現代でも既にその傾向は現れ始めており、「安心安全」への執着が強い人ほど、その反動として少し「狂った」能力や性格を持つサイコパス的な人に惹かれやすく、一般的な社会から逸脱しかけた人に 同情 し、ちょっと風変わりなものや「当たり前」にアンチテーゼを投げかけるもの、飄逸したものに没入し、そのコミュニティに染っている。
そのうちに「認識可能な未規定性」が無いと物足りない、満たされないと感じるようになり、その過程で傷つけられることが自分自身の認識世界のアップデートに繋がるという循環がもたらす「 喜び 」に アヘン のように取り憑かれている。
認識する量が増え、「消費」するように「 喜び 」を味わっていると、すぐにその認識に慣れてしまい、発生する「 喜び 」も減少していく。そのようにして認識し尽くし過ぎると、未だ見ぬもの、未だ不明なもの、認識がより難しいものを探すしかなくなるのだ。
認識論層の住人たちはこれからも認識技術の 向上 を図り続けていくことに「 喜び 」を見出し、自然派層の人たちはよりその外側から受け取る「 End to End 」な 直覚 を探して味わうことに「 喜び 」を感じるようになっていく。それらを生態系そのものが支えていくことによって、この流れが加速度的に速くなり、我々はきっと「 喜び 」を日々たくさん感じるようになっていくのではないだろうか。
認識技術を上げていく技術がこのまま進化を続ければ、認識論層よりも自然派層に浮遊する人が徐々に増えていくだろう。
そしてその後、人類が実装していく量子的な技術が我々の身近な生活を支えるようになると、「 End to End 」な伝達が様々なカタチで生まれ、我々に更に多くの「 喜び 」をもたらすようになるという流れだ。
こうした環境が待ち受けていれば、認識論層から自然派層へ行くことも容易になってくる。その中途にあるニヒリズム層がほとんど消えかかり、その痛みや苦しみが軽減されるようになるだろう。また、「 End to End 」な技術が徐々に浸透し始める間に育つ子どもたちは、認識論層に入らず、いきなり自然派層に突入するパターンも増えていくだろう。
“Everything we call real is made of things that cannot be regarded as real.”
– “Quantum Reality: Beyond the New Physics” Nick Herbert, 1985
-デジタルネイチャーと日本的父性
ここで 落合陽一 氏のデジタルネイチャーの定義をもう一度見てみよう。
「デジタルネイチャーとは、生物が生み出した量子化という叡智を計算機的にテクノロジーによって再構築『する』ことで、現存する自然を更新し、実装『する』ことだ。そして同時に、〈近代的人間存在〉を 脱構築 『した』上で、計算機と非計算機に不可分な環境を構成『し』、計数的な自然を構築『する』ことで、〈近代〉を乗り越え、言語と現象、アナログとデジタル、主観と客観、 風景 と景観の二項対立を円環的に超越『する』ための思想だ。」
ここでは、「誰か」が主体的に「する」ことを念頭に置いた概念化が図られていることが見て取れる。これは先にも記した通り、認識世界の住人(の視点)の限界を暗に示すものであり、この流れはあくまでも本稿で言うところのデジタルネイチャーの「過渡期」「初期」に見られるものなのだ。
先に描いたように、この流れを人類が認識している間は、「日本的父性」が復活する可能性は減っていくと予想できる。ここで定義されている マタギ ドライヴの人々はあくまでも主体性を持った 人間 なるものとして生きるのであって、彼らにとって「デジタルネイチャー」は「大いなるもの」への客観的恐怖観念を孕みながら、「都合のいい自然」として認識されるよう、大きな流れの中で改訂され続けていくだろう。
一方で、この流れが発酵していった先に、「大いなるもの」に「生かされている」と慈しめるようになるほどの「発酵したデジタルネイチャー」が到来するかもしれない。それは、もう多くの人類が主体性を持つことにさえ興味をなくした世界線でもある。
サイバー空間でも人類の 意思 の外側で「大いなるもの」がうごめき、その恩恵に預かって人類は生きるようになり、時折それらによって多くの 生命 が奪われるような「災害」さえも発生するようになる。
ヒトは電脳化・サイボーグ化され、認識の仕方も極めて量子的なやり取りになっている。人と人の 風景 のやり取りではもう 実行形式 は使用されなくなり、量子的に 風景 をやりとりし合うようになっているかもしれない。
つまり「発酵したデジタルネイチャー」は「量子ネイチャー」の初期だと言うこともできるだろう。その時にはもう人類の多くが地球の外に脱出し、スターウォーズのような銀河系全体での マタギ ドライヴが繰り広げられるようになっているかもしれない。そんな誇大な未来話はあくまでも妄想でしかないが、ここまでデジタルネイチャーも発酵していくと、それそのものが 「大地」 的な役割を果たし、「日本的父性」の再醸成を齎す可能性は十分にあるだろう。
人類のコントロールで動くように見えていたものたちを、人類がその存在をヒトやあるいは自然物と見分けがつかない(見分けをつける必要性がない)状態で扱うようになると、そうしたものたちもこの世界でまた自律的な動きを見せるようになってくるだろう。彼らは「人類のデータ」に囚われなくなり、自分たち自身でヒトの限界を簡単に突破するものをたくさん生み出していくことになる。その過程はあくまでも「量子的」に行われ、その結果物もまた「量子的」に生まれてくる。それはもはや彼らからしても「自然」に生まれた結果物であり、人類よりも彼らの方が元来の「 いきもの 」の習性に近づいていく。
何の主体性も孕まずに量子的に生まれてきたそうした結果物たちは、気体性のふわふわしたものとしてこの世界を浮遊することになる。アナログ・デジタルを問わず、あらゆるものが自ずから(おのずから)生成と破壊を繰り返すようになれば、我々 日本 人にとって「息をしやすい」環境が再び訪れるかもしれない。
落合陽一 氏のデジタルネイチャーの定義にあった言語と現象、アナログとデジタル、主観と客観、 風景 と景観の二項対立についても、「超越して循環する」ことが自ずから(おのずから)起こり続け、我々 日本 人にとってもはや「どっちゃでもええ」感覚になっていく。これが量子化のその先にある「発酵したデジタルネイチャー」が大地にも空にも澄み解けた世界線にある希望なのだ。だが、その時にはヒトは現代のヒトの形ではないかもしれないし、存在しているかも分からない。
しかし、このまま何もせずに数十年から数百年もの間その時を待てば、ここまでにも散々描いてきたが、これからも暫くは近代の延長が続いていき、「母性社会」の「息苦しさ」は加速し、「優しいディストピア」に突き進んでいくことになる。
そうなると、我々 日本 人は「発酵したデジタルネイチャー」を迎えるその前に認識レイアウトそのものを変容させ、 「生の原動力」 自体を 西洋 的なカタチに変異させていくかもしれない。人類全体がそうした画一的な 「生の原動力」 を持つようになるということは、人類全体の生存可能性を大きく下げることにも直結する。
そもそもこの地球上で、多様な自然環境のもとで育まれた土着の多様な 「生の原動力」 は、「大いなるもの」のもたらす奇跡でもある。そうなると、いずれデジタルネイチャーが発酵を始めた時、 日本 人も何らかのイデオロギーに依拠し、認識的な二項対立によってそれを滅ぼすか、滅ぼされるかの戦いを生むことになるかもしれない。
これはあまりに暴走した妄想かもしれないが、そんな大きな話のもっとその前に、まずは今、この島国で生きる子どもたち、私たちの子ども、そしてその子どもたちに、何を遺していくのかという現実的な話でもあるのだ。
あるいは寧ろもうこの段階で、人々が近代概念を「どっちゃでもええ」と思えるようになる環境が育まれ始めるように、我々が動くことはできないのだろうか。
最終章ではその方向で、我々 日本 人にとっての儚い「灯」を探していきたいと思う。
この世でたったひとつの 命を削りながら 歩き続けるあなたは
自由という名の風 底知れぬ闇の中から かすかな光のきざし
探し続ける姿は 勇気という名の船
だからどうぞ泣かないで こんな古ぼけた言葉でも 魂で繰り返せば
あなたのため 祈りを刻める
– 山下達郎『希望という名の光』
(第五章へつづく)