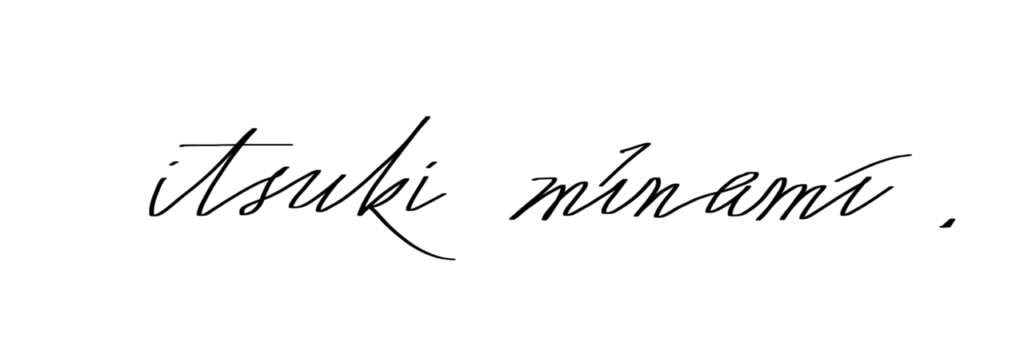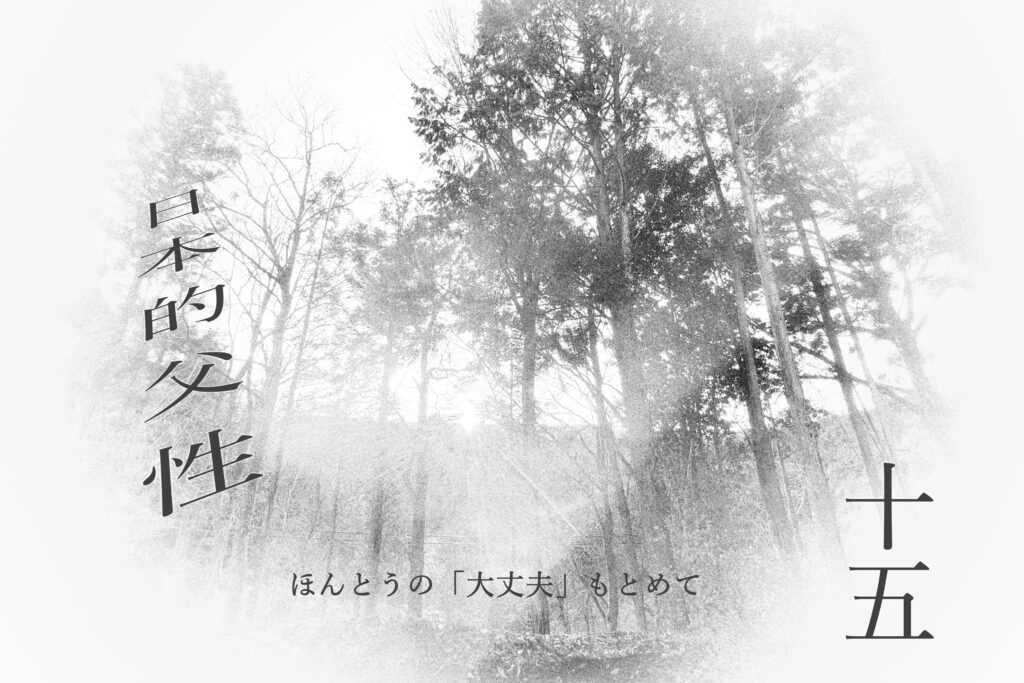
15.第三章「大地性と日本的父性」
『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –
目次
-当たり前と「許し」
さて、第一章で「父性」における「許し」について解説したが、そもそも「許し」とはなんだろうか。
許すことと諦めることの違いは何だろうか。
「日本的父性」での「許し」とは、現代のグローバルな意味合いでの「許し」とは少し違う。近年よく使われる「許し」は、一神教的な歴史に紐づいている場合が多く、それは 日本 的な「許し」とは少し異なるのである。
そもそも「許」という漢字は、「言う」の意味と「きね」の形をした神体の象形から、神に祈って「許される」「許す」を表すようになったとされる。 日本 でいう「神体」と聞くと、先述した「気体性アニミズム」の 風景 を思い浮かべる。
「気体性アニミズム」レベルでの「許し」は、極めて「当たり前」のことであり、それはつまり いのち そのものと向き合うということでもある。日本的自然観における 「全」 と「一」の遥か永遠に広がっていく関係性の中では、あらゆる個々の事柄は、「許し」と共に触れることができる。
「母性社会」の章で、「やるせなさ」と「 生命 を断ち切る」行為の関係性を描いたとき、「『この連鎖の中のどこに恨みを集中させるか』、または『この社会自体に絶望するか』は、人の想像力などによるところなのである。」と書いた。ここでいう「想像力」が、日本的自然観に根付き、「気体性アニミズム」に溶けていた場合、その人は「恨み」そのものを「融解・抱擁・輝化」させることができるだろう。そもそも日本的自然観の中では「許し」は当たり前のものであって、存在する必要がないとも言えるのだ。
しかし、現実問題として、それはいつの時代も多くの人にとって難しい。認識世界を生きる現代の人々が甚だ不可能に近いことは言うまでもないが、生来の感性がとても 豊か で、 「全」 に触れられる人ほど、あまりにも 豊か な痛みや苦しみに直接触れてしまうため、それを「許し」というフィルターを主体性を持って世界のどこかに設置して抑える必要性が出てくるのである。例えそれがどんな人だとしても、そうしたネガティブな感情は人を飲み込んで、病的な症状を作り出してしまうものなのである。だからこそ、こうした嗜みレベルでの「許し」の力(技術)が、非常に重要なのである。
しかし、「固体」をそのままにして、視点や視野、表現方法を変えたり、認識を避けて感情を抑えることを、 「日本的父性」の「許し」とは言いにくい。
「日本的父性」における「許し」とは、「固体」を「気体」状態にするということでもあり、この力があるということは、「融解・抱擁・輝化」できる範囲が広いということである。
昔の仏教や漢学、兵法、儒学などに関連するものは、こうした「許し」の技術を会得するために働いていた部分もあるのかもしれない。
こうした力を与えてくれるのは、お天道様や山河大地など時代が変わっても変わらずに「ただただそうであるもの」としていてくれるものたちなのである。
想像できないほどの「許し」という「父性」を 発揮 して、歴史を大きく動かした人物としてネルソン・マンデラ氏の存在は見逃せない。
南アフリカでは長年、アパルトヘイトという人種差別の国策が続いていた。そんな中、ネルソン・マンデラは若くして反アパルトヘイト運動に身を投じる。1964年には国家反逆罪で終身刑の判決を受け、ロベン島という離島の牢獄に投じられ、採掘場での重労働と過酷な獄中生活を課せられ続けた。ここで約二十年を過ごしたマンデラは、結核をはじめとする呼吸器疾患になり、目も痛めたという。それから別の刑務所に移送されたりもしたが、釈放されるまで計二十七年もの時間を獄中で過ごした。
1990年にようやく釈放されたマンデラは、アパルトヘイト撤廃に向けて活動を続けていく。1994年には、南アフリカ初の全人種参加選挙が行われ、マンデラが大統領に就任する。マンデラ政権は、アパルトヘイト体制下での人種間対立や政治的対立をいかに収束させ、全人種を融和させるかに最も心を砕いた。六つの原色に彩られた新国旗に象徴される「虹の国」を掲げ、新国歌を制定することを手始めに、様々な手を打っていった。
1995年には第三回ラグビーワールドカップが南アフリカで開催されるが、ラグビー南アフリカ共和国代表(スプリングボクス)は当時ほとんどの選手が白人で占められており、またラグビー自体が白人のスポーツとして黒人など他人種には不人気であったが、マンデラは開幕戦を直接観戦し、またスプリングボクスを国民融和の象徴として支援し続けた。そのこともあってスプリングボクスは快進撃を続け、決勝戦で再びマンデラが観戦する中で初優勝を遂げた。マンデラ政権下では経済格差を是正することがなかなかできなかったが、国民統合に関してはかなりの成果を上げたと言われている。
マンデラの残した言葉にこんなものがある。
「Resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies.(遺恨の念は、毒を飲んでおきながら、それが敵を殺してくれると期待するようなものだ。)」
「True reconciliation does not consist in merely forgetting the past.(真の和解はただ単に過去を忘れ去ることではない。)」
「As we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same.(私たち自身を輝かせることで、他の人たちにも同じことができる許しを無意識に与えるのだ。)」
「Part of being optimistic is keeping one ‘s head pointed toward the sun, one ‘s feet moving forward.(楽観的であるということは、顔を太陽へ向けつづけ、足を前へ踏み出すことである。)」
本稿でも述べ続けてきた大切なことがこうした言葉の背景にたくさん描かれている。
認識的に「忘れる」ことで、真の和解なんて生まれないし、誰かが生きることを許すためには、自分が いのち を輝かせてなきゃいけない。
どんなに辛い経験でも、遺恨の念は「不誠実の始まり」であり、その 沼 から抜け出す方法を大地やお天道様が教えてくれる、と。
「悔やむことも当然、やりきれぬ思いも当然。失ったものは大きく、得たものはない。
だが、これは前進である。戦った相手が誰であろうとも、戦いは起こり、今終わったのだ。
過去を無きものになど誰にもできはしない。この戦争の上に立ち、生きてみせよ‼︎」
-ネフェルタリ・コブラ『ONE PIECE』
-限界のない器
さて、お天道様といえば太陽、太陽といえば、「太陽の神ニカ」の話をしておきたい。「太陽の神ニカ」とは、本稿を執筆している現在、週刊少年ジャンプで連載中の漫画『ONE PIECE』の主人公ルフィの呼称の一つである。まだ読んでいない方には少しネタバレにはなってしまうが、少しだけお話しさせていただきたい。
日本 だけでなく世界中で人気を博す『ONE PIECE』は、「父性」の物語として非常に重要だと私は考えている。作中には、登場人物が「父性」を 発揮 するシーンが何度も何度も登場する。ほぼ全てのストーリー編において、「父性」にまつわるシーンが描かれているのだ。麦わらの一味全員が 発揮 する「父性」はもとより、始まりのシャンクス、バラティエ編のゼフ、ドラム王国編のヒルルク、空島編のノーランド、頂上戦争編の白髭、ワノ国編のおでん、エッグヘッド編のくまなど、物語中での「父性」の顕現は数えきれない。
また、そのそれぞれのストーリーが、かなり示唆に富んだものになっているのだが、『ONE PIECE』は、作品全体が「日本的父性」の話であるとも言える。ルフィの悪魔の実の正体が、「ヒトヒトの実幻獣種モデル『ニカ』」であると判明するのは、1000話を超えてからになるのだが、その実を食べたものの呼称として、「解放の戦士」や「太陽の神」という言葉が語られるのだ。
「父性」について語るときに、「器(うつわ)」の話は避けて通れない。「器が大きい」という言葉があるように、器が大きいほど、そこに入る量も増えるというイメージができる。だが、器を大きくして大きくして、大きくし続けていくことなどできるのかといえば、非常に難しい。どんなに器を大きくしても、陶器などの硬い器であれば、入れるものが限界を越えればどうしたって溢れるのだ。だが、「日本的父性」とは、固体ではなく気体性であるというイメージがすごく重要だという話をしたように、「日本的父性」における「器」は、硬くない。それは、一体どんなものが入ってきてもその大きさに応じて広げたり伸ばしたりして入れ続けることができる「器」である。それは、『ONE PIECE』におけるルフィの身体的特徴である「ゴム」の性質に似ている。硬い「器」であれば、その受け入れられる量に「限界」が決まってしまうが、伸びることができるものであれば、その受け入れられるものに応じて形を変えられる「器」ということにもなる。さらに、ルフィの悪魔の実の能力は覚醒を迎えると、周りの環境もゴムに変えていく。「父性」も同じく、周りに影響を与えて、周りにも「父性」を伝播させていく。
「太陽の神」(お天道様)が人々に認識を遥かに飛び越えて醸成していく「器」の性質は、「日本的父性」の 風景 とあまりにもリンクしている。ルフィの「みんなを仲間にしていってしまう」という不思議な性質と、「解放の戦士」と呼ばれる所以は、「日本的父性」における「認識スクリーンからの解放」という「超越」と、それを支えるために必要不可欠な「融解・抱擁・輝化」そして「大丈夫」の存在を暗示しているようにも感じられる。
また、この作品が現代の 日本 で生まれ、そして世界中へと広がっていること、これはとてつもないことである。「父性」という 風景 がまとめられたことがないが故に、人々は「父性」的なものを見て「父性」的だと認識できない。そうしてどれだけ「社会」(現実)で「父性」が消えていっても、それでも人々は「父性」的な 風景 に心惹かれ、心打たれることがたくさんあるのだと思わせてくれる。まだ読んでいない方には少し分かりにくかったかもしれないが、 日本 人はこの作品から「父性」について本当に多くのことを学べるし、各ストーリーで描かれていることは現代 日本 の問題とも深く結びついている。ぜひ、作中のセリフを何度だって読み返してほしい。表現は多少異なるが、本稿で伝えていることと同じメッセージを込めたセリフが非常に多いことに気が付くだろう。
物語の中で「父性」が極めて重要な役割を果たしているように、現代の多くの問題も、「父性」があれば想像もできないものへと変えていけるものが本当に多いのだ。
子曰 君子不器
-『論語』
-趣という希望
日本 人が長い歴史の中で培ってきた文化から学べることはたくさんあるが、もう一つ、大地が育んだ美意識である「趣」についてここで見ておきたい。
現代でも、「趣」という言葉はいまだによく語られるが、そうした美意識は近代とともに失われていった。現代の 日本 人の多くが、「趣のあるものはいい」という認識の自動化によって趣を語り、満たされるための道具にしている。同じような表現に「侘び寂び」というものもあるが、こちらも「なんとなく」使う程度の言葉と化している。
侘び寂びの文化が大きく花開く室町時代よりもずっと前から、古くなったものや欠けたものが、「調和」をもたらすことによって生む美について、 日本 人は非常に敏感であった。それは生活の知恵でもあり、自然環境の中での生存の産物でもあった。
「趣」や「侘び寂び」にとって非常に重要な「調和」という概念は、英語に翻訳するのが難しい。「バランス」や「ハーモニー」を「調和」と訳すことがあるが、その性質はまるっきり異なる。バランスは、二項対立や平面的な関係性を指す。「ハーモニー」は 「全」 を前提にしない「一」の集合としての「面」的な表現に近いとも言える。だが、「調和」は奥行きのある世界全体の話である。調和とは、突き通った一筋の線の 「ゆたかさ」 のこと、そのものなのである。
また、「趣」や「侘び寂び」においては、こうした「調和」を土台にした「不調和」が重要なエッセンスになる時もある。
このような 日本 独自の美意識は、「父性」にも重要な影響を与えてきたと考えられる。逆に、「日本的父性」があったからこそ生まれた文化だと考えることもできるだろう。
壊れたものや、欠けたもの、どんなものに対しても、「許し」の可能性を「諦め」ない無意識の精神性が、その先に見えてくる「調和」の取れた 風景 を生み出したのではないだろうか。この相互作用は決して簡単に無視できるものではない。
現在の 日本 ではこうした 日本 的な美意識を養う環境はほとんど存在しない。お見合いの減少に伴い、嫁入り修行としての茶道や花道に触れる機会も失われ、学校の書道授業は点数をつけるゲームと化している。「おばあちゃん」からの文化の継承が途絶え、「調和」に美を 直覚 する力は育まれなくなった。
どちらかというとスティーブ・ジョブズのような海外のニッチな 日本 ファンが、激しく「趣」や「侘び寂び」などの文化から影響を受け、現代社会に通用する価値を創出したりすることが多い。 日本 人はその成果物のファンになるしかないような状況がもうずっと続いているが、それはもしかすると、 日本 人にはやはり認識の外側のどこかにまだ「趣」的な感覚も残っているということなのかもしれない。
近年では、「個性を守ろう!」とか、「ダイバーシティを!」といったキラキラした言葉に内包されてボコボコにされている「我慢をする(忍耐を保つ)」という行いも、「調和」への 直覚 がある時代には、特に重要なものとして働いていた。
そのために「個性」は強制的に捻じ曲げられることもあっただろうが、あくまでもそれぞれに役割があって「調和」を成していくことが、地域を強くしたり、環境を守ったりするために重要だったのではないだろうか。
AかBかの認識で悩んでいる人にCをもたらしても混乱を招くだけかもしれないという「父性」の限界について、第一章の最後で言及した。「可愛い子には旅をさせよ」の基準はどこにあるのか、という疑問も第二章で提示した。また、それ以外にも例えば「日本的父性」における「大丈夫」は、大切な人が「失敗」や「ミス」をした時に、その全ての責任を肩代わりしてやるというような精神にあるのではない。失敗をしたら失敗をした分だけの責任を取るということを身を持って示すことも重要なのではないだろうか。
このように、どんな場面で「超越」「許し」「大丈夫」を齎すのか、どこまでを自分が引き受け、どこまでを相手に受け止めさせるのか、そうした基準が難しい場面が「父性」の生まれる場面ではたくさん存在する。
その基準を統計学的に弾き出すのではなく、時と場合に応じて、「自ずから」生まれ出る「調和」への 直覚 を 意志 を持って体現するという姿勢こそが、「日本的父性」においては重要なのだ。
それは、その人の生き様が齎す「調和」への 直覚 の力そのものなのである。
そんな 直覚 に大きな影響を与えるのが、「素読」によって育まれてきた認識的な要素たちと、認識不可能な「何か」の力なのかもしれない。
また、こうした「大丈夫」を、「誰に」持つのか、その誰かの基準はどうやって決めるのだろうか。
これも同じように、その瞬間の「調和」を土台にしたものの中からしか見えては来ない。
向き合わずに逃げることが癖である不誠実な 人間 に降りかかるものまで、身代わりになって引き受けることは、果たして本当に「大丈夫」なのだろうか。
そういった基準を認識的に書き連ねることは難しい。大いなるものの中で、長い歴史をかけて受け継がれてきた儒学や漢学にあったヒントは、こうした認識的な基準のカケラたちなのかもしれない。そして、そうしたカケラたちの中でも何度も言及されているように、誰かが誰かの「大丈夫」であるために、「我慢」や「忍耐」は必ずと言っていいほど求められた。「我慢」も「忍耐」も無いような人に、「大丈夫」をもたらしてくれる「調和」など生まれ難いのではないだろうか。
近年「人権侵害だ!」とか「平等!平等!」「基本的人権がどうの」とか、色んな 西洋 的な言葉が正義を謳っているが、そんな叫びを続ける「調和」になんの興味もない大人たちは、知らぬ間に消えていく「生まれ持った いきもの の可能性」に無頓着であったりもする。
また、「 人間 」が「我慢」をしなくていい「社会」を作って、そこで取れなくなった「調和」を「機械」が勝手に取ってくれる世界線を目指すような思想については、第四章で詳しく見ていきたい。
「我慢」の少ない人生が、巡り巡って「日本的父性」を育むことに非常に不利に働くということは、そうした煌めきのある認識たちが日々隠し続けて、もうほとんど誰からも見えなくなっている。「日本的父性」は、認識的なものも非認識的なものも含めた「調和」への 直覚 の先にしか生まれてこないのだ。
「父性」の典型的なイメージとして「味のある大きなオヤジの背中」を想像する人は多いが、そうしたオヤジは「必要以上のことを語らない存在」として、映画やドラマなどの場では描かれることが多い。そこに見えるキーワードは、「粋」と「野暮」である。
「粋」とは、「趣」の機微を直感的に感じる力があることを表す言葉である。「趣」に対する直感が限りなく消えた現代社会で「粋」な人は非常に少ない。
一方で、「野暮」とは、逆に、「趣」の機微を直感的に感じる力が無く、また、「趣」が無いさまそのものを表す言葉である。
日本 で「父性」のある人を「粋」な様子で描くことが多いのは、そこに強い相互作用性があるからだ。
多くを語り、「安心安全」を追求して提供するのは「母性」の仕事である。 日本 の映画やドラマではそうした「口うるさいおせっかいな母ちゃん」が描かれることも多い。
一方で、一言で「超越」や「許し」や「大丈夫」を伝えられてしまう人には「父性」を感じさせようとする演出はやはり未だに一般的である。
「趣」や「侘び寂び」といった美意識的感覚が極限まで薄れ、重要視されなくなった現代では、自分の言葉や行動を「粋」か「野暮」かという基準で選んだり省みたりできる人もほとんどいなくなった。これは、平面スクリーンに奥行きのある「調和」を映すことが非常に難しいことに起因する。技術次第で如何様にでもできる認識スクリーンに囲われた人が、「趣」や「侘び寂び」を「理解する」のではなく「分かる」( 直覚 する)ことは不可能に近い。
しかし、例外的に 透過度 が高い人は、「趣」や「侘び寂び」を顕著に意識する傾向がある。だがそれはあくまでもオナニズム的な感覚に過ぎず、その外側に出ることは難しいのだ。
「花は盛りに、月はくまなきをのみ、見るものかは。」
-『徒然草』吉田兼好
-日本的父性への憧憬
「 人間 」にとってではなく、 いのち にとって「大丈夫」な環境とは一体何なのだろうか。
生命 にとっての「大丈夫」は「安心安全」の保障にあるのかもしれないが、「 いきもの 」にとっての「大丈夫」はどこにあるのだろうか。
いのち の 悦び とは、感情や感覚が満たされて、 「幸福」 な状態や瞬間を味わうことなのだろうか。全く違う自然環境や歴史から生み出されてきた概念や仕組みに執着することが、本当に私たち 日本 人にとって大切なことなのだろうか。
いのち の 悦び とは、遥か彼方に無限に広がってゆくものではないのだろうか。
私たちは、 いのち に根差した「許し」を、向き合う人に持てているだろうか。
何らかの認識に支配されて、誰かを殺してしまったりしていないだろうか。
そうしたものを放り出さない 意志 を持って、誰かに「超越」をもたらせるように今、生きているだろうか。
どんなに無念な出来事があっても、 いのち の底から「生ききった」と言えるような、そんな日々を過ごせているだろうか。
ここまで、日本的父性にまつわる様々なものを描いてきた。ここまでに描かれているありとあらゆるものが、「日本的父性」を醸成するものであり、その構成要素ともなり得るものである。
そこからも分かる通り、「日本的父性」とは「持つ」ことで「表す( 発揮 する)」ものではなく、畏敬の念や憧憬を秘めることで「現れる( 発露 する)」ものである。それ故に、「定義して、理解して、表現してもらう」ための取扱説明書のような文章を書くことはできない。「日本的父性」が生まれた歴史や、背景にある「 風景 」を描いて、それを共有することが精一杯なのである。
近代以前の人々は全員この「日本的父性」を 発揮 して生きていたかと言えばそうではないだろう。「日本的父性」とは、こうした 風景 の現場を何度も何度も反芻することで、自ずから(おのずから)醸成され、数奇な環境要因や 意志 が重なり、奇跡的に 発露 するものでしかないのだ。
「日本的父性」とは、「超越」と「許し」と「大丈夫」の全てが、どれも欠けることなく一体となってあることによって育まれるものだ。このどれか一つでも欠けていれば、それは「父性」ではあるものの「日本的父性」とは言い難い。
そしてそれらが 日本 の長い歴史で培われてきた「生の原動力」や いのち の 悦び に根ざしているということが最も重要である。
その点から考えると、現代の 日本 でこの「日本的父性」というものはもう存在しないと言っても過言ではない。「日本的父性」への 直覚 的憧憬も存在しないし、そうしたものが育まれる環境も消えていく一方である。そもそも 風景 に触れるための前提である、認識世界からの飄逸さえ多くの人にとって難しい状況の中で、「日本的父性」の回復を望むのは極めて非現実的なのである。
本稿では、この国では長い長い時をかけて、独自の 「生の原動力」 が生み出され、受け継がれてきたのだと仮定している。それはこの国の大地やお天道様と共に生きてきた歴史そのものであるとも言える。
認識は 悦び 、嗜むものであって、支配されるものではない。
感覚や感情が満たされるために生きるのではなく、ただ生きて、そして死ぬのである。
そこには自ずから(おのずから)遥かなる いのち の 悦び が広がっていて、 氣 はこの世界の隅々にまで吹き巡っていた。
「社会」を創り、人々を統制しなくても、儒学や漢学、仏教、神道などなどによる道徳心の醸成や「恥」への 直覚 、「生」も「死」も飛び越えた「 意志 」への敬慕が平生から人々の心に宿っていたがために、人々は「安心」「安全」よりももっとその先の「大丈夫」を胸に持って生活できていたのではないだろうか。
そうした環境が「日本的父性」を醸成し、その存在は 日本 人が「 いきもの 」として 「ゆたか」 であれる環境を守る最も重要な、ふわっとした風のような「奇跡」だったのではないだろうか。
しかし、私たち 日本 人はここ百数十年の間に、いつの間にか分厚い認識スクリーンに囲まれるようになり、本来の「 生の悦び 」、「 いのち の 悦び 」、「 いきもの 」としての 「ゆたかさ」 を感じられなくなったのではないだろうか。
それは「 いきもの 」としての「大丈夫」を奪い取り、「安心」「安全」を求める心を生み出した。
人々は認識の 向上 に取り憑かれ、そこから生まれる感覚や感情の 「豊かさ」 に アヘン のようにハマっている。
「社会」はそうしたベクトルでより 「豊か」 な人々をもてはやし、再生産する仕組みを作っている。
そこでは異常な程の「母性」が育まれ、それは いのち の可能性を奪い取り、苦しみの連鎖の動力源となっている。
この「日本的父性」への 直覚 が消えたことで加速させた「安心」「安全」への執着が強い母性社会や、 日本 に漂う「息苦しさ」、たくさんの人が原因不明の鬱や無 氣 力感に支配されていること、認識技術を 向上 させる一方向的なベクトルから逃れられなくなった人が無自覚に いのち の可能性を奪い、奪われ、その究極のやるせなさから誰かを殺害したり、自らの 生命 を終わらせる行為に走ること。そんなやるせなさに向き合わないように、更に認識技術を 向上 させて、深い 沼 へと入って行くこと。私たちは、認識的に思考したり、理解したり、語られたりするネガティブな言説の数々よりも、もっと遥かに根底のところで、恐ろしい状態に浸かってしまっているのではないだろうか。
いのち の 悦び は、外の世界に染み出し広がっていく。「 氣 」は巡り、 いのち は輝く。この国に、今、そんな気体性の「 悦び 」は皆無に等しいのではないだろうか。
個々人がそれぞれの認識世界でのみ「 喜び 」を享受するということが、この国においては不健康極まりない状態なのかもしれないと、疑ったことがあるだろうか。疑わせてくれる環境で暮らしているだろうか。
だが、このようなことを疑わせてくれる 風景 のカケラたちは、この世界の隅々に未だに点在している。
日本 では未だに自然災害は起こり続けているし、山も海も川も、風も空も大地も変わらずにそこにある。 生命 を懸けて何かを成し遂げようとする 意志 ある者もいるはずだし、趣を 直覚 するおばあちゃんや職人もたくさんいる。「主観」という概念さえ持ち得ないほどの広さで誰かを包み込んでいく者もいるはずだし、『ONE PIECE』のように「父性」的な美を描く作品は無くならない。
掻き消されていったものや、覆い尽くされて見えなくなったものはたくさんあるけれど、 風景 のカケラたちは未だにその多くが単体として影響を与え合いながらこの世界の片隅で生まれては消えてを繰り返している。私たちはそうした大地の上で暮らしている。
これからの時代で、こうしたものたちは更に消えていく可能性が高いということは次の章で解説するが、だからこそ、今、ここでそうした点として散らばって消えていきそうな 風景 たちを、まとめてからこそ生まれる「日本的父性」をここに描いておきたかったのだ。
そんな「日本的父性」が、 日本 人を認識に支配されないように守ってきたものであり、 日本 独自の生きる 悦び や死ぬ 悦び を生み出してきたものだったのではないだろうか。
この風通しの悪すぎる「 地獄 」のような 日本 に、最後の希望として、今「日本的父性」という「奇跡」の姿を、ここに小さく遺し、まずはここまでを読み、何か重要なものに出会った気になってくれる人がいることを祈るばかりである。
終わらない歌を歌おう クソッタレの世界のため 終わらない歌を歌おう 全てのクズ共のために
終わらない歌を歌おう 僕や君や彼等のため 終わらない歌を歌おう 明日には笑えるように
-THE BLUE HEARTS(真島昌利)『終わらない歌』
(第四章へつづく)