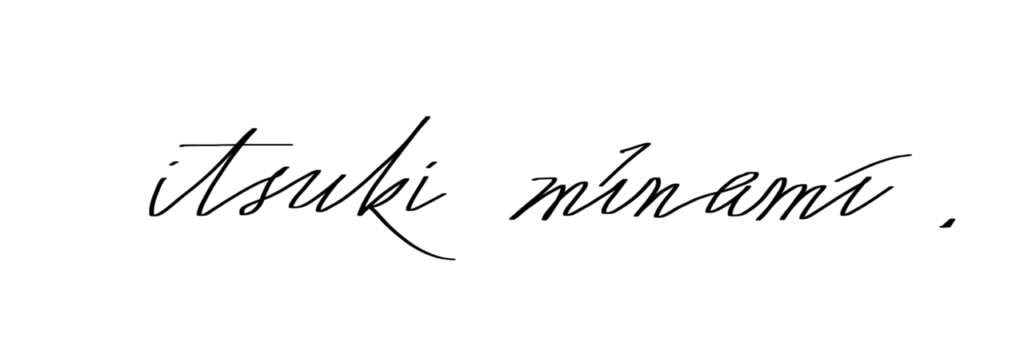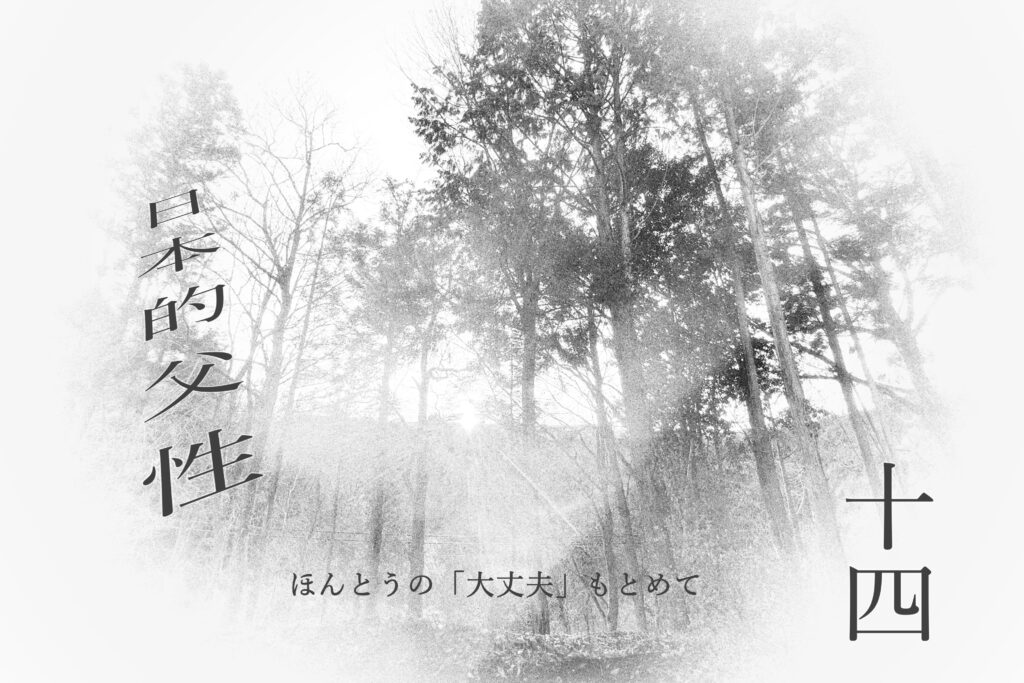
14.第三章「大地性と日本的父性」
『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –
目次
-脱主観とあわい
「主観(Subjektivität)」という概念もまた、近代の黎明期に形成された理論体系の一部である。
哲学者イマヌエル・カントなどが「主体(Subjekt)」として生きる「個人(Individuum)」の認識と経験のプロセスの中心にある「自我(Ich/das Selbst)」が生み出す認識の枠組みを「主観」という言葉で表現した。この考え方は、 西洋 的な 「生の原動力」 を前提にしており、「自我」が「主観」的な経験としての世界をどのように構築し、解釈するかを探求する近代的な認識論の枠組みを提供することに繋がった。
「主観」という言葉は、「主」から「観る」と書く。これは、自分の心や思考など、自分の内部からの視点で物事を見ることを表している。したがって、「主観的に物事を捉える」とは、自身の心理的、情緒的、感覚的な経験を通じて物事を解釈するという意味合いになる。
一方、「客観」という言葉は、「客」から「観る」と書く。これは、自分以外の視点、つまり個人の主観的な視点を超えて物事を見ることを表している。したがって、「客観的に物事を捉える」とは、自身の主観的な解釈や経験を排除し、一般的、普遍的な視点から物事を理解することを指す。
主観と客観の間の違いを考えてみると、主観的な視点で物事を捉えると、自身の心理や感情、思考などに大きく影響を与える。例えば、感情が強く刺激されたり、視覚的な印象や思考のパターンが変化する可能性がある。このような理由から、「主観的に物事を捉える」ことを「感情的に物事を捉える」と表現する人もいる。一方、客観的な視点では、自身の感情と距離を保ちつつ冷静に物事を比較・分析することが可能となる。「自分と物事の間に距離を置くことで、主観的な影響から自由になり、より公平な評価が可能となる」という意味合いで使われることが多い言葉だ。
しかし、これらはいずれも、認識スクリーンに世界をどのように映すかという話に過ぎない。非常に分かりすいイメージは、近年のゲームに多く利用されている一人称視点と三人称視点を自由に変えられる機能だろう( 「図1:西洋的認識世界」 )。この世界のある 風景 を一人称視点で捉えて認識スクリーンに映すと「主観的」、三人称視点で映すと「客観的」と表現することができる。これが 西洋 的な認識を前提に置いた概念である証でもある。
つまり、「客観的」になることはあくまでも「主観」概念の内側にいることでしかなく、ほんとうの「脱主観」を目指すのならこうした理論体系全体から抜け出してみる必要がある。それは、認識世界から抜け出すということでもある。
認識世界なき 「全」 なる世界では「主観」という概念は存在しない( 「図8:日本的認識観」 )。全ての物事が 物化 する存在であり、あらゆる物事に直接触れられるので、圧巻の感覚と感動に溢れられる世界線だ。貴方は私であり、私は貴方、それはこれだし、これはそれ。貴方は宇宙だし、私は宇宙、これは宇宙だし、それも宇宙。全てが無であり、全てが永遠の一部である。 そんな感覚が広がっている。
こうした「脱主観」では、「みずから」と「おのずから」がよもや一体となっている。
日本 では古来から「自」という字に二つの意味合いを持たしてきた。一見反対の意味合いにも感じるような「みずから」と「おのずから」の存在は前述したほんとうの「脱主観」が 日本 古来の自然観に寄り添っている証とも受け取れる。
そして、前述した「 意志 」の 風景 も「みずから」と「おのずから」の話と同じような話であった。本稿でよく使われる「醸成」や「育まれる」という言葉は、こうした 風景 を見過ごさないために用いているものである。「 意志 」もまた「おのずから」育まれたものを「みずから」大切にしていこうとする姿である。
この世界のあらゆるものたちが「おのずから」と「みずから」が相互に溶け合い、混ざり合う中で「おのずから」醸成されていくものたちである。
この矛盾とも取れる言葉で着目すべき点は、「おのずから」と「みずから」とが、根源的には「相即」するというところにある。それは、一元論でもなければ二元論でもない。大事なのは、まさにその一と二の「 あわい 」にある [31] 。
吉野源三郎の著書『君たちはどう生きるか』に登場するコペルくんは、デパートの屋上から地上を眺めてこう言った。
「ここから見ていると、雨粒くらい人が小さく見えるね。分子みたいにちっぽけだ。ほんとうに 人間 って分子なのかも。だってさ、目をこらしても見えないような遠くにいる人たちだって、世の中という大きな流れをつくってる一部なんだ。もちろん近くにいる人たちも。おじさんも。僕も。」 [32]
分子は自由に飛び回る。ここでは 人間 中心の文脈で語られているが、ヒトはこの世界のほんの一部に過ぎない。そう考えると、 人間 が織りなす世界をここで言う「世の中」とでも言うのなら、それは世界のほんの僅かな欠片でしかない。世界のあらゆる影響があって、ご縁が生まれ、「おのずから」何かが生まれるという考え方は前述した日本的自然観に依拠している。
先ほど少し見たように 日本 語が主語を持たなくても意味が通じる言語として発達したのも、このような流れの一部と考えることができる。全てのものが影響し合い、「みずから」と「おのずから」の あわい の中で生まれているのだと 直覚 する人々が、そうしたものを認識的に変換することに拒否感を感じ、それをそのまんまに表現する美的感覚の限界(こだわり)として、こうした言語の特徴が生まれたのではないだろうか。
こうした「みずから」と「おのずから」の あわい は、近代に持ち込まれた「主観」のある 西洋 的な感覚と溶け合えず、昭和の体育会系思想や、近代的な自己責任論が、「ギギギギギ」とものすごい異音を立てながら時折現代の「社会」で火花を散らしている。 日本 人が元来の自然観に立ち返り、ほんとうの「脱主観」をすることができれば、そうした火花は火事になることなく消えていくのかもしれない
爲學日益、爲道日損。損之又損、以至於無爲。無爲而無不爲。取天下常以無事。及其有事、不足以取天下。
-老子 第四十八章
-物化する嗜み
では、認識スクリーンに囲われることもなく、現代的な意味合いでの「信じる」ことも無く生きてきた 日本 人はじゃあどうやってこの世界を認識して味わっていたんだ!という疑問が湧いてきはしないだろうか。その疑問に回答するための重要な概念を一つ描いておこうと思う。
元来 日本 人の認識レイアウトはとても多様であったと考えられる。球体で囲われているパターンも勿論多少なりとも(あるいは皆一時的に)存在していたであろうが、どちらかと言えば前述したように、「いくつもの小さな認識スクリーンを世界の無数の輝きの一つとして、この世界の片隅に据えて嗜んでいた」というパターンが多かったのではないだろうか。( 「図8:日本的認識観」 )。
ここで使われているように、「嗜み」という言葉が、最もしっくり来るのは、「それに囲われない(支配されない)」という感覚を表現するのに適しているからであろう。「嗜む」という言葉は本来、「好む」や「親しむ」といった意味合いに加え、「つつしんで接する」という 日本 的な奥ゆかしさも含んでいる。
例えば「お酒を嗜む」といった表現で使われる場合「お酒を好んではいるが、それに支配されたり、振り回されたりはしない」という意味合いを持つ。こうした言葉が生まれる背景としては、やはり日本的自然観があったのではないかと考えられる。また、 日本 で古くから受け継がれてきた(嗜まれてきた)仏教などは、 こうして作り上げられた「お酒への身体的な認識」のような、認識スクリーンの数々を輝化させることに重きを置いていたのではないかと捉えることができる。
だが、「嗜む」という言葉を聞いて何か物足りなさを感じるのは現代人の性ではないだろうか。認識を通して感情を生み出すことに慣れた現代 日本 人にとって、「嗜む」という感覚の 「ゆたかさ」 が永遠を孕む途方もないものだと 直覚 することは、ほぼ不可能である。もっと分かりやすく、単体と単体で感情に繋がっているものの方が、 人間 の 豊か なホルモン放出には最適だと考えるのは特にデジタルネイティブな世代からしたら当たり前のことである。
一方で 風景 を圧縮変換することなくそのまま味わう 「ゆたかさ」 に 文学的理解 を持ち、「複雑なものを複雑なままに」と声を上げている人は、現代においても探せば一定数いるが、認識世界を生きる現代人からしたらどう頑張っても「複雑なものを複雑なままに」感動するにはエネルギーをかなり消費してしまうため、どうにも無理くり感が出てしまうのが現状である。
それと同様に、「嗜む」という言葉もやはりニッチな一部の知性のある人々の「複雑なものを複雑なままに味わうことが大切だ」というある種の正義感や美意識に紐づけられてしまっている。
しかし、もし元来の「嗜む」に内在する 「ゆたかさ」 が、究極まで突き詰めても「遥か永遠に認識できないもの」を孕んでいるなら、それを「 物化 する嗜み」と呼ぶことにしようではないか。
日本 人がもともと「いくつもの小さな認識スクリーンを世界の無数の輝きの一つとして、この世界の片隅に据えて嗜んでいた」ということをもう少し具体的なイメージで示すとすれば、小さな認識スクリーンを通して「知る」「理解する」この世界の事象も、 「全」 なるものに 物化 させることができるため、それは即ち無限に広がる感動を湧出させる可能性を持つということでもあり、さすれば認識スクリーンから得られた信号情報や分泌も、 いのち レベルでの 「全」 からの直感に従って 無自覚コントロール されるということにもなる。つまり、認識を「嗜む」ことが可能になっているのである。「全てを味わっている」かつ「生まれるものも無自覚にコントロールされる」という両輪を同時に走らせるというとんでもない所業が可能であることを、本稿では「嗜む」と呼ぶことにしよう。
簡単に言えば、「嗜む」とは、どこまでも夢中になれても支配されることなく、どこまでも感動が生まれても支配されることなく、今よりも遥かに 豊か な感動さえ簡単に生まれるようなもので、それでいて いきもの として 「ゆたか」 であるというイメージだ。
ちなみにそんな中でも、何らかの認識スクリーンに「夢中になる」ことは平生からあったであろうし、一般常識は多くの人に同じような認識スクリーンを作り出していたであろうし、認識スクリーンに囲われて生きている人もいたかもしれない。だが、そのレイアウトはとても変動しやすく、 日本 の大いなる自然環境はそれを「許す」存在そのものだったのではないだろうか。
天地与我並生 而万物与我為一
-『荘子』「斉物論第二」 荘子
-恥を知る
「日本的父性」がまだ人々の心にあった頃、親が子を叱るときの文句が今とは少し違っていた可能性について考えてみたい。
つい昭和の頃までよく聞かれていたのが、
「恥を知れ!」
「恥を知りなさい!」
という叱りの言葉であった。しかし、近年は子どもを叱るときに、
「こら!恥ずかしいでしょ!」
「恥ずかしいことをしないの!」
と言う母親が増えたとともに、子を叱る時に「恥」という言葉を使わない父親が増えたと言われている。これは、「恥」という言葉の背景にある 風景 が変化したためだと考えられる。
吉田松陰の『講孟余話』に、こんな一節がある。
「恥は吾が心にあることにて、尊位をし富禄を糜して、道を行ふこと能はずんば、何の面目かあらん。類を充て義の尽くるに至れば、即ち盗と云ふべし。且、罪と云ふものは、外に顕るる如しと云へども、其の一身に止る。恥と云ふに至りては、心に在りと云へども、其の害、君民に及ぶ。然れば、罪恥の軽重、云はずして知るべし。」 [33]
ここで吉田松陰は、「罪」と「恥」のどちらが重いかという質問に、「恥」であると答えている。「恥」とは、自分自身の心にあるもののことで、それは外に影響を及ぼすものだという考えだ。
「恥」という漢字は「耳」に「心」と書くわけだが、この頃の「恥」という言葉は、自分自身の「心」に「耳」を澄ますという意味合いで使われることが多かったのではないかと考えられる。
一方で、近年の「恥」という言葉は、「周りから見られて恥ずかしい」というような、誰かや一般の「心」や「声」に「耳」を傾ける時に使われることが大半である。このような変化は、母性的な「 共感 ・ 同情 」「没入(同化)」の顕現そのものであると言えるのではないだろうか。この「恥」という言葉の使われ方の変化にも、「日本的父性」の喪失と「母性」の支配が現れているのかもしれない。
ここで吉田松陰は、「道」を外れた行いをした時に自分自身の心に耳を傾けると、聞こえてくるものがあるだろ、それが「恥」なんだと、そう言っている。
では「道(ドウ・タオ・みち)」とは一体何だろうか。
それは丁度この頃まで長らく 日本 の教育の柱となってきたものの源流にある 風景 であり、老子、荘子、孔子、孟子などなど様々な中国の思想家や、その弟子、またそれを学んだ人々によって継承されてきた感覚でもある。だが、近代化以降、 日本 人はこの「道」への関心をみるみるうちに失っていき、近年では「思想」として圧縮変換された知識の一つとして覚える人がほんの一部いるだけで、多くの人が知りもしないという状況になっている。
無論この「道」とは、「遥か永遠に認識できないもの」を前提とした表現であるが故に、現代の認識世界を生きる人々には伝わりきらない感覚である。
古くから 日本 では言わずもがな社会的な「罪」を犯すことよりも、この「恥」の方が重たいものであり、そうした「道」を 生命 懸けて体現していくのが「侍」であったとも言えるのだろう。「道」に限らず、何かを大切にして生きる「生き様」に根ざしていた時代では、他人に笑われても「恥ずかしい」のではなく、「悔しい」といった気持ちを感じていたはずなのである。
だが、現代の人々の考え方は真逆であり、「罪」は「悪いもの」と自動化され、「恥」はあまりにも薄っぺらい表面上の話に形骸化した。
吉田松陰的に言えば「恥」ずかしくて仕方のない損得勘定や言葉の自動機械となった人々が、 「豊か」 な人だと言われる現代の世の中で、 「幸福」 という一元的な認識指標の外側で「道」や自分自身の いのち の声に耳を澄まし続けて生きられる人などまず見つからない。
また、現代人が溺れがちな自己啓発の「名言」のような言語 アヘン は、「道」を源流とする歴史書で描かれていた 風景 を現代の個別事象に適用できるように圧縮変換したものに過ぎず、人々に新しい発見をしたかのような感覚を与え、快楽 沼 を提供し続けている。
そんな世の中では「恥を知れ」と言える父親がいなくなって当たり前だし、その言葉を聞いて、自分自身の心に必死で耳を傾けようとする子どもなど、もうどこを探してもいないのも当然であろう。
その流れと共に長い時代を経て「恥」を醸成してきた様々な教育的観念も、同じように忘れ去られていっている。例えば儒教から派生する仁・義・礼・智・信などの「徳」も、孝・悌・忠などの観念も、人々は認識的理解以外で気にすることもなくなり、時代に置き去りにされている。
そもそも「恥を知る」ということは、「遥か永遠に認識できないもの」も含めたものに手を伸ばし、 直覚 しようとすることであり、こうした「恥」を認識スクリーンに映し出すことは不可能に近いのだ。認識世界の住人はそんな認識変換しにくいものを感じろとか、耳を傾けろとか言われても困ってしまうのだ。しかし、本来、「恥」のない生き方をすることは、自分に 生命 を与えてくれた親への孝行であり、親が子に示せる最大限の姿だったのではないだろうか。
現代人が「日本的父性」を取り戻すためには、吉田松陰が表現している感覚が非常に重要であり、そのためには、「遥か永遠に認識できないもの」への 直覚 が溢れる環境を取り戻す必要がある。
子曰 好学近乎知 力行近乎仁 知耻近乎勇 知斯三者 则知所以修身
-『中庸』第20章 子思
-山河の背中
吉田松陰と同じ時期に活躍した人物で、「父性」について語るときに外せないのが西郷隆盛である。
日本 の歴史の中でも、西郷隆盛ほど「父性」を宿した人として描かれる人物は他にいないかもしれない。西郷隆盛については写真も残っていないし、西郷自身が遺した書物などもないため、その人物像を正確に把握することが難しく、後世様々な西郷隆盛像が作られてきた。本稿で描く西郷像は、実際の西郷隆盛とは異なるかもしれないが、たとえ妄想だとしても、「父性」の象徴として語られてきた歴史そのものとして描いておきたい。
貧しい下級武士の家に生まれ、百姓のような暮らしをしていた西郷が、激動の維新期に何をし、どう生きたのかは、史実に刻まれた彼の数少ない痕跡を辿るだけでも、多くのことが見えてくるのである。列強の圧力がかかる中で、長く続いた仕組みの転換を目指し、少しずつ少しずつ糸口を見出していった維新期の「侍」たちの物語は、今、私たちが生きているこの時代にも、確実に繋がっているはずだ。
西郷隆盛は、1828年に薩摩藩の下級武士の家に生まれた。彼の家は貧しく、借金も多く抱えており、西郷は家計を支えるために多くの時間を労働に費やしていた。彼は薩摩藩主・斉彬のもとで、開国と近代化の必要性を学んだ。斉彬は西郷に、 日本 が列強の間で独立と尊厳を保つためには、自国の力を強化し、近代的な技術と知識を取り入れることが不可欠であるとの考えを伝えたとされている。
斉彬の急死後、西郷は一時的に奄美大島に流されるが、この期間中に僧・月照との出会いがあり、彼とともに入水自殺を図ったが失敗し、西郷だけが生き残ってしまった。その後西郷は「一度死んだ者なので」というような表現を時折使っていたことが文献からも分かっている。この事件の後、彼は「敬天愛人」という信念を持つようになり、厳しい流刑生活での人々との関わりの中で、この信念を深めていったとされている。
明治維新の過程で、西郷は大久保利通や岩倉具視らと緊密に協力し、新しい 日本 の礎を築くための重要な役割を果たした。だが、西郷は征韓論に端を発する政府内の対立で政府を下野する。その後鹿児島に戻った西郷は若手の育成に携わり、最終的には西南戦争で命を落とすこととなった。
ここまでが、彼の生涯の概略である。この短い略歴にも諸説ある部分が多く、実際の詳細は不明である。だが、現在主流となっているこうした概略の中から「父性」に関わる箇所を更に詳しく、できる限り史実に基づいて妄想してみたい。
西郷は、 戊辰戦争 で 先頭に立って 新政府の樹立に不満を持つ各地の志士たちを薙ぎ倒した。「敬天愛人」の精神を持つ西郷が、多くの 生命 を奪うこの戦争を指揮することに何を感じていたのか、想像は難しい。現在の 日本 には、西郷を顕彰し祀る南洲神社が全国に四ヶ所あるのだが、そのひとつは庄内地方にある。 戊辰戦争 で、最後の最後まで城を枕に討死の覚悟で戦った庄内藩だったが、西郷は決着がついた状況からの殺戮を命じずに相手の尊厳を尊重したとされている。そこに西郷の「父性」的な何かを感じた庄内藩の藩士たちは、後に西郷を何度も尋ねて「遺訓」を編纂するに至る。
また、西郷は、維新期に行き場と志を失った侍たちが、次の時代でどのような役割を担えるかを深く考えたのではないだろうか。西郷は明治初年から行き場を失った侍たちを招聘して捕亡方や邏卒などの治安維持隊を作っている。明治四年には御親兵(後の近衛兵)を招聘して、天皇を守るという役目を与えた。後に現在の警視庁を創設した川路利良にその創設を促したのも西郷隆盛である。
大久保らが欧州視察に行く間、西郷は留守政府を任される。ただ、外遊中に留守政府が勝手に改革しては困ると、外遊組は自分たちが帰国するまでは決められた事だけを実施し、急激な改革はしないようにという盟約書を留守政府に書かせていた。ただ、同時に廃藩置県の後始末については迅速におこなう事も同時に取り決められていた。しかし、外遊組の帰りの遅さと、人々の不満の高まりを感じて痺れを切らした西郷ら留守政府組は、大急ぎで凄まじい改革を推進していく。明治五年二月には兵部省が解体され、陸軍省と海軍省が設置される。同年五月には田畑の永代売買が認められ、翌年の地租改正の下準備となった。八月には学制が公布され、義務教育の仕組みが始まった。九月には琉球王国が琉球藩として 日本 に組み込まれ、横浜~新橋間の鉄道が開業し、横浜にはガス灯が灯った。十月には人身売買の禁止と富岡製紙工場の開業があった。十一月には徴兵告諭と国立銀行条例が施行された。十二月には太陽暦が採用され、太陰暦が廃止された。明治六年一月には六鎮台が全国に設置され、徴兵令が出された。七月には地租改正の条例が公布され、物納から金納の納税システムが始まったのである。このように、留守政府は驚くべき速さで現代にも続く重要な改革を進めていった。
しかし、視察から帰ってきた大久保や岩倉らは、この留守政府の「身勝手」に不満を持つ。そんな時、政府は朝鮮に対して新政府発足の通告と国交を望む交渉を行っていたのだが、 日本 の外交文書が江戸時代の形式と異なることを理由に朝鮮側に拒否されてしまう。それをキッカケに、朝鮮にどのように対応していくかを巡って政府内では亀裂が生まれる。あくまで交渉の可能性を探りたかった西郷は、自身の 生命 を懸けてでも朝鮮に自ら赴いて話し合うことを強く訴えた。しかし、留守政府の「身勝手」に不満を持っていた大久保らは、その機につけてたくさんの留守政府の功労者を政府から追い出してしまう。西郷も、そこでお役御免と悟ったのか、早々と薩摩に戻っていく。薩摩に戻ってから百姓の仕事やのんびりとした生活に戻った西郷は、薩摩の若者を育てる様々な施策をしたと言われている。
一方、西郷と同じ頃に下野した者たちが、 日本 各地で新政府に対して発起し始める。新政府に対して溜まっていた元士族たちの不満が爆発し、各地で戦争が起こった。薩摩隼人の志士たちも、発起を西郷に何度も促したという。幼馴染でもあり一緒に維新を駆け抜けた大久保に 政府を追い出された 西郷が、どのような想いで政府を去ったのか、また、大久保に対して牙を剥く各地の志士に対してどのように感じていたのかは、想像してもしきれない。
そして最終的に、西郷隆盛は、まるで全ての侍たちの思いを集めるかのように、盛大に立ち上がったのだ。そして、それを討伐したのは大久保の指示で動く川路利良率いる警視隊の抜刀隊であった。この西南戦争は、 日本 国内の最後の大きな内戦とも言われ、西郷らは最後の最後まで山々を駆け巡って戦い抜いたと言われている。まるで、「侍」の死に場を、最後に自分の 生命 を懸けて作ったかのようにも受け取れてしまう。
その後、明治政府はものすごい速さで近代化を進め、 日本 は独立を守るに至ったのだ。その後これほどの内戦は 日本 では一度も起きていない。 日本 において「侍」の果たした役割はあまりにも大きかった。だが、国を守るために、突然その「侍」たちは必要なくなり、西郷隆盛という人物が、彼らが輝いて大地に還る場を作り、死んでいったのだ。
島津斉彬、松平春嶽、藤田東湖、徳川慶喜、勝海舟、坂本龍馬、中岡慎太郎、大久保利通、木戸孝允、福沢諭吉、板垣退助、伊藤博文、大隈重信、渋沢栄一、などなど、その他にも様々な西郷と関わったことのある人物が、西郷の「父性」についての言及を残している。西郷は多くを語らない人物だったが、彼の周囲の人々は彼についてたくさん記しているのだ。
勝海舟は西郷の死を耳にしてこんな句を詠んだという。
「ぬれぎぬを 干そうともせず 子供らが なすがままに 果てし君かな」
西郷と共に江戸城無血開城という偉業をやってのけた勝海舟は、西郷の最後をそんな風に語ったのだ。
時代が大きく変わる時、戦争が終わる時、そこには誰かの「父性」が必要である。下級武士として百姓的な生活を営んでいた西郷は、いつだって大地と共にあった。苦しみの連鎖を終わらせるのは、「父性」そのものである。「侍」という「日本的父性」を 生命 懸けて体現した者たちがいたからこそ、
「なるほど西郷というやつは、わからぬやつだ。少しく叩けば少しく響き、大きく叩けば大きく響く。もし馬鹿なら大きな馬鹿で、利口なら大きな利口だろう」(坂本龍馬)
と言われるような西郷が、このような生涯を歩むに至ったのではないか。そして彼は、そうした「父性」の体現者たちが「生ききる」場を作り、自らも生ききったのだ。
彼が「超越」「許し」「大丈夫」、つまり「日本的父性」の体現者の象徴として描かれる所以はこうした彼の生涯のほんの一部を切り取るだけでもよく分かるのである。
「父性」から連想される「大きな背中」は、まさにここにある。あまりにも多くの「死」を全て抱えて、どれほどの傷を抱え、どれほどの「生」を背負って生きたのだろう。その「大きな背中」は、一体どれほどの「大丈夫」であったのだろうか。
晴れの日もあれば雨の日もあるし、穏やかな日もあれば暴れる日もある。だけどそのどれも大地は見て見ぬフリはしない。無かったことにもしないし、決めつけることもない。全てがあってこそ生きていく。
西郷の故郷、薩摩には、とても大きな背中の桜島や八重山などの山があり、甲突川沿いで彼らは育った。西郷のその大きな背中は、こうした大地を生きる中で育んだ、雄大な山河そのものだったのではないだろうか。
現在の 日本 が、維新期レベルの過渡期だと発言する人が、現代社会には溢れている。その中に「生」や「死」を遥かに飛び越えた風のような「日本的父性」を体現できる人なんてどこかにいるのだろうか。一人でもいるのだろうか。
そんなものなくても認識レベルではたくさんの「変化」を生むことは可能だろうが、それは思いのほか「優しいディストピア」を作り出すだけなのかもしれない。
根本的な変化を求めるのなら、まずは「日本的父性」に触れられる環境づくりから始める必要があるのではないだろうか。山河大地にしっかりと根差した環境でもう一度走り回らなきゃならないんじゃないだろうか。
或曰、以德報怨、何如、子曰、何以報德、以直報怨、以德報德
-『論語』憲問第十四36
(つづく)