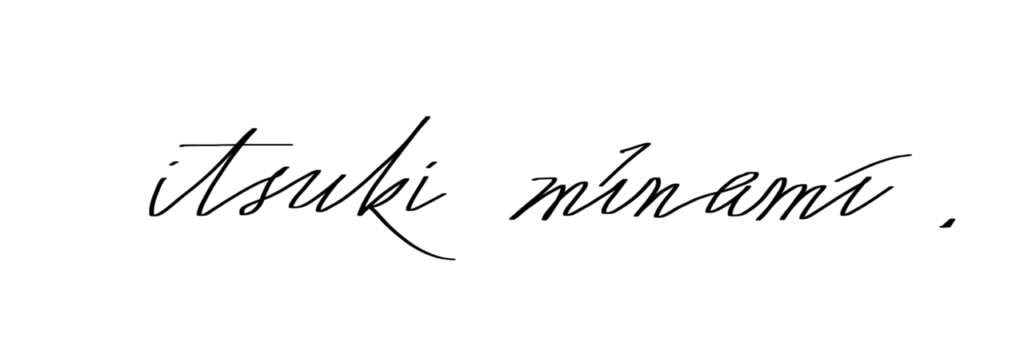13.第三章「大地性と日本的父性」
『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –
目次
-生と死のその先に
「日本的父性」における「超越」は限界性を持たない。
ということは、「 生 」や「死」そのものさえも「超越」してしまうほどの「日本的父性」には一体何が眠っているのだろうか。
まずは本稿における「 生 」と「死」の定義を整理しておこうと思う。これは議論の絶えない話題なので、あくまで本稿としての定義であるということをご理解いただきたい。
本稿における「 生 」と「死」は、その「一回性」に着目する。 いのち を宿す 生命 の多くが、現在のところ「一回性」を持っている。 いのち を宿す 生命 の中で、生き返る可能性を持たず、成長、代謝、適応、反応、再生産をしなくなった状態のものを「死」んだものとし、そうなる前のものを「生」きているものと呼びたいと思う。つまり、「死」とは、 いのち を宿す 生命 が成長、代謝、適応、反応、再生産を完全に停止した状態への移行を指し、「 生 」とは、それらの特性を持つ状態を指す。
「 生 」と「死」はそのほとんどが 「大地」 に 在る 。固体の密度は、液体やガスに比べると遥かに高いことが多い。地球の大部分は固体で構成され、物質の大半は 「大地」 に存在する。また、 生命 に必要な分子(水、DNA、タンパク質など)は主に水や土壌中に存在する。微生物をとっても、大気中の微生物の総量は、地表面(特に土壌や海洋)に存在する微生物の総量に比べて遥かに少ないと考えられている。大気は栄養素が少なく、乾燥していて、紫外線にさらされているため、多くの微生物にとっては生存が難しい環境となっているのだ。このように、「生」や「死」は分子レベルで考えると、その大半が 「大地」 にあると考えることができる。
更に、この 「大地」 の中でも特に 「土」 は注目すべき集合体である。土は 生命 の源であり、植物の成長に必要な栄養素を提供する。これらの栄養素は、植物が成長し、生きるために必要な分子を生み出すために使用される。また、土は微生物の豊富な生息地であり、これらの微生物は 生命 の「生」と「死」のサイクルに重要な役割を果たす。バクテリアや真菌は、死んだ植物や動物の残骸を分解し、新たな 生命 を生み出す分子を生成する。そして、 「土」 は生物の「死」と再生の場でもある。動物が死ぬと、その身体は分解され、その成分は土に戻る。これらの成分は再び植物の成長に利用され、新たな 生命 を生み出す。したがって、土は「死」を物質的に生み出す分子と、「生」を物質的に生み出す分子の両方をたくさん含んでいると言えるだろう。
この 「大地」 については、たくさんの歴史の片隅からその重要性を 直覚 することができる。鈴木大拙は、代表作の『日本的霊性』という本で「大地性」という章を設けてその重要性を語っている。まず彼は「霊性」という概念をこのように解説している。
「なにか二つのものを包んで、二つのものが畢竟ずるに二つでなくて一つであり、また一つであつてそのまま二つであると云ふことを見るものがなくてはならぬ。これが霊性である。……精神と物質の世界の裏(うち)に今一つの世界が開けて、前者と後者とが、互に矛盾しながら、しかも映発するやうにならねばならぬのである。」 [30]
鈴木大拙は、本稿で言う「 いのち 」や 「全」 、「世界」、それらを 直覚 する「一」など、 物化 するすべてを「霊性」と呼んでいると解釈できる。
私の場合、玉ねぎの収穫をしているときにオーディオブックで聴いていたのがこの鈴木大拙の『日本的霊性』との初めての出会いであった。丁度その時に私が衝動的に書いたメモの文章が残っている。
「○○だが、○○ではない。」という文章にパラドックス性を見出すしか術がない 人間 には分かりっこない話。
あなたとわたし。あなたとあなた。わたしとわたし。
あれとこれ。あれとあれ。これとこれ。
生と死。生と生。死と死。
天空と大地。天空と天空。大地と大地。
夢と現実。夢と夢。現実と現実。
質量と虚無。質量と質量。虚無と虚無。
意味と誠。意味と意味。誠と誠。
全と一。全と全。一と一。
まあ、つまるところ、1+1。これは、本当に2だろうか。
ヒントは「即」にあった。『 日本 的霊性』にも「即」という漢字がでてきた。僕は、「=」を「即是」に変換することをよしとしてみることにした。さすれば、まずは解の個数的理解へと至ることができた。
「1+1即是2」は表現の1つに過ぎない。「1+1即是1+1」は成り立つ。「1+1即是0+2」は成り立つ。つまり、
「1+1即是∞(むげん)」
ということは
「1即是∞(むげん)」
ということも可能だ。
「1+1即是∞+∞(むげん+むげん)」
といえてきた。そう。たいして差などない。1も2も、即ち無限であり、無である。
今、僕の目の前には、数百個の腐ったたまねぎが落ちている。これらは、皆、死んでいるのだろうか。じゃあ、食べられるたまねぎは、生きているのだろうか。土に埋まっていた時と、収穫された今と、たいして変わりはない。生と死の間に、たいした狭間は存在しないともとれる。
右手にひとつ、たまねぎを持つ。
左手にひとつ、たまねぎを持つ。
右手のたまねぎが腐っているので放り投げる。
新しく、右手にたまねぎを持つ。
捨てたたまねぎは、「1」ですか?
それとも、「0」ですか?
ここで問いたい。「1」と「0」に一体いかほどの差があろうかと。それは 人間 が決めたことか。その境界は何だ。1つのたまねぎも、無数の分子からできているし、無数の腐ったたまねぎが、分子の集まりにも見える。それは目の前に存在している。僕の目の前には、無数の腐ったたまねぎが存在している。あぁ、なんと温かなことか。僕らは、AでもBでもないし、1でも2でもない。あなたとわたしは、合わせて2ではないだろうし、世界はもっと複雑で、愛はもっと無限で、「一」はもっと量子的で、存在はもっと「無」である。この世界はもっと無でいいし、もっと無限でいいし、もっともっと散らかってていい。
「生」と「死」は、この溶け合う 「全」 (霊性)の一部であり、霊性と共にある。
鈴木大拙は大地性についてこのように述べる。
「霊性はどこでもいつでも大地を離れることを嫌ふ。」 [30]
「霊性と云ふと、如何にも観念的な影の薄い化物のやうなものに考へられるかも知れぬが、これほど大地に深く根を下して居るものはない。霊性は 生命 だからである。大地の底には底知れぬものがある。空翔けるもの、天下るものにも、不思議はある。然しそれはどうしても外からのもので、自分の 生命 の内からのものでない。大地と自分とは一つものである。大地の底は自分の存在の底である。大地は自分である。」 [30]
彼は 「大地」 に根ざしていることが、霊性を生きることに直結するという見方を示している。
だが我々はいつからか「 生 」と「死」からずいぶん遠ざかった生き方をするようになった。
ヒトのいる大地を更に「 都市 」 と「 田舎 」 の二つに分けると、 生命 の「 生 」及び「死」を物質的に生み出す分子は、生物多様性の観点から見ても一般的には「 田舎 」の方が「 都市 」よりも多いと考えられる。
「どのようにして 人間 が住みやすい場所を作るか」が最重要課題とされる「 都市 」の環境では、可能な限り土はセメントで隠され、可能な限り管理(制御)にコストのかかる自然環境の形は変えられてきた。近代科学は、より自然環境を管理(制御)していくためのたくさんの手段を生み出し、そうしたものがまたたくさんの「 生 」と「死」を 人間 の周りから隠していくために使われてきた。
高度に安心が担保されるようになった 人間 社会では、村文化的な濃い 人間 関係は地域から消え、人との物質的な触れ合いも減少した。その流れと共に、 日本 では「 都市 」にあまりにも多くのヒトが集中するようになり、 人間 がヒトやヒト以外の 生命 の「 生 」と「死」に触れる機会を急激に失った。
近年、人々のデバイスの使用開始時期が低年齢化していくのに伴って起こる変化の一つとして、子どもが 「土」 に触れて「泥んこ」になる機会が減少したと言われることがよくある。学校の校庭は 「土」 から「砂」や「ゴム」や「人工芝」になり、公園では走り回る子どもと同じ数だけデジタルスクリーンを見る子どもを見ることができるようになった。
それでも残る、「安全」性が極限まで保証された環境で触れる「 生 」と「死」の多くは、認識フィルターで変換可能な情報しか持たない事象に形骸化した。すると我々は認識スクリーンに数え切れるほどの「 生 」と「死」しか映し出さなくて済むような生き方ができるようになった。
現在のこうした状況は、到底数え切ることなど不可能なほどの 生命 の「 生 」と「死」に触れ続けて生きていた時代の状況とは明らかに違い、「 生 」に「意味」を自動的に見出し、「死」に非日常性のみを感じる 人間 をたくさん生み出すようになったと言えるのではないだろうか。
認識世界の住人にとって、認識スクリーンに変換可能な「 生 」は「認識世界を生きること」そのものであり、「死」はすべての「終わり」を意味する。「自分が死んでも世界は何も変わらずに回り続ける」という認識にネガティブな気持ちを感じるのは、認識に囚われた人々の特徴である。
勿論認識できない 生命 の「 生 」と「死」はいつまで経っても自分の一部にはならないし、そこに無関心であり続けるしかない 生命 は「日本的父性」を宿すこともできない。
「 生 」と「死」はいずれも 生命 の いのち に大きく影響すると考えられる。というのも、「 生 」や「死」に触れる体験は、 直覚 を受け取る可能性をとても大きくする。
認識スクリーンの 透過度 が極めて0に近かったとしても、この強い 直覚 は僅かばかり届く可能性がある。しかし、認識世界の住人からすれば、「 生 」は日々の認識そのものであるから、「 生 」が生み出す 直覚 もいつものように無意識の間に圧縮変換されてしまう。しかし、「死」は未知なる体験であって、認識技術がどれほど 向上 しようと、体験したことのないものなので変換不可能な部分が必ず出てくるのだ。
「 生 」にも例外はある。 輝化の条件で述べた四つの状況 に触れた時の「 生 」が生み出す 直覚 は、「死」ほどではないが、圧縮変換されずに届く可能性を孕んでいる。だがそれはそんな簡単なことではない。それでも「 生 」からの 直覚 を受け取らない限り、臨死体験をしたり誰かや何かが「死」なないと認識世界の外側に気が付く可能性さえ持てないということになってしまう。
物化 する大地に根差して生きるということは、無数にある「 生 」と「死」に溶け合って生きるということでもある。一つ一つの「 生 」や「死」は当たり前のように強い 直覚 の可能性を纏い、 直覚 は 「全」 であり、それは「 生 」や「死」を飛び越えたものに触れるということでもある。
「 生 」も「死」も全てを「融解・抱擁・輝化」させ、 「全」 の一部として循環させる大地性は、それ即ち「日本的父性」でもある。「大地性即是日本的父性」であり、「日本的父性即是大地性」なのである。
物質的空間も時間も超越していく 風景 こそが大地性であり、それは歴史そのものでもあり、「今ここ、この瞬間」の永遠でもある。
大地に根差した生活をしていた時代の人々は、言わずもがな大地から 日本 的な「父性」を教わり、自分自身もまた大地の一部として 日本 的な「父性」を身に纏うことができていたのではないだろうか。
つまり、「 生 」や「死」はいずれも「日本的父性」の必要不可欠と言っても過言ではない構成要素であり、大地に根ざすことは、「日本的父性」を取り戻すための第一歩だと言ってもいいのではないだろうか。
「どんなに恐ろしい武器を持っても、たくさんのかわいそうなロボットを操っても、土から離れては生きられないのよ。」
-シータ『天空の城ラピュタ』
-志というサムライスピリッツ
こうした「生」や「死」を飛び越えるほどの何かを持ち合わせていた存在として、「侍(武士)」について見ておきたい。
もしも侍たちが何かを「信じて」いたわけではないのだとしたら、一体何が、「 切腹 」 という世界でも稀に見るほど残酷だと言われるような自殺の形を可能にしたのだろうか。
それは先ほども少し述べたように、彼らの 意志 決定が「生き様」という軸に根ざしていたからだと考えるのが一般的である。
侍に限らず、近代以前の 日本 では、儒学やそれに付随する道徳教育が学問の中心としてあり、「どのように世界を理解するか」ではなく、「どのように生きるか」を小さい頃から学ぶ文化が根付いてきた。
そうした生き様の追求は、言語化や認識可能な成果物を残すといった「圧縮」の行動に限界を感じさせ、言語化できないレベルでの日々の鍛錬や生活の機微、「 物化するもの がどれだけ身体と共にあるか」に表す流れを生み出したと考えられる。
また、それを 日本 の自然環境と共にある暮らしの中で追求していくと、当たり前のように世界との溶け合いや、自身の利ではなくその拡張が求められるようになっていく。それは現代で言うところの「社会性」や「利他心」という概念では全く置き換えきれないほどの広さと溶け合い方を孕んでいる。
「 切腹 」という極めて残酷な自殺を生み出したのは、全的感覚の 「ゆたかさ」 から生まれる大いなるものの力だったのではないだろうか。
こうした侍の心を一文字で表す「志」(士の心)は、本稿で言う 「全」 に触れた状態で生まれる「 いのち の信号」だと捉えられる。 直覚 があってこそ、ようやく生まれる「志」なのだ。
一方で、認識スクリーンに囲われて生きる現代の 日本 人の 意思 決定の指針となるものはこの「志」に比べると遥かに小さくて狭くて薄くて脆いものなのではないだろうか。それを現代では「 意思 」と呼ぶ。
認識世界の住人は、認識スクリーンに映る世界を基に、並んだ選択肢から好きなものを選ぶ。何を選ぶかは各人の状況や感情、経験、身体性なども踏まえた「 意思 」によって決定され、それが他者(認識世界の外側)への影響の大きいものであった場合、「社会性」や「利他性」という言葉を媒介して語られたりもする。この「 意思 」は認識世界の状況を変化させるトリガーになり得るため、認識世界の住人にとって重要だが、それは脆弱な認識信号に過ぎない。
生命をかけて何かを成し遂げようとする姿は、現代の多くの人にとって少し恐怖感を感じさせる。何かに支配され、洗脳され過ぎてしまったんだろうなと、感じる人が多いだろう。それはドラマや映画、小説など、ノンフィクションの物語であれば感動の対象にもなるが、現実的に身近にそんな人がいたら冷めた目で見る人がとても多い。
日本的な「生の原動力」を見失った人々は、生命を懸けてでも生き様を貫こうとする姿勢に無関心になりやすい。ものすごく強い洗脳的な「意思」しか思い浮かべることができず、風のようなふわふわした「意志」に触れることができない。
豊かな 認識とは比べ物にならないほどの ゆたかな 直覚 を受け取ることができなければ、そんな「意志」は育まれない。
何かの思想を持ち、強く洗脳されて目的や意味を達成することが重要なのではなく、「生」も「死」も抱きしめて超えていく姿、それでも大地に立って生きる様そのもの、そうした生き様にこそ「意志」と呼べるものを見出せたのではないだろうか。
「どんなに恐ろしい武器を持っても、たくさんのかわいそうなロボットを操っても、土から離れては生きられないのよ。」
-シータ『天空の城ラピュタ』
-大切と親切
次に、「日本的父性」の 発露 に重要となる「大切」と「親切」という二つの言葉について探求したい
まず、「大切」という言葉は、「大きく切る」と書く。そのせいで意味合いに困惑する人も多いが、元々は、「おおきくせまる」と読み、とても切迫して緊急を要する様を表す言葉として使われていたそうだ。それが転じて「重要なもの」「かけがえのないもの」という意味合いで使われるようになったという。
「親切」という言葉も、「親を切る」と書くために難解に感じるが、「切」という字は、ある漢字の下に付いて「非常に~である」という意味を表す働きがあり、「非常に親しい」という意味で「親切」という言葉が使われるようになったと言われている。
このように、「切」という字は、とても多くの意味合いを持つ漢字である。成り立ちは、「縦横に切りつける」象形の「七」と「かたな」の象形の「刀」を合わせた文字とされている。
①きる。たちきる。きりさく。
②こする。みがく。きしる。
③せまる。さしせまる。
④ぴったりあう。
⑤しきりに。ひたすら。
⑥ねんごろ。ていねい。
⑦すべて。一様に。
⑧きれ。断片。
⑨きり。くぎり。終わり。
なぜこの字がこれほど多くの意味合いを持つようになったのかを考えるのは非常に興味深い。くっつけて合わせるイメージと、切って分けるイメージの両方を含んでいるのに加えて、「一」と受け取れる意味合いから、「全」を想起させる意味合いまで、一見矛盾しているとも受け取れるものをどちらも含んでいるのだ。
漢字の成り立ちからして①が起点だとすると、「切る」から連想されるものがたくさん新たな意味合いとして生まれていったことがよく分かる。気がついた時には、「大きく切る」が、「大切」という意味合いを表す言葉に変化したということでもある。
もし、①から⑨までの意味合いが転々流々し、表裏一体の可能性を持つということを「切」という漢字の歴史から読み取るのなら、「大切」も「親切」も、認識できないところで①から⑨の 風景 を転々流々と循環し続けている可能性があるのかもしれない。
「大」を「大きく」や「とても」の意味合いとすると、「大きくきる」「大きくみがく」「とてもさしせまる」「大きくピッタリ合う」「とてもひたすら」「とてもねんごろ」「大きくすべて」「大きい断片」「大きなくぎり」の全ての 風景 可能性を「大切」という言葉は秘めているのではないだろうか。
たとえ現代で一般的な「とてもねんごろ」という意味合いで使ったと認識していても、その先にある 風景 には、これら全ての可能性があるのではないだろうか。
つまり、「大切にする」ということは、何かを「大きく切る」ということなのかもしれないし、知らないところでこの世界のどこかに「大きなくぎり」を生み出しているのかもしれない。
同じく「親切」もそのようである。「親切にする」ということは、「親しみを切る」、あるいは「親しみのくぎり」を生み出すことなのかもしれない。あるいは「親」という漢字の転々流々性を考えるともしかすると「親切にする」ということは「親を切る」ということかもしれないのだ。
「言葉」というのは多くの人が使うようになってはじめて意味合いが定着していくことを考えると、こうした 風景 の表裏一体可能性は、長い歴史の中で醸成されてきた結晶物であって、こうした 風景 の全てを無視しないことは、「全」及び いのち に誠実に生きることと同じなのかもしれない。
「安心安全」への執着を原動力とする現代の「母性社会」では、「大切にしたい」という言葉の裏に、こうした 風景 の広がりを感じることはまず無い。「大切にする」ということが、「安心安全な存在でい続ける」という意味合いだけを認識させることが多い。
認識スクリーンで自動化されたこうした「一」から「一」への変換は、やはりオナニズム的に働くしかないのだ。だが、認識できないところで真逆のことが世界のどこかで一緒に生まれている可能性がある。
貴方が何かを「大切」にした時、この世界のどこかで誰かや何かが大きく切られているかもしれない。何かを「大切」にすることは、自分やその相手が「大きく切られる」可能性をこの世界に生み出すことなのかもしれない。
そうした 物化 する 風景 を直視せず「融解・抱擁・輝化」することのない「大切にする」という行為は、ものすごく短絡的な自己 満足 なのかもしれないとも考えられる。
また、現代で「親切でありたい」と願う人の多くは、「親しみを切る」とか、「親を切る」という行為を「しない方が親切である」と自動変換している。自分の生き様よりも先に「親を安心させてあげたい」という文句が語られるようになったのも、ここ最近の風潮なのではないだろうか。「親孝行」を、親の価値観を満たしてあげることだと認識している人もとても多い。
「生き様」がどれだけ蔑ろにされていても、誰かの認識を満たしてあげることができているならば、自分はその人に対して「親切」にできていると感じる人も多い。
だが、それはもしかしたら、この世界の何かを無視しているだけの認識オナニズム的な「親切」に過ぎないのかもしれない。何かや誰かに「親切にする」ことは、時に大きな痛みや苦しみを生み出しているのかもしれない。
「大切にする」ことも、「親切にする」ことも、こうした 風景 をそのままに受け取り、そこで生まれる苦しみや悲しみ、痛みをちゃんと受け入れてでも、誠実に向き合い尽くしてでも、それでも何かを「大切にしたい」と、「親切にしたい」という「 意志 」を持てるかどうかということなのではないだろうか。
近年、世の中を飛び交う「誰も傷つけたくない」「誰一人取り残さない」といった言葉の背景に、これほどの「父性」を感じることはほとんどない。皆認識オナニズムの中を生きて、「大切にする」とか「親切にする」といった言葉を短絡的に使用しては「安心」「安全」を提供し合い、満たされているようだ。
何かや誰かを「大切にしたい」のなら、いざと言うときにその何かや誰かを「大きく切る」かもしれない覚悟を、その時に認識的な縁切りではなく、 生命 を懸けてでも誠実でいる覚悟を、同時に持たねばならない。
何かや誰かを「大切にしたい」のなら、何かが起こったときに「大きく切られたとしても」それに向き合って抱きしめて、それでも「大切」にできるかを自分に問うことを忘れないで。
何を基準に何かや誰かを「大きく切る」のか、本稿を通して伝えたい想いはここにある。
たとえ大きく切ったとしても、それが「日本的父性」を宿した行為でありますように。そこには、 いのち への「許し」の前提と「超越」への 直覚 、全てを抱きしめる「大丈夫」が必ずありますように。そんな「大切」や「親切」がもう一度溢れる世の中になりますように。
It’s the heart, afraid of breaking That never learns to dance.
It’s the dream, afraid of waking That never takes the chance.
It’s the one who won’t be taken. Who cannot seem to give.
And the soul, afraid of dying That never learns to live
-Bette Mider『The Rose』
(つづく)