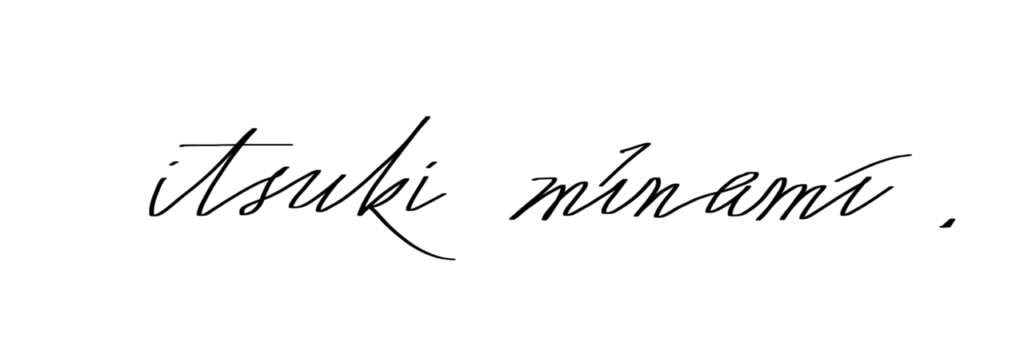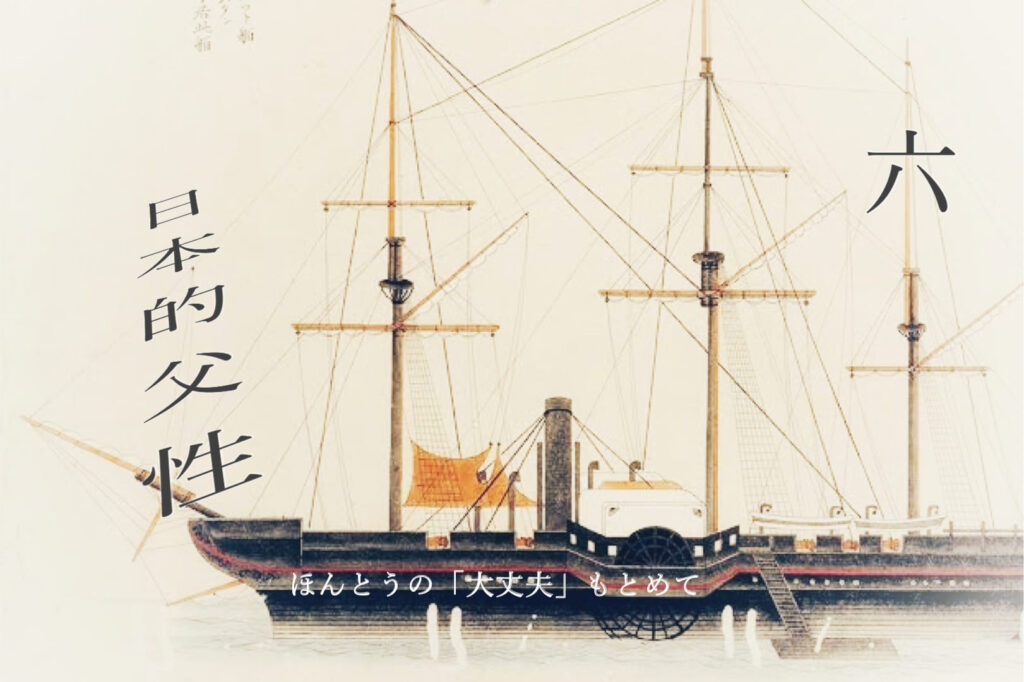
6.第二章「近代の守破離」
『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –
目次
-選択肢の沼
今、「社会」に「息苦しさ」を作り出している大きな濃い 虚構 が存在する。その一つが「選択肢」という概念である。
まだ幼い自分の子どもにお受験をさせている親や、少しでも偏差値の高い学校や進学実績のある学校に行ってほしいと洗脳のように言い続ける親や、それを盲信している子どもに、こんな質問をしたとする。
「なぜそういうことをするのですか?」
もちろん答えは多様だが、回答の中にこんなものが多く見受けられる。
「将来、何か夢を見つけたり、やりたいことが見つかった時に、良い学校を出たり、そこで人脈を作っていると、役に立つかもしれない。」
「少しでも選択肢を多くもっている事は、将来 豊か に生きていくために大切なことだと思う。」
また、日本各地の大学には「国際協力」という名目で活動している学生団体がたくさん存在する。そうした団体に入りたいと願う若者の多くは、実際に現場に赴いたこともなく、学校やテレビで教えてもらった「かわいそうな人たち」の画を想像していることが多い。彼らの活動の多くは、 日本 でカネやモノを集めて持っていくことだったり、現地に行ってちょっとした遊びをすることだったりする。彼らに先ほどと同じような質問をしても同じような答えが返ってくることが多い。
「彼らは、貧しい。僕らが当たり前のように持っている消しゴムも鉛筆も持っていない。学校にいけない子どももたくさんいる。学校にいけない子どもたちは選択肢が限られてしまって結局将来の選択肢がほとんど無くなってしまう。これは連鎖するんだ。」
「彼らに教育の機会を与えて、選択肢を少しでも増やせるように努めることは、基本的人権を尊重するということなのだ。」
だが、実際に現場で活動している人の中には、「与える支援」に声を上げる人たちがいる。
長年アフガニスタンで現地に根を張って活動をした中村哲さんは、こんなことを口にしている。
「寒風の中で震え、飢えている者に必要なのは弾丸ではありません。温かい食べ物と、温かい慰めです。」
「近代化と民主化はしばしば同義である。巨大 都市 カブールでは、上流層の間で東京やロンドンとさして変わらぬファッションが流行する。(中略)人権は叫ばれても、街路にうずくまる行倒れや流民たちへの温かい視線は薄れた」
「国土を省みぬ無責任な主張、華やかな消費生活への憧れ、終わりのない内戦。襲いかかる温暖化による干ばつ−終末的な世相の中で、アフガニスタンは何を啓示するのか。見捨てられた小世界で心温まる絆を見いだす意味を問い、近代化のさらに彼方を見つめる」 [7]
また、ウガンダをはじめとした国々で衛生環境の改善などを中心に活動してきた原貫太さんと、その現地パートナーのサイラス氏がYouTubeでこんな発言をしている。
(原さん)「アフリカを支援したいと思っている 日本 人にまず何を考えて欲しい?」
(サイラス氏)「アフリカを助けたい、アフリカに寄付をしたいと考える前に、まずはアフリカで何が起きているかを知って欲しい。アフリカの人たちを助けるべきか、それとも自立させるべきか、それを考える前に、まずは知って欲しい。もしかしたらお金ではなく別の形の支援が必要かもしれないし、それが本当の意味で助けになるかもしれない。なぜ知らない誰かのことを助けたいと思えるんだい?そこに何があるか知るためにアフリカに来る必要があるだろう。まずはアフリカに来て、住んで、そして勉強してほしいよ。」 [8]
私は十九歳の時、実際にアフリカに足を運び、そこで彼らとお話をさせてもらったことがある。実際にスラムを訪れ、そこで暮らす人の家にホームステイをしたりした。そんな中で感じたのはもっと深く恐ろしい現実だった。
これまでの様々な活動や寄付が救ってきた 生命 もたくさんたくさんある。そのおかげで発展し、富を得た人も間違いなくいる。しかし、既にアフリカにはとてつもない額の支援金や投資が注ぎ込まれているのに、最貧困層の現状はたいして変わっていない現実もある。それはなぜなのか。問題はもっともっと根深い。
植民地支配で自国の歴史と文化を破壊され、自分でなんとかしていく前に、与えられ過ぎた者たちが、精神の面で一体どうなるか想像できるだろうか。結果として現れている「次は何をくれるんだ。次は何をしてくれるんだ。」という 都市 部の一部の人々の精神性や、人のせいにする以外どうしようもなくなってしまった人々の精神性は、 いきもの として一体どれほど恐ろしいものなのだろうか。
一方で、ウガンダの自給自足の農村の家に数週間ホームステイをした時、こうした精神性とはかけ離れたぬくもりに触れた。トイレは地面に堀った穴に落とすタイプで、中には無数のゴキブリがいる。バケツ数cmの水を手で掬って水浴びをする。食事も質素で、テレビも水道も電気も無い。だけど、そこでは、多くを求めるわけではなく、僕らに同じ「 いきもの 」として接してくれる人たちがいた。夜は真っ暗だけど、それぞれのお家では大きな笑い声が響き渡っていた。
私が海外を旅していて本当に強く感じるのは、彼らの「 悦び 」、彼らの目の輝き、 いのち の生き生きとした姿なのである。それは 日本 に帰ってくるとまず感じることができない。
「選択肢」を増やし、途方もない量の「選択肢」の前に立ち尽くし、右にも左にも進めなくなって「取捨選択」という痛みから逃げるために、認識できる世界を都合よく変えていく人ばかりのこの 日本 「社会」と、 いきもの としての可能性に満ち満ちている彼らの姿を見て、到底「選択肢」が いきもの である我々に必要不可欠なものとは思えないのである。
また、現地で彼らの「 生の悦び 」に触れていると、「選択肢」という言葉には 手触り感 のある中身がなく、どれほど濃い 虚構 なのかがよく分かる。
「選択肢!選択肢!」と言っている人々の多くは、無意識の間に「せっかくあれを選択したのだから」という理由で、次の「選択肢」を絞っていってしまう。
いろんなキャリアを重ねれば重ねるほど、知らない間にどんどん「選択肢」は絞られていく。
私たちは生まれてからこれまで、様々な選択を繰り返してきた。今、この瞬間も、いくつもの選択を私たちは無数にし続けて生きている。無論ほとんどの選択は意識下では起こっていない。自分の 意思 に基づいているかといえばそうでもない。
選択肢を増やし続けているつもりになって、知らぬ間に自分の人生の 歩み が自動化されている人たちはそれに気が付くこともなく死んでいく。まるでロールプレイングゲームのキャラクターのように。これは、「選択肢」という名の 沼 なのだ。
選択肢を求めれば求めるほど、実態としては何もないラベルに触れることしかできなくなっていく。
世界はもっと自由で、可能性に満ち満ちているのに、気がついた時にはそうした可能性をほとんど喪失している。
以上の考察から、「選択肢」という概念は、私たち 日本 人にとってそれほど重要なものではなく、むしろ「選択肢」にこだわるあまり、本来の いきもの としての可能性を見失ってしまう危険性さえ大いにあることが分かる。
実は「選択肢」などという概念が存在しなかったとしても、 手触り感 のある 歩み の想像や直感があるだけで十分なのではないだろうか。
残念だけれど僕たちの国では何か大切なところで道を間違えたようですね。
–さだまさし『風に立つライオン』
-素晴らしき人間
私は小さい頃から、「 人間 らしい」とか、「 人間 味がある」といった言葉を知らず知らずのうちに褒め言葉として使ってきた。そんな私の中にあった「 人間 らしさ」とは、感情が 豊か であったり、ぬくもりのある助け合いの 風景 であった。
だが、なぜそれを「 人間 らしい」という言葉で表現しているのかと問われた時、私は立ち止まった。
私の中に浮かんでいるのは、「昭和っぽい」というこれまたぼんやりとした 風景 であった。
恐らく私のそうしたイメージは、ドラマや映画に出てきた人情味のある下町の人々の暮らしの画なのだろう。少年少女の頃は外で遊んで人を傷つける痛みや自分が傷つく痛みをたくさん覚え、青年になったら様々な葛藤の中でたくさんの過ちを犯し、親や近所の人から叱られ、人と人の関わりが深く、信頼をゆっくりゆっくりと構築していく情緒 豊か な 風景 であった。もしかすると、私の「 人間 らしい」とはその 風景 そのものだったのかもしれない。そこにあるぬくもりや味に、私は夢を見ていたのだ。
だが、その「 人間 らしさ」の生まれる 風景 は、私が育った都会の環境には全くと言っていいほど存在しなかった。そもそも隣に住んでいる人の顔も名前も知らない。道端で子どもが困っていても、大人たちは見て見ぬふりをする。声をかければ、不審者だと通報されかねない。
子どもたちはいつしか、動画で見たインフルエンサーの言葉遣いや振る舞いを演じるようになり、自分自身を曝け出すことを恥と感じるようになる。外で遊ぶ子どもの声を公害扱いするクレームは後を絶たない。 電車やバスに乗れば、何よりも自分が座れるかどうかが重要だ。多くの人がスマホの画面を見るか寝るかで、目の前に困っている人がいても気がつかない。声をかければ、「ナンパだ」とか「変な人だ」と言われる。人が人を見る目は、冷たく冷たくなっている。誰が作ったのかも分からない食材を買い、家族揃って食卓を囲む家庭も少なくなり、冷凍食品やインスタント食品を一人で食べる子どもたちがたくさんいる。
高齢者の入る施設は増え続け、孤独死は増加の一途を辿っている。オンライン上には 風景 の伴わない文字の羅列が上から下、左から右に流れ続け、小さな子どもたちが小さな画面に映される誰かの編集された喜怒哀楽に中毒のようにハマり、無 氣 力な夢を見る。実際に触れる体験の数は減っても、たくさんの経験をしたと思い込めるようになる。
テレビでは感動創作番組や芸人の内輪話が溢れ返り、今日も知らない誰かの苦手を知らない誰かが笑っている。パートナーとの出会いもフィジカルなお見合いではなくマッチングアプリに変化し、満たし合いのインスタントな恋愛関係はその延長で温かな家族の 風景 の破壊に直結していく。
人と人の繋がりも「社会」の「人間」と「人間」の繋がりに落とし込まれ、小学生の頃から「付き合う」や「別れる」といった恋愛ゲームのような感覚で愛を認識に落とし込むようにもなっている。
そんな「人間」としての 歩み は、「人生ゲーム」のように認識され、ルーレットを回してそのマスに止まってしまったことを「運命」だと認識し、そのマスに設定されている誰が作ったのかもわからない「イベント」を遂行して生きていく。「社会」的な制度として結婚し、「一生の愛を誓う」などと謳いながら、「離婚」のマスに止まってしまえば、こういう「運命」だったと言って離婚をする。
あらゆる人と人の関係が、日々の 歩み が、そんな形骸化したゲームの中に閉じ込められていく。
こうした環境の中で、人々は失われつつある「 人間 らしさ」を必死に探している。ヤンキーものやヤクザもののコンテンツは未だに根強い人気があり、スポーツや芸術、食やエンタメでも、その瞬きよりも裏話や過程に人々は感動し、心を打たれる。ついには「エモい」という言葉が登場し、感情起動スイッチをあらゆるところに探している。
かつて「 人間 らしさ」を育んでいた 風景 は消え去り、代わりにコンテンツ化された濃い 虚構 が我々を取り巻き、多くの人がそうしたものを際限なく消費し続けて生きるようになった。
「 人間 らしさ」に 手触り感 があり、「 悦び 」の源泉となっていた時代から、ただの感覚や感情を満たすための道具となった今の時代にかけて、変化したのはこうした都会の環境だけなのだろうか。
こうした変化の正体は、多くの人が想像するよりも遥かに根深く、恐ろしいほど核部にまで達しており、こうした都会環境の変化はその表出事例の一部でしかない。
「選択」や「 人間 」などの常識化した様々な概念や、そうした空虚な概念が骨格を成す「認識」そのものの 脱構築 に、今、挑まなければ、「 人間 」としての「生き易さ」ばかりを志向して、「 いきもの 」としての「息苦しさ」が蔑ろにされる流れはいつまでもどこまでも続いていくだろう。
本章では、ここから、いつどこでそうした概念が生まれ、どのように利用され、それを用いる者たちの根底で何が変容し、こうした概念たちが今、この国で何を引き起こしているのかについて詳しく描いていく。
「当たり前じゃないか。明日だって、明後日だって、50年先だって、ずーっと夕日はきれいだよ」
– 一平『ALWAYS 三丁目の夕日』
(つづく)