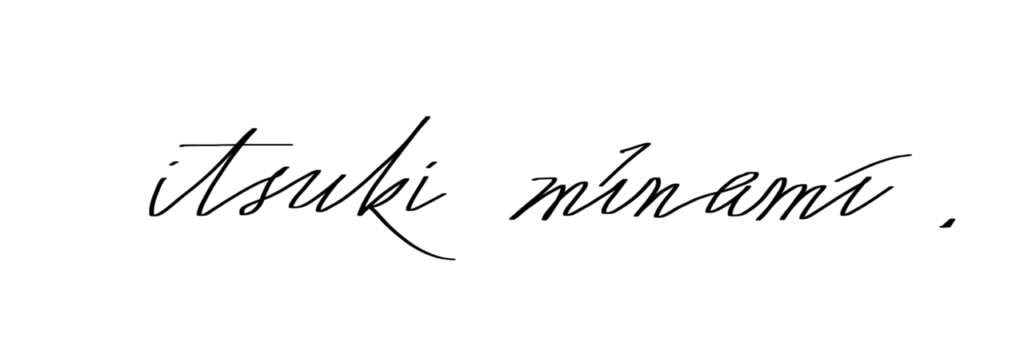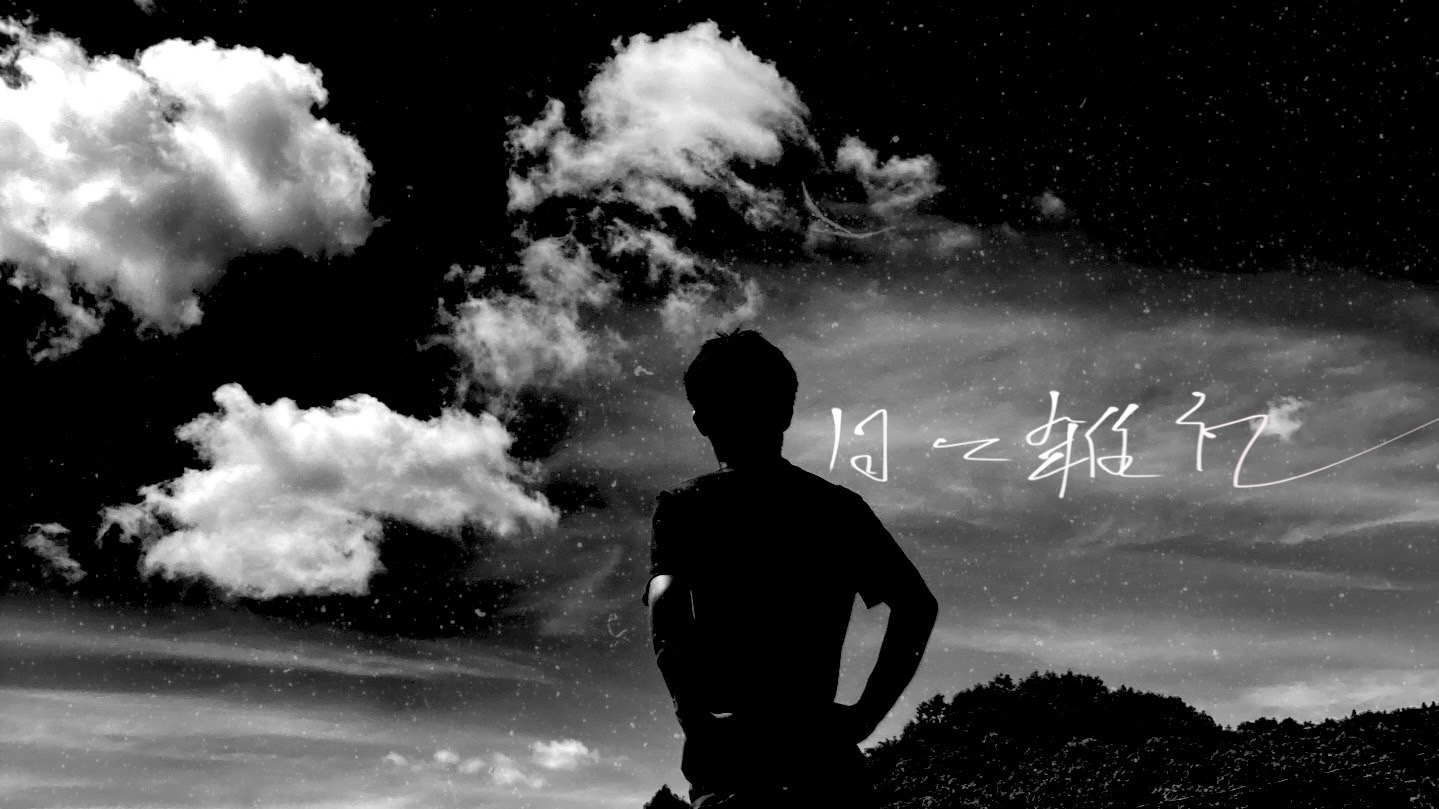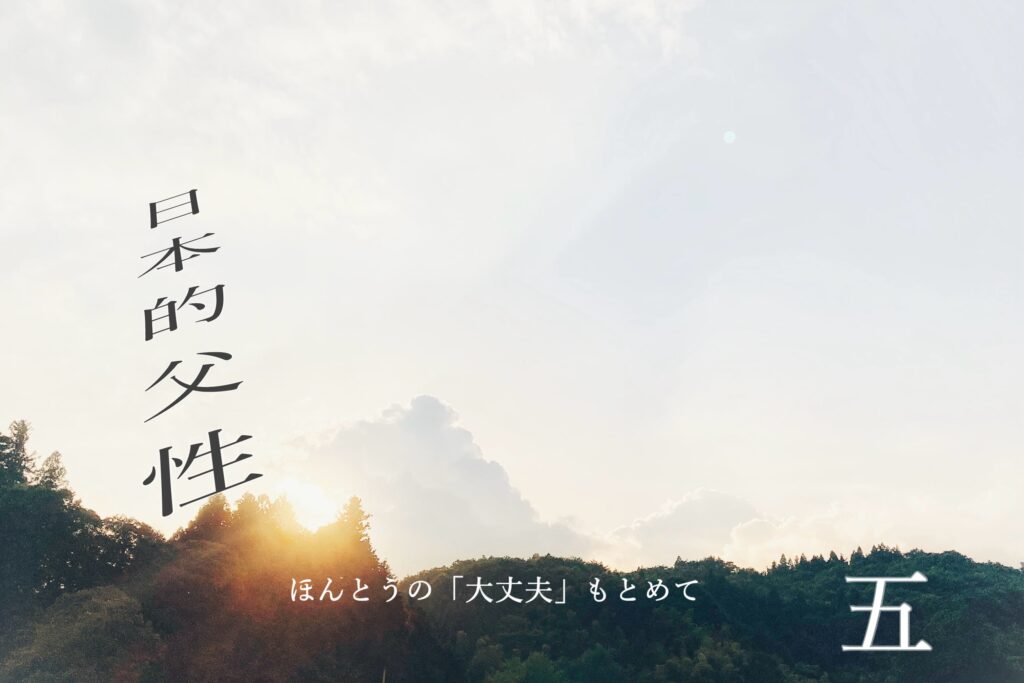
5.第一章「父性とは何か」
『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –
目次
-融解・抱擁・輝化
さて、「父性」においてとてつもなく重要なイメージをもう一つ共有しておきたいと思う。「超越」「許し」「大丈夫」を現実的にもたらすときに、どんな変化が起こるのかのイメージである。
このイメージを三つのキーワードで表してみることとする。
一つ目は、「融解(溶融)」である。
これは、固体が熱を受けて液体になることを表す言葉である。簡単な言い換えをすると「溶かす」である。あくまでイメージであり、それが固体であるか液体であるかは特に関係は無い。固体だって液体だって気体だってなんだって溶かせばいい。
「父性」の第一歩は、「溶かす」ことであるとも言える。固まった認識や状態が何らかによって「溶ける」という体験をしたことがある人は結構いるのではないだろうか。固まった何かを溶かし出したらそれはグラデーションを生み出し、フニャ〜と広がってゆく。心の中にある真っ黒なものを溶かせば、真っ黒なドロドロした液体がフニャ〜と広がってゆくだろうし、きっぱり何かを分けていた仕切りを溶かせば隔てられていたものたちが混ざり出すだろう。
こうした「融解」を生み出すのは決して「冷たさ」ではなく、「熱さ」や「温かさ」であることはとても重要である。本稿ではこの「溶かす」という現象を発生させるものを「 ぬくもり 」と呼び、「 ぬくもり 」が起こす現象を「溶かす」という 風景 で表し、そこにある全てをまとめて「融解」と呼ぶことにしよう。
二つ目は、「抱擁」である。
これはその言葉の通り「抱きしめる」ということである。ここで重要なのは、対象を一人にしないということなのだ。勿論対象が人でない場合もあるだろうが、いずれにせよ、溶け出したものがどんなに汚かろうと、苦しかろうと、悲しかろうと、痛かろうと、醜かろうと、抱きしめてやんなきゃならない。
そしてイメージとしては、「並列の固体同士がくっつく」というイメージではなく、対象を丸々包み込むような、だけど暑苦しくなく、息苦しくなく、寧ろ息がしやすくなるような形で包み込むイメージである。
勿論物理的に抱きしめればいいという話ではない。固くて冷たいものに抱きしめられたら溶け出したものもまた固まるだろう。温かさを感じられるが、爽やかな気体が包み込んでくれるような、そんなイメージである。
また、「融解」の段階では「ぬくもり」さえあれば、勝手に溶け出すこともできたが、この抱きしめる時には「勇 氣 」が必要になることがある。特に、自分自身で自身の何かを溶かして抱きしめるときは、「 意志 」が育む「勇 氣 」が必要になることが多い。
さらにこのタイミングで、一時的にでも、「母性」で言うところの「安心」を満たすことも大切である。そこには、当然のようにどんなことがあっても逃げ出さないでいてくれるという安心感が必要だ。絶対に消えない居場所が必要だ。
「父性」でもたらされる「大丈夫」は、「安心」のもっとその先にある感覚のことだからだ。
こうして抱きしめられているうちに、黒い液体はその黒さをちゃんと元に含んだまんま橙色や黄色の優しい色に変化していく。混ざり合った別々の液体も合わさって世界で唯一の色になって、その色をちゃんと元に含んだまんま橙色や黄色の優しい暖色に変化していく。今まで嫌いだったものや怖かったものも、ものすごく温かな仲間に様変わりする。
そして三つ目は、「輝化」である。
これは、液体が気体に変わる状態変化を表す「気化」と、世界の無数の いのち の「輝き」を合わせた造語である。溶け出して抱きしめたものが「気化してその全てが世界の輝きになる」というイメージである。
粒子状に広がって光り輝いてゆくその光景は、元がどんなものだったとしても同じように、あまりにも美しいものである。それらが世界に広がり、自身の身体にも浸透してゆき、澄み溶けていく。「 物化 」 と似たようなイメージである。「一」が 「全」 になって、「一即是全」「全即是一」になっていくような感覚である。
一つ目の「融解」や二つ目の「抱擁」は、人の「ぬくもり」や「 意志 」次第で引き起こすことが可能だが、三つ目の「輝化」は、自分の力ではまず起こらない。
こうした瞬きを生み出す外的要因としては、例えば、ゾーンやランナーズハイに入るような体験や、とてつもない「父性」を宿した誰かとの肌の触れ合う接触、多くの人との溶け合い、圧倒的な自然環境との溶け合いなど 、 いくつかの特殊な状況や環境を想像できる 。それぞれについて少し詳しく見てみよう。
一つ目の「ゾーン状態」や「ランナーズハイのような状態」とは、その二つに同時に入った時に引き起こされる感覚のことである。こうした状態をホルモンや神経伝達物質の話で考えることもできるが、分泌の制御を極限まで人為的にできるようになったとしても、全く同じような状態を作り出すのは不可能な神秘的なものなのではないかと仮定すれば、いつゾーンに入るかは誰からも予測不可能であるし、個人の特性によっては、そもそもゾーンのような体験をしない人も多いだろう。
二つ目のとてつもない「父性」を宿した人とは、そもそも現代では出会うことがほぼ不可能に近い。そして出会ったとしても、肌が触れ合う接触をするには多くの高いハードルが存在する。
三つ目の多くの人との溶け合いというのは、「とてつもない 生 の グルーヴ 」と表すこともできる。多くの「 喜び 」が一体となる感覚に近い。こうした「 喜び 」の溶け合いは、一人称を完全に超越して、無人称・無限人称的になる。そうした感覚を孕む「 喜び 」を、「 歓び 」と表そう。音楽やスポーツにおいては、そうした「 歓び 」の瞬間が生まれることが極々稀にある。
四つ目の圧倒的な自然環境との溶け合いとは、とてつもない量の「 生 」と「死」、 いのち に包まれ、環境に対して「絶対に敵わない」と 直覚 してしまうような状況で、予測不可能なこと、 風景 、奇跡に遭遇したり、恐怖に包まれたりし続ければ、その先にこの世界の全てが仲間になるような瞬間が訪れることがある。
ここでは想定されていないものも含めて、こうした体験の中で、液体になった暖色のものたちが気化し、輝いて自分の一部になって、世界の一部になってゆく瞬きが訪れることがある。このような奇跡を「輝化」と呼ぼう。
また、 日本 人の中でも未だに いのち の「 悦び 」に根ざして生きている人の日常の中には、この「輝化」という感覚が溢れていたりもする。
この「融解・抱擁・輝化」の三段階を通して、固体や液体として貴方の重荷や壁になっているものたちは全てちゃんと自分の一部となってゆくことができる。
この三段階の要所要所で必要になるのは様々な いのち が持つ「父性」であり、「父性」における「超越」「許し」「大丈夫」のそれぞれにこの三段階はとても重要になるのである。
貴方などこの世界の 切れつ端にすぎないのだから 貴方など懐かしい 切れぎれの誰かや何かの 寄せ集めにすぎないのだから
だから いつでも 用意さるゝ 貴方の居場所 どこにでも宿る愛 どこにでも宿る愛
変はりゆくこの世界の あちこちに宿る 切れぎれの愛 ほらご覧 いま其れも 貴方の 一部になる
– コトリンゴ『みぎてのうた』(この世界の片隅に)
-「父性」のその先に
私たち、この世界の全ての いきもの は、それぞれ世界に一つだけの特徴を持って生まれてくる。その生まれ持ったものがどのように発達し、どのように変化していくのかについては、育ち、生きていく環境に大きく依存している。誰も生まれて来る場所は選べないし、育つ環境だって、生きていく環境だって、選ぶことのできない領域の方が明らかに大きい。
そうした環境の中で醸成される一瞬一瞬の一つ一つの特徴もまた、 世界に一つだけの奇跡的な結晶 である。
しかし、後の章で詳しく解説するが、我々はそうした過程の中で、知らず知らずのうちにたくさんのことを学び、「一般的なもの」を覚えていく。
例えば、生まれもった身体に、右手が無かったとしよう。多くの人が、その身体を見て、「一般的なもの」から外れていることに気が付く。
これは「慣れ」の問題でもある。経験が無く、慣れていなければ驚いたり、過剰な注意を払ったりもするだろう。
更にそこに、「一般的なもの」への指向性があると、その身体に、ネガティブな気持ちを抱く可能性が高い。「一般的なもの」への指向性とは、生きていく過程で経た様々な(「社会」)環境の中に存在していた、何らかの指標に基づきネガティブとポジティブな出力を創出していく営みが、人々に植え付ける認識の癖のことである。
「一般的なもの」への指向性ではないとしても、そうした何らかの指向性(認識の癖)は、全ての人が持っているものである。その指向性がより強く、その指向性からより離れた特徴を持っている程、ネガティブな感情が生まれやすいとも言えるだろう。
「右手が無い」
と聞いて、すぐにネガティブな印象を持つ人が多いのは、それまで生きてきた環境で右手が無い人と関わり、「右手が無い」ことになんの違和感も感じなくなるほど慣れることが、多くの人にとって難しいからだ。
もしくは例え慣れていたとしても、その特徴がネガティブに働く場面にばかり立ち会ってきたり、当人がその特徴にずっとネガティブな認識を持っていれば、結局「右手が無い」ことに対してネガティブな印象を持つ可能性は高くなるだろう。
多くの場合、「一般的なもの」への指向性は、歳を取ればとるほど深く、濃く、分厚く、強くなっていく。
その一方で、より様々な特徴を持った人と深く関わって助け合いながら生きていけば、慣れる範囲も広くなっていく。この慣れる経験が増えていくと、「慣れていないもの」に出会ったときの感じ方や気持ちの持ち方さえも勝手に変化していく。
自分自身の何らかの特徴が、「一般的なもの」から外れている程、多くの人からネガティブに受け取られる可能性も高くなる。自分はただ、ありのままに生きているだけなのに、相手を嫌な気持ちにさせて怒られたり、嫌がられたり、いじめられたりする経験にも繋がりやすい。これは身体的な特徴に限った話ではなく、我々すべての人のあらゆる特徴について言えることである。
このようにありのままに生きていることがネガティブな「何か」に繋がっている状態に、痛みや苦しみを認識していても、特別認識していなかったとしても、誰かがそうした状況を変えてくれた時に、「解放された」「救われた」と感じることがある。
それが「かわいそうだからもうやめなよ」といった母性的な 同情 や 共感 の深層心理から生まれた言動であった場合、それによって「救われた」側は、以降より母性的な安心への執着を強く持つようになる。そうなると、その場ではネガティブな環境が無くなったとしても、こうした自分自身の特徴に対してのネガティブな認識は消えず、寧ろ、より「触れられたくない」「気が付かれたくない」という深層心理を強く宿すようになりやすい。その反動として生まれる新たな特徴は、更に違和感や 虚構 味を感じさせる「調和」のとれていないものになることも多い。
一時的な救いは、痛みや苦しみを消し、安心や安全をもたらすために非常に重要なものである。しかし、それを繰り返していると、せっかく生まれた、この世界にたった一つの奇跡的な結晶は置いてけぼりになっていく。
それを消せば、周りは笑顔になってくれるかもしれない。それを忘れれば、この世界に余計な痛みや苦しみ、嫌な気持ちを生まなくて済むかもしれない。
この世界にはそうして「触れてはいけないもの」「触れられたくないもの」「わざわざ触れない方がいいもの」が溢れている。
これを繰り返していけば、一つ一つの事象が「融解」することもなく、「抱擁」されて「輝化」することもなく、自分自身の暗部に不発弾のように格納され続けていく。
何かあった時に「融解・抱擁・輝化」を齎してくれるような人が周りにいなかったり、そうした体験をできないようなぬくもりの無い環境で育った子どもたちはこの「不発弾化」とも言える認識技術が飛躍的に 向上 する。
この流れはほとんどの場合無自覚に起こっていることであり、痛みや苦しみから逃れるための生存戦略の賜物であり、これもまた、一所懸命に生きた結晶なのだ。
一方で、ネガティブな状態を変えてくれた言動が、「それはもうそういうものなんだから、それはそうと、この左手の器用さを見てよ」「どうでもいいけどお前イカしてるぞ」といったような、父性的な「超越」をもたらすピュアな言動であった場合、それによって、「救われた」側は、「右手が無い」ことにネガティブな認識を持つよりも、「右手が無い」からこそ生まれるものに目を向けてポジティブな認識を持てるようになったり、「どっちゃでもええ」と思えるほどに自分自身の特徴を受け入れて生きていけるようになったりすることがある。そんなことが起これば、自分の特徴への認識は「融解」され、「抱擁」「輝化」して、自分の一部になって生きていくことができるようになるかもしれないのだ。
しかしそれも、その後に「裏切り」が待っていると、痛みや苦しみはより大きなものになって襲ってくることになる。こうした「超越」をもたらしてくれた存在が、
「あ、やっぱり、右手が無い君とはやっていけないわ。」
「右手が無い君は私を 満足 させられないから。」
と、自分の都合で身勝手に縁を切った途端、この人は「死」に極めて近い絶望を突きつけられることになる。特にそれがこの世界で唯一、自分のありのままを認めてくれている人だと思っていた場合、この「裏切り」的な言動が持つ殺傷能力は想像できない程のものになる。
だからこそ、「大丈夫」が大切なのである。
「右手が無い」ことにネガティブな気持ちだけを感じずに、その人とありのまんまに付き合っていこうと思うのなら、その人が「右手が無い」せいで自分が苦労をすることになったとしても、迷惑を被ることになったとしても、他にもっと煌めきを感じるものに出会ったとしても、「右手が無い」ことを理由に縁を切ってはならないのだ。認識を覆してはならないのだ。それで相手が死んでも、もうどうしようもないのだ。例え 生命 を絶たなかったとしても、そんな殺傷能力の高いもので突き刺し、抉られた心は、簡単に治せるものではない。だからこそ、「大丈夫」が大切なのだ。私たちは「大丈夫」を忘れてはならないのだ。
たとえ自分のことを「ダメだなあ」と感じていても、
「それでも自分が愛おしい」と思えるようになることが、大切なのでは
– 乙武洋匡
-炙り出される限界
ここまで見てきたように、「父性」とは可能性そのものなのである。
この停滞した「社会」で、「超越」はイノベーションを生み出し、「許し」はそのイノベーションを受け入れて広げる役割を果たす。
また、「超越」を生み出すまでのプロセスで生じるあらゆる「失敗」を乗り越えるためにも、「許し」が必要とされる。
そして、そこに「本 氣 」で挑戦できる者が現れるためには、周りの環境が「大丈夫」でいてくれることが大切なのである。「失敗」や「ミス」をしたからと言って簡単に「関係を断つ」とか「縁を切る」と言わない「大丈夫」の精神性が「父性」の基盤になるのである。
「超越」とは、誰かの「息苦しさ」を取り払うために重要なものである。
誰かが困っているときに「安心」や「安全」をもたらすのは「母性」かもしれないが、「父性」はその先の相手が想像もできなかったこと(求めてさえいなかったもの)をもたらす可能性を持っている。
悩みも苦しみもどうでも良くなってしまうほどの、もっと広い世界を、ちゃんと「大丈夫」の「ぬくもり」を持って見せる傷だらけの背中が、「父性」なのである。伝統の継承も、世代交代も、イノベーションも、「息苦しさ」の気化も、あらゆるものに、今、「父性」が必要とされているのだ。
だがしかし、何でもかんでも「超越」を目指していたら、何でもかんでも「許し」ていたら、この世界はぐちゃぐちゃになってしまわないだろうか。
例えば、「超越」に正義感を持って法律に反することを堂々として誇らしい顔をしている人が現れたらどうだろう。「ね?こんなルール思い込みでしかないんだよ。」と正義を主張していたらどうだろうか。ましてやそれを「許す」ことは大切なことなんだろうか?例えば自分の大切な人がその人の正義感で殺されたとしても、貴方は「許す」ことが大切だと思うだろうか。
もっと言うと、我々が簡単に用いている「大丈夫」は、一体どこまで「大丈夫」なんだろうか。
相手に「安心安全」をもたらすことでその場を乗り切ろうとするのは、「大丈夫」なのだろうか。その場しのぎの「大丈夫」は、寧ろ凶器にさえなり得るのではないだろうか。トムは簡単に「大丈夫」なんて言葉を使うことはなかったが、彼の中には間違いなく「大丈夫」があったのだ。きっと山に水源を発見できなくても、彼は何か自分にできることをし続けただろう。
ほんとうの「大丈夫」とは一体なんだろうか。
「大丈夫」が「最後の砦」なんだとしたら、それが破られたらもう終わりということなのだろうか。
ましてやそれがその場しのぎの「大丈夫」でしかなかったのなら、相手が強敵だったり望み通りにことが運ばなかったら簡単に突破されてしまう くだらない 砦なのではないだろうか。
こうした自己 満足 の 「(見方によっては)押し付けがましい父性」 は、この世界から「安心」や「安全」を奪い取る不誠実な道具になる可能性を十分に持っているのではないだろうか。
誰かの「認識」を「超越」して、新しいものに気がつかせてやろうという気持ちは、単なるはた迷惑なのではないだろうか。
そもそも何かの「認識」に囚われている人に新しい「認識」を与えても、結局はまた何かの 「枠(囲い)」 に閉じ込めるだけなのではないだろうか。
自己啓発本や「意識高い系」に対して「気持ち悪さ」を感じる人たちは、ここまでの「父性」の話を聞いても、そのネガティブな側面ばかりを見てしまうのではないだろうか。
その通りである。
そもそも、現代の 日本 人が「父性」を体現しようとしたところで、様々な問題の解決を促す可能性を生む一方で、「(見方によっては)押し付けがましい父性」による「安心」と「安全」の破壊に繋がってしまう可能性も生み出すのである。
「Aにするか、Bにするか」などの○項対立で悩んでいる人に、「Aだろうが、Bだろうがどっちゃでもええやないかい」「そんなことよりCは最高じゃないか!」と言って、囚われた認識そのものからの超越をもたらしたとしても、現実問題AかBしか選べない環境が目の前にあれば、その環境下では選択不可能なCを提示されても困ってしまうのだ。
真剣に向き合っていたはずの問題の解決そのものが不要になってしまう程の「父性」は、現実的には混乱をもたらしてしまう可能性が高いのだ。
これが、骨格だけの「父性」の限界だと言うこともできるだろう。
こうした限界性を埋めるように、 西洋 では「宗教」が広まったと考えることができる。キリスト教でも、ユダヤ教でも、イスラム教でも、仏教でも、「超越」は「神」の成せる技そのものであるし、「許し」の重要性は各宗教で強調されるキーポイントになっている。更に いきもの としての「大丈夫」を担保するものがこうした宗教の存在する理由だと言うこともできるかもしれない。
しかし、 日本 でこうした宗教が生まれなかったのは、 日本 で独自に育まれてきた「何か」が、その限界性を超越する「奇跡」そのものだったからなのではないだろうか。
本稿ではその「何か」を「日本的父性」と呼ぶ。
「何か」を失った近現代の 日本 人を、三島由紀夫は 「空っぽになった日本人」 と表現した。彼が 切腹 自殺をしてから何十年と月日が経った今日も、 日本 人は何も変わらずに空っぽのまま、寧ろそれが更なるディストピアを作り出しているのではないだろうか。
ここまで「父性」の骨格と可能性を、そこに広がる化学変化的イメージと共に描いてきたが、本稿はあくまでも「父性」の中でも「日本的父性」というものを探求していくものである。
この「奇跡」と呼べるようなものが、 日本 の歴史の中でどのように醸成されてきて、それがどれほどこの島国で生きる人々にとって大切なものであったかということを「日本的父性」という言葉に託して描いていこうと思う。
「宗教とか人の信仰ってみんな人間が作ったもの そしてどれも正しいの
ですから正しいものどうしのあらそいはとめようがないでしょ」
–手塚治虫『火の鳥(太陽編)』
(第二章へつづく)