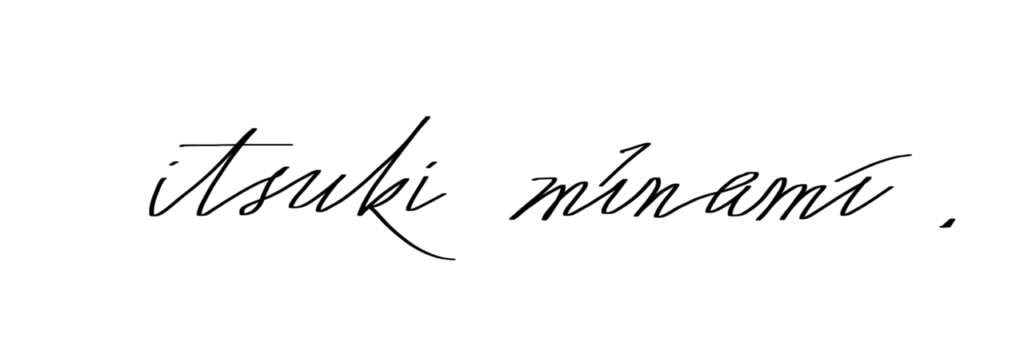1.はじめに
『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –
– pray for you
この世界のどこかに、もしもまだあなたがいるのなら。
あなたのいのちとした約束を果たすために、生きた、その日々の記録を、ここに遺したい。この原稿『日本的父性』は、その日々の結晶だ。
私にできることは、本当に些細なことしかなくて、でも、ここに残す原稿は、きっと未だかつてない未曾有のものだと、そう思えるところまでいけたんじゃないだろうか。
この世界のどこかの貴方の手に、偶然、この素読本が届いて欲しくて、それを目指してずっと力を尽くしてきた。でも、それもこれ以上は間に合わない。
自分のいのちを、生きる可能性は、誰からも奪われやしない。諦めの無い世界で、私は貴方のいのちが生きたいと叫ぶ日を待っている。
– はじめに
素読とは何か
「素読本」と聞いて、何を想像しますか?
「素読」とは、簡単に説明するならば、「意味」を「理解」するか否かに関わらず、何度も何度も言語(或いは事象)を反芻し続ける行為のことだと言えるでしょうか。
こうした行為は、日本では教育・文化などの面でとても重要な役割を担ってきました。
言語分野に目を向けると、日本に伝来した仏教は、様々な変遷を遂げましたが、その中で重要な役割を果たしたのが経典の「素読」でした。平安時代以降は、教育の分野で儒学の「素読」が中心となり、兵法書や論語などの「素読」も非常に重要視されていました。
しかし、そうした「素読」は近年「刷り込み教育」として見直しの対象となり、日常生活で「素読」を強いられる機会はほとんど無くなりました。現代に残るものとしては、小学校の音読の宿題を口でブツブツ言い続けることや、好きな音楽のメロディーを真似して歌うこと、あるいはスポーツにおける反復練習などが挙げられるかもしれません。このように「素読」を広く捉えると、私たちは「素読」的行為を常々行なっているようですが、特に「意味」の「理解」を伴わない「素読」については、より合理的・効率的な手法へと見直される流れが強まっています。
では、なぜ長い歴史をかけて培われてきた「素読」という文化が、徐々に消えつつあるのでしょうか。そもそもなぜ、「意味」を「理解」せずに繰り返す「素読」が重んじられていたのでしょうか。それはただ単に科学や教育レベルが発達していなかったからだと片付けてしまってよい話なのでしょうか。「素読」が重要視されなくっていく背景で、この国に一体どんな変化が起こってきたのか。私たちは一体何を得て、何を失っているのか。この問いの答えは、本稿を素読的に読み込み、何度も反芻することで、徐々に見えてくるかもしれません。
本稿を読む際は、一章ごとに何度も素読し、確かなものとして感じられるようになってから次の章へと進むか、もしくは原稿全体を一気に何度も読み進めるか、ご自身の心地良い方でご活用いただければと思います。
本稿を読む上で
本稿では、「父性」というテーマを軸に、多くの風景を描いています。言葉を「理解」しようとすると、よく分からないと感じることもあるかもしれません。しかし、よく分からないことに出会ったときに、「まだ見ぬ風景との遭遇」そのものを悦んでいただけたら、いつの日にか、限りない可能性と、微かな希望の感覚に触れられる時が来るかもしれません。もしも途中で「風景」として受け取ることに限界を感じたら、一つの「仮説」であると思って読み進めていただきたいと思います。
ほとんどの場合、それぞれの言葉を使うに至った「過程(文脈や風景)」が存在します。「言葉」の縛りを解き、その余白に向き合うことで、読み終わった時により大きな変化が訪れるかもしれません。
単に「理解しよう」とするのではなく、山登りをするイメージで。本稿が、あなたの人生の一歩一歩の歩みの中で、さまざまな風景に出会ったときの道標になれば幸いです。
また、本稿では「父性」や「母性」をはじめとして一般的には性別の意味合いを持つ言葉が登場しますが、本稿において性の意味合いはあくまで歴史上の生物的観点の参考程度にすぎません。また、タイトルにもある通り「日本」と「西洋」の対比が何度も出てきますが、これもあくまで曖昧な概念の対比に過ぎません。このグローバル化した時代に、西洋と日本をキッパリ切り分けることは非常に難しいため、明確な境界線を引くものではありません。「日本的父性は日本人が宿すもの」「父性は男性の話」「母性は女性の話」といった固定的な考え方は、本稿には存在しません。あらゆる境界を溶かしてもっともっといのちに根ざした思索をしていきます。
本書の構成は以下のようになっています。
第一章:現代の問題意識を共有し、「父性」の骨格を捉える。
第二章:前提を共有し、脳を縛るあらゆる「意味」を溶かす。
第三章:「日本的父性」の風景を描く。
第四章:「日本的父性」の未来を探索する。
第五章:すべてを踏まえ、手触り感のある希望を整理する。
本稿でなされるのは新しい概念の描画です。「父性」という言葉に様々な文脈を託し、一つの概念として整えていきます。ただし、言葉の定義は使う人々の使い方次第で変化します。大切なのは文脈を持って生まれた「概念」という「風景」であり、それを表す言葉自体にこだわる必要はあまりありません。
本稿の「父性」や「母性」はユングの示した父性原理や母性原理を前提にしたものではありません。それらを学習済みの方は、一度それらの概念から離れて読むことをお勧めします。
また、本稿は自己啓発書や哲学書ではなく、誰かを気持ちよくしたり共感を求めるものでもありません。あえて言うなら「素読本」です。読んだからといってすぐに何かが変わるわけではなく、むしろ多くの読者が「モヤモヤ」を感じるかもしれません。
本稿に描いているものは「風景」であり、それ以上でもそれ以下でもありません。ふるさとの「風景」は、歳をとってから懐かしく思い出されることがあります。今、誰かが遺しておかなければならない「風景」を、可能な限り圧縮することなく遺す。それが、本稿の使命です。
この「風景」の先にある微かな希望の灯(ともしび)に触れたとき、そこにはきっと、遥かな「大丈夫」が広がっているでしょう。
もしも本稿を読み、ここで語られる「父性」や「日本的父性」の風景が多くの人の心の片隅に残り、いつの日にか、誰かが息をしやすくなったり、いのちが輝く、そんなきっかけになれば、もうそれ以上望むことはありません。
※ 本題へと入っていく前に、脳と心の準備運動をされたい場合は、「別添 第零章 まえがき」へとお進みください。特に著者のことをご存知ない方にオススメです。少し長いので、面倒な方は第一章へとお進みください。