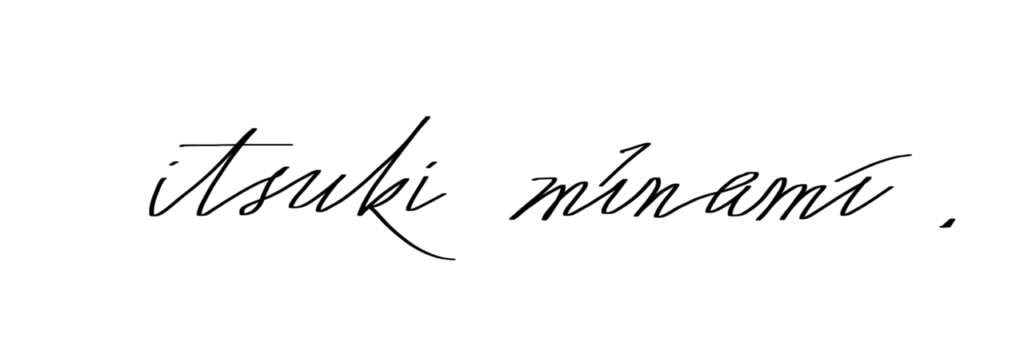1.5.別添 零 まえがき
『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –
※ 本章は、『日本的父性』全体を読む前の頭と心の準備運動のような内容です。特に、著者のことを詳しくご存知ない方向けです。少し長いため、面倒な方は、飛ばして第一章へとお進みください。
まずは私のある日の生活と、それにまつわるエピソードを通して、様々なことを想像していきたいと思います。この章で登場するキーワードは、後の章で詳しく描いていくものです。もし理解できない部分があっても、そのまま読み進めていただければと思います。そして全ての章を読み終えた後、ぜひもう一度この章に戻って来てください。きっと、最初とは全く違った 風景 が浮かび上がり、全く違った感じ方をする自分に出会えるはずです。
目次
-自然という認識
朝四時半、人工的なアラームで目が覚める。頭はぼんやりとしていて、最初の五分ほどは脳がまだ眠っているようだ。なんとか起き上がり、水を飲んで顔を洗う。外はまだ真っ暗闇だ。私は体が冷えるとすぐにお腹が痛くなるので、厚手の上着をしっかりと着込む。
—– そういえば、私は酷い時は毎日のようにお腹を下す。そんな「都合の悪い自然」とも言える身体的特徴を持ちながら、海外の不衛生な環境で育った私は、腹痛と環境の関係性について頻繁に考えさせられてきた。
小学生の頃、親の仕事の都合でインドの首都デリーに住んでいたが、外出先でお腹を壊すと最悪の事態に陥った。現地のトイレは汚く、そもそもどこにあるのかさえ分からない。まさに「都合の悪い人工 都市 」だった。
対照的に、中学高校時代を過ごした東京は、街中でお腹を下してもコンビニのトイレに駆け込めば事足りた。そこはまさに「都合の良い人工 都市 」だった。
二十歳の時、岡山の山間部に移り住んだ。ここでも突然の下痢に襲われ、山中や畑の陰で用を足さざるを得ないことがあったが、お尻を拭く物さえ常備していれば、基本的にどこでも即座に用が足せる「都合の良い自然」環境だと言えよう。
一方、十九歳の時にアフリカのサファリで腹を下した際は、ライオンが出現する恐怖に怯えながら、草原の真ん中で内容物を大地に還すしかなかった。「都合の悪い自然」ではあるが、どこでも容易に用が足せるという点では「都合の良い自然」でもある。
先日、神戸の街を歩きながらこんなことを考えていたら、コンクリートの道の上に、土に還れない大きな虫の死骸を見つけた。森の中なら、鳥や獣、昆虫や微生物が数日で跡形もなく分解してくれるだろう。しかし街中では、「気持ち悪い」と人々に忌避され、長く地面に残るのだろう。
人類 にとって「都合の良い自然」とは一体何なのか。近年地球温暖化の深刻さが増し、世界全体でその対策が叫ばれる中、「自然」との向き合い方やその概念そのものを転換せねばならぬことに 日本 人の何割が腹落ちしているのだろうか。
-民藝と音と環世界
今日は何を聞こう。オーディオブックのライブラリを見ながら選書をする。本に気分がのらない時は、好きな音楽をかけることにしている。今日はNujabesとharuka nakamuraのミックスプレイリストだ。
—– そういえば、haruka nakamuraさんがとある連載でこんなことを綴っていた。
「多角的に、客観的に、対岸から対象を見つめる。自我を外して弾き、主観を外して聴く。物事の風通しをよくすること。出来るだけ身軽に、シンプルであること。常に新鮮な状態でいること。」 [1]
本稿でこれから述べていくことに近い表現がこの文章に多く含まれている。 「全」 を 直覚 するように 風景 にそのまんま触れ、音がそのまんまに流れ、吹きぬけてゆく、そんな音側をはじめとしたあらゆる環世界での浮遊こそが、haruka nakamuraさんの携わる音楽の真骨頂といえるのかもしれない。
それは言葉や楽譜のフレーム的世界で表される諸々のポピュラー作品とはジャンルそのものを異にしている。むしろ「表す」というよりも「現れる(アラワレル)」といった方が近いのかもしれない。近年再び注目を集めている柳宗悦の「 民藝 」的な性格も、haruka nakamurasさんの音楽にはよくうかがえるのである。
こういったあらゆる垣根を溶かして「現れる」ような極めて 日本 的な特質は、 いのち そのものに「大丈夫」をもたらす力を持ち、 生 や死を飛び越えて溶け合う感覚を与えてくれるのかもしれない。
-霊性はぬくもり
玄関の扉を開け、外に出る。外は暗闇に包まれ、何も見えない。左手には小さなお墓がある。眠っているのが誰なのかは知らないが、先人の霊魂を感じ、心が温かくなる。
—– そういえば、岡山のような地方の集落では、家の裏にお墓を設けているところが多い。夜でも昼のように明るい都会から引っ越してきた当初は、真っ暗闇の中を歩くことにも恐怖を覚えたものだ。ましてや、暗闇の中をお墓の横を通って出かける時は、余計なものを見ないようにと必死だった。
しかし、時が経つにつれ、徐々に「恐怖」の湧出要因を感覚的に掴めるようになってきた。それは単なる「慣れ」の問題ではなく、もっと根深い問題に繋がる重要な感覚だった。
この点については後の章で詳しく述べるが、「 人間 」らしい生活の中で、「 人間 」が作り上げてきたもの を用いながら「 人間 」のためにばかり時間を使っている時ほど、「恐怖」を感じやすいのだ。その対処法といえば、「変なことを考えずに見ないようにする」程度のものだった。
一方で、土に触れ、風を感じ、植物や動物、様々な いきもの と触れ合い、助け合いながら、あらゆるものに溶け込んで生きる日々を送ると、驚くほど「恐怖」を感じなくなる。
そうした日々を重ねるうちに、真っ暗闇の中を一人で歩いていても、これまで気づかなかった音や香り、光、気配、世界の無数の いきもの の機微、霊性など、あらゆるものが際限なく感じられるようになる。「もっと感じていたい」と思うほどに心地よく、どれほどにこの世界が奇跡で溢れているか、ぬくもりで溢れているか、「仲間」に包まれているか、その感動が遥かに広がってゆく体験に出会える。
それは自分が長年「 人間 人間 しい」暮らしの中で生きてきたために、そうした体験をしたことがなかったからであろうし、幼少期からそうした環境で生き続けてきた人たちはわざわざそこまでの感動を持つことは無いのかもしれないが、それ以来私はあらゆる 生 や死から「ぬくもり」さえ感じられるようになったのだ。
-生に根ざさぬ誠実生
原付にまたがり、家の横の急な坂を下っていく。薄い霧の中、街灯も無い川沿いの道路をひた走る。左耳からは音楽が、右耳からはエンジン音と川のせせらぎが微かに聞こえる。数分走ると新聞屋のおばちゃんの家に着く。今日の分の新聞束を貰い、原付のカゴに積んで出発する。
—– そういえば、ここらの川には鮎や鰻が生息していて、初夏には蛍もたくさん舞う。こういった 風景 の中で暮らしていると、本当にこの国は人にとってとてつもなく 豊か で奇跡的な自然環境を有していることを実感する。まさに鮎をはじめとした川魚は、そういった複雑で生死 豊か な環境のあらゆる「奇跡」を詰め込んだような味がする。
そんな土壌で育まれた和食という文化では、「肉食」はほとんど必要とされなかった。一般的な 日本 人の食卓に畜産の食肉が並ぶようになったのは、近代化以後の数十年に過ぎない。
そういえば最近牧場を営む方と仲良くなって、畜産の現場を実際に訪ねる機会が増えた。数ヶ月毎日搾乳をするバイトをしたこともある。近年環境問題や動物愛護の観点からヴィーガンなどが広まってきているが、私が実際に牛に触れて実感したことは「 生 への不誠実さ」の問題だけであった。
なんなら繁華街や高級住宅街のど真ん中に牧場や屠殺場を造って、 人間 と動物との距離を縮め、真摯に「生死」と向き合えるようにすれば、 日本 人の食生活は持続可能な形に勝手に進化するのではないだろうか。
ちなみに、幼少期を過ごしたインドでは牛が街の至る所で人と同じように歩いたり座ったりしている。もしもインドの人口十三億人が牛を食べていたら、もう今頃アマゾンの森林は跡形もなくなっていたかもしれない
-言葉という虚構メディア
暗闇の字道を原付で走りながら、田んぼの 生 の 豊かさ にただならぬ雰囲気を感じる。すぐ上は雲だ。そしてその上に空があり、そこにも雲がある。つまり、今、「雲海」の下を走行しているのだ。
—– そういえば、空ってどこからが空だろう。
「言葉」という情報伝達手段は、人類の 文明 を大きく進化させてきた。
いつからか、 日本 でもたくさんの人が「言葉」に強く囚われるようになり、その他の世界に疎くなってしまった。
風景 無き「言葉」で表されたイデオロギー及び「意味」を、「生きる意味」や「生きがい」に結びつけるようになった。だが、「言葉」はあくまでも不完全なものだ。
「全」 なる世界の事象を圧縮しているにすぎないため、その「言葉」で創り上げられた「意味」は想像力と 手触り感 が欠けていると脆い 虚構 と化す。同じ言葉でも視点の変化で「意味」は変わるし、次元の違いで「意味」は無価値にもなる。
するとこれまで信じてきた「生きがい」を喪失する圧倒的絶望感が発生する。それを拒絶し、新たな「意味」に寄り縋ろうとして、今もまだたくさんの人が「意味」をとっかえひっかえしながら 生命 を繋いでいる。
しかし私は、その絶望に気がつくことは、多くの現代 日本 人に与えられた希望だと言いたい。その気付きは、近代思想から一度解脱し、 日本 的霊性の 直覚 や自然観の再獲得など、劣化した感性の回復と禅的で 民藝 的な価値の創造を呼び起こすキッカケになるのではないかと考えている。
そしてそのためには、 風景 (言葉では表せられない世界の広さ)を携えて「言葉」に触れること、そして絶望を忌避せずに受け入れることが必要不可欠なのである。
そしてそこに重要な役割を果たすのが、「父性」なのである。
-衰退する日本
新聞をポストに次々と投函していく。この辺りは三軒に一軒くらいは新聞を取っている。客が入っているのか心配なレストラン、東南アジアの技能実習生が支えている小さな町工場、かつて子どもたちでにぎわった面影を残す中学校。今日も様々な場所に「社会」の情報を届ける。
—– そういえば、技能実習生制度を体験した海外の友人が何人かいるのだが、彼らは皆口を揃えて「しんどかった」と言う。中には海外の詐欺業者に騙されて、 日本 食を学べると思って来たつもりが切花工場に飛ばされて、三年間逃げ出すこともできずに超低賃金で過酷な労働を強いられたという友人もいる。年間一万人近くの失踪者を出すこの制度が、 日本 の多くの工場を支えているという現状をご存知だろうか。
新聞配達で通る道中に、倒産した車屋が何軒か目に入る。しかし、車業界も厳しい状況だ。電気自動車への転換が迫られる中、 日本 中の中小企業はこれからどう舵を切っていくのだろうか。そしてそこからどれだけ 日本 独自の価値を生んでいく産業が発達していくだろうか。宇宙か、それとも新たな産業か。
今後、自然災害などの天変地異が起こらず、このまま 日本 が衰退の一途を辿れば、格差はさらに拡大し、地方の暮らしはより困難になっていくだろう。
どこかの誰かが先行きの厳しい産業で歯を食いしばって経営を繋いでいるその努力の裏で、人生の時間と健全な精神を奪い取られている人がたくさんいる。
さらに負の連鎖は広がり続けていく。「マス(大衆)」を大切にする中央集権的な国家体制を前提に若者への希望を語る「ちょっと未来について考える気のあるオッサン・オバサン」たちと、一部の数的最適解や損得の事しか考えられない「意識の高い若者」たちとは距離を取り、守破離を繰り返して目を輝かせて未来を思考できる侘び寂びた人物が何人出てくるかが、この 日本 の行く末を左右しそうだ。
果たして二〇三〇年、二〇四〇年、またその後、私たちはこの国の何を好きでいられるのだろうか。
-意味の奴隷
配達が終わって家に帰る。朝ご飯を食べて、お弁当と水筒を準備して、畑に出かける。気持ちの良い朝の風を感じながら畑に腰を下ろし、土を手で拾う。土の香りを嗅ぎ、鳥の声を聞く。青空を見て、風になる。自然の中に自分の存在を溶かしていく。 生 も死も紙一重に感じられるほど、あらゆるフレームや境界は溶けてゆく。今、都会で病んでいるたくさんの若者に、この「溶ける」という 「ゆたかさ」 や、心に風が通る感覚を伝えられたら、どれだけ新しい希望を感じられるようになるだろうか、なんて考えながら。
—– そういえば、私の友だちには不登校の子がかなり多かった。
ある時は小学校五年生の不登校の子の家庭教師をさせてもらっていたのだが、その子が言った一言は、ずっと私の心に残っている。
「なんで学校に行かなきゃいけないの?なんで勉強しなきゃいけないの?ねぇ、なんで生きなきゃいけないの?」
とっても目が輝いていて、野球が大好きで、ピュアで妹想いの少年だった。私は、彼といるのがとっても楽しかった。彼は何度も私の前で涙を流した。彼は察しのいい子だから、私がどれだけ「学校なんか行かなくてもいいし、勉強なんかしなくてもいい。」と心から伝えても、それが「社会」や両親の「正しさ」に反していると感じるようで、その「教え」からどうしても逃れられなかった。
つまり彼が私に伝えたかったことは、「社会の正しさに従うのが辛いのだけれど、ぼくは生きてちゃいけない 人間 ですか?」という純粋な寂しさだった。
「社会に認められないと生きている意味がない」と思う人が、本当にたくさんいる。
私は、ただただ、「生まれてきてくれて本当に有難う。」「君が何をしていようと、どこにいようと、素晴らしいんだ。」という気持ちを一緒に体を動かして伝えることしかできなかった。
時代と共にアップデートされない教育や、無意識下で「社会的な 人間 」であることに希望を見出す人々の存在が、あろうことかたくさんの子どもたちに「生きる意味」を考えるように迫っている。
「日本的父性」無き環境では、その反動はまたしても「意味の発見」に繋がり、その成功体験はどんどん いのち の可能性を隠し続けていく。
-馬鹿という希望
午前中の畑作業が終わって、お世話になっているぶどう農家のおじさんの家に顔を出す。「まあコーヒーでも飲みや。」からはじまり、「これいるか?あれいるか?」とたくさんのモノや気持ちを持たせてくれる。おじさんは本当に嬉しそうな純粋無垢な少年のような顔をする。
—– そういえば、これまで私の周りには、「損得」に少なからず支配された 人間 しか存在しなかった。何かをする時間を時給換算するのがクセになっている人や、与えるのが得意でも見返りを考えてしまう人、地位や名誉や実績で人との関わり方を変えてしまう人、自分や相手のメリットデメリットを考えて関わるべき人を決める人、そんな人ばっかりの「社会」で育った私にとって、正義感や文脈もなく本当に純粋にただただ目の前の いのち と向き合えて、自分や相手の 悦び を心から悦べるそのおじさんとの出会いは、感動に溢れていた。そういう人は「社会」では「バカ」と呼ばれたりもするけれど、私にとっては「理解できないほどの希望」そのものだった。
私はこのおじさんの影響もあってぶどうに興味を持つようになった。
山奥に来れば人との出会いが減ると思っていたが、その真逆で、毎日新しい出会いがあり、大学やその他様々な活動で「多量」の出会いがあった時よりも、多様で 「ゆたか」 な、ぬくもりを持った いのち との出会いが日々溢れている。
気が付いたら畑を貸してくれる八十歳の夫婦と出会い、ぶどう農家になっていた。畑は私一人でやっているのに、日々助け合いがあっていつだって「結」がある。畑からは大きな笑い声が響き渡り、時に泣きながら喧嘩をして、苦しい時はたくさん泣いて、それでも誰かに支えられて立ち上がって、とてつもない嬉し涙を流しながらぶどうの作業をする。
八十歳のおじいちゃんや親くらいのおじさんおばさんと、鍋をつついてカラオケを歌い、夜なべしてぶどうについて語らう。風呂で背中を流して、みんなが眠ったら食器を洗って全然眠る時間がなくても朝からまた新聞配達だ。
ここに来た人は小学生も中学生も高校生も大学生も社会人もおじいちゃんもおばあちゃんも、どんな肌の色だろうが、生まれ持ったものが何だろうが、とびっきりの笑顔で笑い、とびっきり泣いて、とびっきり生きて、帰っていく。
-物化するぶどう
おじさんの家でたらふくお昼ご飯をご馳走になって、ちょっとお手伝いをしてからまた自分の畑に戻る。ぶどう栽培の醍醐味だと言っても過言ではない「粒間引き」という作業に取り掛かる。ぶどうにはたくさんの粒があるのだが、その数を制限することで一粒一粒の大きさを大きくし、皆さんがご想像する粒の大きい「ぶどう」のカタチに整えていく。畑に剪定鋏の音が響き渡るのも、また格別な趣がある。
—– そういえば、ぶどうの作業をしていると、「ゾーン」と呼ばれるような状態に入ることが稀にある。どんどん「無」や「空」に近づいていき、気が付くとかなりの時間が経っている。
この「粒間引き」の作業は、二つの意識が溶け合っていく作業でもある。一つ目の意識は、「この粒を取れば、ここに空間ができて、この粒が大きく育ち、こんな形になるだろう」と、思い描く「ぶどう」のカタチをイメージし、作品を創り上げていくアーティスティックな意識である。一方二つ目の意識は、「下向きの粒を取る。上向きの粒を取る。」という単純な思考のみが存在し、そのぶどうの房環境の中で自ずから(おのずから)見えてくる最適なものを見つめ続けていくだけの、極めて「 民藝 」的な意識である。
この二つの意識(無意識)が一瞬一瞬で幾度となく交錯しながら、時に溶け合い融合していくのが、「粒間引き」という作業の真髄なのだ。
その時、私が触れている「ぶどう」は、天然物でありながらも、アートであり、 民藝 なのだ。その一粒一粒、一房一房から、 「全」 を感じられる瞬間がある。ぶどうが、 物化 をもたらす瞬間だ。
-ご近所とぬくもり
日が暮れてきたら、畑作業を辞めて、帰路につく。帰り際、山道で車にすれ違う度に会釈をする。ほとんどが知り合いなのだ。この辺りに住む人の多くは、家に鍵をかけない。自分の家で食べきれないほどの野菜やご飯があれば、ご近所にお裾分けするし、何かがなくて困っていたら、たいてい誰かが貸してくれる。
—– そういえば、このような人の結びつきを「ぬくもり」と称して憧れた時期があった。僕らの世代の特に都会で育った人の多くは、核家族化と 都市 化が定着してからの時代しか知らない。昭和の昔懐かしいドラマや映画を見るたびに、そこに描かれる世界に「ぬくもり」という名の大切なものを感じていた。
東京に住んでいるときは、隣人の名前も顔も知らず、関わることに「面倒臭さ」さえ感じて暮らしていた。通学するときはランドセルに防犯ブザーを付け、学校では「不審者に遭遇した時の心得」を教えられ、教員や保護者たちは「リスクを事前に察知し、対処することが肝要なのだ」と背中で子どもたちに教えていた。
こうした大人たちの過剰なまでの「安心・安全」志向は、やがて子どもたちに伝播し、近代を形作った概念を盲信するための補助装置の一つとして機能していく。
そんな環境の中で、幼い頃に感じていた「どうして諦めるのか」「どうして」「どうして」の先に見ていたのは、「社会」などとは比べようもないほど広大な世界と、そこへ至る「超越」の可能性そのものだったのではないだろうか。
我々は、どれほど 虚構 を生き続けてゆくのだろうか。「父性」と「ぬくもり」にはどのような関係があるのだろうか。この「ぬくもり」の正体は、一体何なんだろうか。
-混沌の中の誠実
夕飯の食器を片付け、外で自家製の紅茶を飲みながら、のんびりパソコンを触る。都会の片隅で「社会」に馴染めない中高生とお喋りをしたり、 日本 の未来インフラを考えてホワイトペーパーを書いたりしながら、薪で風呂を炊く。ふと空を見上げると、天の川が見える。見えなかったものが見える。聞こえなかったものが聞こえる。あまりにも仲間に包まれているような、そんな気がする。
—– そういえば、私がこれまでに見た中で、最も美しかった星空は、十八の時に行ったパキスタンで見たものだ。ヒマラヤ山脈のふもとにある断崖絶壁の細道を、現地ドライバーがとんでもない速さで走っている時に、死を覚悟しながら車窓から身を乗り出して見上げた星空は、まさに圧巻だった。
私がパキスタンを訪れたのは、現地の子どもたちとサッカーをするためだった。パキスタンは、手縫いのサッカーボール生産量が世界一で、たくさんの子どもたちが小さい頃からボールを縫うために働かされてきたとして大きな問題にもなっている。現地でサッカーをした子どもたちは、ボロボロの手製ボールを使い、ゴミが散乱する路上で楽しそうにプレーしていた。
私たちが何の気なしに使っていた真新しいサッカーボールは、ひょっとしたら、世界のどこかで誰かが必死に作ったボールだったのかもしれない。
ひょっとしたら、今日私たちが口にしている食べ物は、世界の反対側で誰かが一生懸命育てたものかもしれない。
直接的には関係なくても、世界の裏側の出来事が私たちの生活に繋がっているかもしれない。
もしかしたら、貴方が遊んでいたサッカーボールを作るために、世界の片隅で人が働き、その作業中に怪我をして仕事を失い、餓死したかもしれない。
貴方や私が認識できる世界で巻き起こっていることは、この世界の本当に小さな小さなごく一部のことでしかない。
貴方がクリスマスプレゼントで貰った新品のサッカーボールを縫ったパキスタンの子どもは、新品のボールを買うお金も無く、ボロボロの布切れを丸めて何度も修理して遊んでいるかもしれない。もしかしたら、その子は親もいないし、今日食べるご飯も無いかもしれない。学校も行ってないし、文字も書けないかもしれない。それでも、どんなにボールがボロボロでも、その子たちの方が、目を輝かせてサッカーを楽しんでいるかもしれない。
もしも世の中に、自分が知らなくても巻き起こっていることがたくさんあるのだとしたら、私たちは何も知らないのかもしれない。
今も昔も、私たちはこの世界のたくさんのものの影響を受けて生きている。様々なものがグローバル化して、身近なもの一つとってもその影響の範囲は広がり続けている。でも現実的に私たちも、そんな世界の様々な話に目を向けていたら、パンクしてしまう。
では、知らない間に自分の足が、美しく咲く一輪の花を踏んでいたとしても、自分に痛みをもたらすものには気がつかないように世界を閉じて生きていくしかないのだろうか。
さあ、「父性」が消滅した時代を生きる貴方へ。
「諦め」ずに、前に進むのなら、
今、トモに「父性」の話を、はじめよう。