
21.第五章「いのちと日本的父性」
『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –
目次
-ロマンあるもの
本稿を読んで、近代の産物が全面的に「否定」されていると感じる方がいるかもしれない。特に認識論層にいる方々はそうした捉え方をするしかないのではないだろうか。
「何が嗜みだ。こちとら本気でやっとんじゃ!」
と捉える方々が多発する可能性も十分にあるかと思う。
現実的に私たちのほぼすべての人が近代の産物としての「近代科学」を基にした教育を受け、近代の産物としての「社会」の一員としての感覚を持ち、その恩恵を受けて生活を営み、近代の産物としての 「幸福」 を追求している。本稿の描いているものたちは、そうした人にとっては「意味不明」なものである可能性が高い。その重要性についても理解はできるが、肌感としては全く分からないし、よく分からない薄い内容のものとして受け流されていくかもしれない。
例えば、「社会」という概念自体が 虚構 だと言われると、困惑する人も多いだろう。「社会」がなくなるってどういうこと?と思うかもしれないが、「社会」という概念が消えたからといって、現在「社会」という言葉で表されている 風景 がなくなるとは限らない。あくまでも メディア の更新なのである。そうした メディア の更新が行われるということは、「いいものをとって、いらないものはなくす」という新陳代謝が行われるということに過ぎない。
では、「『社会』という概念は一回どっちゃでもええもんとしてふわふわさせときましょう。」と言われて戸惑う方々に、こんな問いを提示したい。
「『日本的社会』という本を描くなら、あなたはどんな 風景 を描きますか?」
例えば、量子化の技術が突きつけた課題とも似ているが、「近代科学」を駆動してきたインセンティブそのものが揺らごうとしている今、科学者たちはどのような気持ちで研究を続ければいいのだろう。「社会のため」とか、「人類のため」といった大義名分を失ってしまうということは、元来の 日本 的な感覚に近付くことであると本稿ではポジティブに描いてきた。だが、先ほどのように近代の産物の中でのみ生きてきて、自己価値を見つけ出してきた人たちはそんなことを言われてもネガティブな気持ちや思考を持つだけで、戸惑ってしまう。そんな方々にはこんな問いを提示したい。
「『日本的科学』という本を描くなら、あなたはどんな 風景 を描きますか?」
こうした問いの提示と、それに向き合ってみる勇 氣 は、近代概念やそれに伴って生まれてきたあらゆる認識を「守破離」するためにとても重要なものである。5W1Hの疑問では到底表現しきれないような、「 風景 の描写」としての回答を生み出すには、 民藝 的な日々の営みとそれによって育まれる圧倒的な 手触り感 が必要なのだ。認識的な思考の先に描かれたものはあくまでも 虚構 でしかない。
そんな日々を実現しようとする人がもしも現れるとしたら、恐らくその多くは「ロマン」の探求にその生活の軸を根ざし始めるのではないだろうか。それはもしかしたらスポーツ選手になることかもしれないし、宇宙飛行士になることかもしれない。探検家かもしれないし、海洋学者、天文学者、小説家、映画監督、冒険家、醸造家、農家、アーティスト、シェフ、パイロット、考古学者、デザイナー、ジャーナリスト、ダンサー、マジシャン、アニメーター、などなどのあらゆる仕事が考えられるだろうし、もしくは「縁の下の力持ち」かもしれないし、「誰かを支えること」かもしれないし、「喧嘩を解決すること」かもしれないし、「病気を治すこと」かもしれないし、「とにかく何でもなくなること」かもしれないし、「人を愛すること」かもしれない。そう、この世界のどんな仕事も、どんな営みにも、そこに「ロマン」は存在している。
では一体ここで言う「ロマン」とは何なんだろうか。
私が先ほどの二つ目の質問に答えるとすれば、こう答えるだろう。
「 日本 的科学とは、非規定性ロマンだ。」
そこに「意味」なんて無いし、「意味」をつけて流布させたいとも思わないような、ただただ「ロマン」を感じるものに「本 氣 」をかけていくということだ。
「日本的父性」を土壌にした「ロマン」とは、何らかの未規定性の強いものに対して、「規定したい」というインセンティブ無しに、「これをこのまんまに味わいたい」という直感的・ 直覚 的なインセンティブによって根源的な興味や好奇心、「 氣 」が湧いてくるもののことなのである。
その探求の際には数多の認識が必要になるかもしれないが、それはあくまでも嗜めるツールや メディア でしかないのだ。そのような認識に飲み込まれないことが、日本的科学の特異な点なのだ。
この「ロマン」という 風景 と同じような高鳴りを表していた古い 日本 のものとしては「物の哀れ」「侘び寂び」「幽玄」などなどがあり、こうしたものは無数に発掘することができるだろう。
そしてちなみにもしも私が一つ目の「社会」の代替案に関する質問に答えるとしたらこう答えるだろう。
「日本的社会とは、雲である。」
この回答についてはここで解説はしないが、先ほどの問いに「本 氣 」で自分の人生の時間を懸けて向き合ってきた者たちとは言わずもがなその 風景 を共有できるかもしれない。
このようにして近代概念の守破離は不可能ではないし、こうした 手触り感 のある探索を現実的なインフラとして生み出す方法を構想し、実装していくこともできるのではないだろうか。
こうした営みは いのち に根ざして生きるものたちにとっては「ロマン」の探求の片手間として執り行う「嗜み」である可能性が高い。もしもそこに「 意志 」が宿れば、それはもう「嗜み」のレベルでは語りきれない勇敢な「使命」になっていくのはないだろうか。そうした「使命」は本当に時代を動かす力になり得るかもしれない。
現代 日本 において、幼少期や少年少女の頃に感じていた根源的なワクワクやドキドキをいつからか感じられなくなったと謳う大人はとても多い。認識の解像感を 向上 させ、意味や目的を持てば持つほど、こうした根源的な興味や好奇心を失くしていく。
それは本稿で言うところの、分厚い「認識スクリーン」に囲まれるようになったせいで、本来の 「生の原動力」 から離れ、根源的な いのち の 悦び に触れられなくなり、「 人間 」としての「 喜び 」のパラメーターを満たしていくことしかできなくなっていく流れを象徴的に表しているとも言える。
こうして「 人間 」として 「豊か」 になればなるほど、「 いきもの 」として 「ゆたか」 でなくなっていく私たち 日本 人が、「超越」「許し」「大丈夫」に希望を見出し、 いのち に根ざして生きることに少しでも関心を持つことは、遥かなる「希望」そのものなのである。
本稿に描かれている 風景 を「素読」的に反芻し、「希望」を宿した者はこんな認識的な文章は燃やしてしまうだろう。そうして「日本的父性」への畏敬や憧憬の念を回復させた末に、一人一人が「どう生きるか」を模索し、その中から非認識的な根源的なワクワクやドキドキ、ロマンに根ざして生活できるようになれば、もうそれ以上のことはない。
それが難しかったとしても、誰かがそのように生きていけるように、 いのち を隠していく近代的なものとの接続を代替する取り組みや、近代的なもの自体を輝化させていく取り組みに 意志 を持って向き合うようになる人が増えれば、きっと、この国の風通しは想像できなかったほどに良くなっていく。
非認識的な根源的なワクワクやドキドキ、ロマンとは、数字や具体的な言葉で表すものではないし、 直覚 する「何か」でしかない。なんとなくであるのに、あまりにも確かなものなのだ。それでいいのだ。そして、もし、それを自分自身が感じられなかったとしても、できることはいくらでもあるのだ。
Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today…
-John Lennon『Imagine』
-いのちあるもの
「日本的父性」があった頃の 日本 で、死ぬことよりも怖いこととはなんだったのだろうか。
「やめておけ お前らにゃおれは殺せねェよ 人はいつ死ぬと思う? 心臓を銃で撃ち抜かれた時 違う 不治の病に侵された時 違う 猛毒のキノコのスープを飲んだ時 違う! 人に忘れられた時さ」
これは『ONE PIECE』の冬島編で出てくるセリフである。このセリフが「正しいか」「正しくないか」なんてどうでもいいが、このセリフから感じ取れることはどれほどあるだろうか。
本稿では「 生命 」と「 いのち 」という言葉を全く別の 風景 として使ってきた。
認識世界に閉じこもった人々にとっては「忘れる」ということが「安心」と「安全」を担保するための非常装置と化している。「忘れる」ことが「良い」とか「悪い」とかそんなことはどうでもいいが、本稿ではこのように認識に囲まれてしまうことによって「知らぬ間に」誰かの いのち に深い深い鋭利なものを突き刺して抉り貫いてしまう恐ろしさについて、はじめの問題意識として描いてきた。
例え「 生命 」を奪わなかったとしても、そのような いのち に不誠実な行いは、当たり前のように「 生命 」を奪う力も持ち合わせ、それよりかもっと恐ろしい「 いきもの の可能性」を奪い取ることに繋がるという話をしてきた。
もちろん私は決して「 生命 」を蔑ろにして治安の悪い「安心」のない環境を作り出そうと言っているわけではない。大量の血を流して時代を変えようと訴えているわけでもない。近代を通して我々が学んできたことを決して捨て去る必要は無い。それらの中から大切なものをつまみ取って昇華させていけばいいのだ。
特にこの島国において、弱きものや苦しむもの、痛むもの、たよりないものに手を伸ばそうと思うのならば、「諦め」を捨てて守破離を続けていく生き様が「 いのち への誠実性」に繋がるということを、ここで何度でも確認したい。
私は小さな頃から、認識論層の人々が 同情 や 共感 によって誰かの「救い」となり、時間が経って認識の変化を理由に放り出して、人を「死」に追いやるという流れを何度も何度も見てきた。「父性」に関心のない認識論層の人々は、「母性」や自分自身の欲求に基づいて、後先のことを考えずに他者に手を差し伸べがちだ。例えば価値観に変化が起きるなど、彼らの認識に変化が生まれた途端、差し伸べた手や、その時に投げかけた言葉、行動などをその時とは違う認識でしか捉えられなくなる。そして、以前の行いによって「救われた」誰かの気持ちは、もはや煩わしいものになってくる。それを追求されると、「ごめんなさい。もう違うの。」という謎の言葉しか伝えられなくなる。
そうした不誠実な「救い」によって傷つき、傷んだ者たちは、自殺を図ったり、次の「意味(救い)」を求めて彷徨ったり、「忘れる」という認識技術を 向上 させて切り替えたりするようになる。それを繰り返した彼らは、気がついた時には加害者側に回っている。こうした苦しみの連鎖を根本的に断ち切る可能性を持つのは「日本的父性」なのだと、今ここでもう一度伝えたい。何度だって伝えたい。
差し伸べた手が誰かの心をかち割ったとしても、見て見ぬふりをしてその人が視界から消えるか自分の都合のいい存在になるのを願い、知らぬ間にその時に負った手の怪我が悪化し、自分の手が機能不全になって「ぬくもり」を失っていても全く気が付かない。手を見ても、ちゃんと自分の綺麗な手が見えている。見えないのになんか痛い。見えているのに、なんだか見える 景色 が減った気がする。手に刺さりっぱなしの破片を誰かの胸に何度も何度も突き刺しても、その手は「優しい」「自然」や「愛」にしか感じない。誰かがそれで喜んでくれたらもうそれで 満足 である。都合の悪いことは感じない。もう、痛くもない。何も痛くなくなった。世界のどこかで誰かがその破片を浴びて大怪我をしていても、何も気が付かない。実際がどうかなんてどうだっていい。金継ぎされなかった破片たちは、不発弾のように認識の外側へ放たれ、その尖った先端でこれからも誰かの胸を切り裂いて抉り続けていくだろう。
それでも「諦め」てはならない。「諦め」ないで。
「諦め」など存在しなくていい。
「諦め」は嗜むものでいい。
溶かして、抱きしめて、輝化する可能性は、誰からも、どこからも消えはしない。
「諦め」無き「 意志 」やそれを伝える背中は、どこにありますか。どこにありますか。
「 氣 」が減退した母性社会を生きる僕らはみんなそれぞれたよりないものたちだ。 いきもの は簡単に死んでしまう。僕らはたよりないものたちに「大丈夫」を、認識を飛び越えて伝えねばならない。「 氣 」をいただいて、「 氣 」を返して生きていかなきゃならない。
この停滞した 日本 も、「息苦しい」「社会」も、それをしようとする「 意志 」が多くの人に生まれないと、何も変わりはしない。
「大丈夫」を誰かに伝えたいのなら、まずは自分が生き様を変えなきゃならない。痛みや苦しみから逃亡することに注意深くあらねばならない。自動化されているのなら、痛みや苦しみからどうしたって目を逸らせない環境に自分自身が行かなきゃならない。
自分が「満たされる」ことに注意深くあらねばならない。自分が満たされてニヤニヤしていることに、震えるほど吐き気を感じるところまで一度いかなきゃならない。それでも大地を踏み締めて、立たなきゃならない。
「日本的父性」は、 いのち に根差した誠実性を伴う。
いのち に根差した誠実性は、自分の認識が破壊されることを恐れたりしない「 意志 」にある。
いのち に根差した誠実性は、差し伸べた手を、無かったことになど絶対にしないという「 意志 」にある。それを後で認識に囚われて小細工しないという「 意志 」にある。
-いのちと日本的父性
認識を遥かに飛び越えるもの、それが いのち である。認識では太刀打ちできないもの、それが いのち である。
貴方が、 いのち に溶けた時、円錐の壁は一瞬で輝化する。円錐の外側での、奥行きのあるすべての手触りは、あらゆる認識を「超越」していく可能性を持っている。
「日本的父性」における「許し」は、「何か悪いことをされてそれを許す」というような平面の薄くて浅い話ではない。「日本的父性」における「許し」は、 いのち の直感的「 意志 」であり、風のような結果物である。 いのち に根差していれば、根源的な「許し」を育むことができる。
永遠に広がることが可能な「 意志 」的な「器」は、「許し」に限界を作らない。例え怒りを永続的に発生させる認識スクリーンに夢中になってしまったとしても、「融解・抱擁・輝化」させる器があればいい。それは「行って 会って やって 話す」ことだったり、 民藝 的な「美」の「 直覚 」の回復や、大地に根ざすこと、誰かや何かを「大切」にすること、「親切」にすること、そうしたことが育む結晶なのである。
移ろいゆくものや、変わってゆくものが、ただそうであり続けられるのは、風がもたらす「父性」の賜物である。変わってゆくことを「諦め」てはならない。だが、変わろうとして変われることなんてほとんど無い。それでも自ずから(おのずから)変わる可能性のある環境に行くことは、 意志 を持ってできることなのだ。
そして、貴方が「日本的父性」を宿せば、誰かもまた変わってゆくことができる。「諦め」無くても「大丈夫」になる。それは、「安心安全」のもっとその先にある、「ぬくもり」のある希望なのだ。
いのち に根差した世界、そのまんまの世界においては、「日本的父性」が常に共にある。「日本的父性」への畏敬の念や憧憬が心のどこかに必ずある。優劣や順位なんてつけなくていいし、そんな認識は遥かにどうでもよくなる。
貴方は、大切な人を、なんの躊躇いもなく抱きしめられるようになる。
誰かと向き合うとき、理解なんてしなくてもそのまんまの相手に触れられるようになる。
満たされる感覚なんて絶対にないほど、「 悦び 」だって苦しみだって遥か永遠に広がっていく。
あまりにも風通しよく、その先にはほんとうの「大丈夫」が広がっていく。
それだけで貴方の いのち は輝き出す。躁も鬱も、どんな認識も全て輝化する。
これまで感じていた「 喜び 」があまりにもちっぽけに感じるほど、すべての感情や感覚は遥か永遠に遠くまで輝いて広がって澄み溶けていく。
気がついた時には、もう二度と元に戻らなくていいという確かな 直覚 と共に、貴方は記憶のあるうちではきっと「はじめて」と言えるほどに「息がしやすく」なっている。遥か遠くまで広がる世界に、「ぬくもり」と共に触れることができるようになっていることだろう。
何度も言うが、 「生の原動力」 がどこにあるのかは人それぞれ違う。 日本 人だからみんな「どう生きるか」にあるとも限らないし、生まれつき「この世界をどう認識するか」で「 生の悦び 」を感じられる人だっているはずだし、もしくはもっとそれ以外の 「生の原動力」 を持っている人だっているかもしれない。自分自身の 「生の原動力」 が何なのかを認識することは誰にもできない。そのため いのち に根差すためにはこうしたものを 直覚 する他ない。
こうした 直覚 は意識と無意識の あわい の中にあり、本稿で見てきたようにそれは環境によってもたらされる可能性が非常に高いものでもある。
そのため、自分の いのち や相手の いのち に誠実に向き合いたいのなら、「 日本 人ならばこうであるはずだ」などといった認識は全て気化させて、できる限りのことをしなければならない。そのヒントを本稿の隅々に散りばめて描いてきた。
本稿でわざわざ認識的な「言葉」というツールを用いて「父性」や「日本的父性」の概念を整理したのは、人々にそれを意識して 発揮 してもらいたいからではなく、素読を繰り返すことで 手触り感 を手繰り寄せ、その重要性を 直覚 し、意識的か無意識的かに関わらず、「父性」や「日本的父性」の 風景 を一度心に描いてみてほしかったからである。
「日本的父性」が自ずから(おのずから)人々の心にあった時代では、人々はそれに対して非認識的に、非意識的に畏敬や憧憬の念を抱いていたのではないだろうか。一方で、「父性」も「日本的父性」も人々の心から消滅した今のこの時代では、まずはこのように認識的にでも描き出す必要があり、それに触れてまずはそこはかとない希望の念を心に 直覚 することが重要なのである。そして、本稿で描いてきたことを素読的に繰り返すことによってようやく「父性」や「日本的父性」が心に宿り、タイミングが来た時、「父性」を自ら(みずから) 発揮 したり、「日本的父性」が自ずから(おのずから) 発露 したりするようになるのだ。
それ故に本稿は前時代的な「日本的父性」の源泉にあったものを描き出し、今、そしてこれから生きていく一人一人が、 いのち に根ざして生きていく可能性を探ったものである。近代以前にあった「何か」を近代的な流れや認識技術を駆使することによって、「いらんもんは削り、新しいものも取り入れて、いいものを受け継ぐ」 脱構築 をした 風景 そのものなのである。
だからこそ、ここで描いてきた「日本的父性」は、「 意志 」から始めることができる。たとえ貴方が、生きている間に「日本的父性」に行き着くことはなかったとしても、貴方がもがいた「 意志 」は、次の世代の「日本的父性」の萌芽を支える養分となるはずだ。植物は、あらゆる「 生 」と「死」から恩恵を受けて、ようやく芽を出す。貴方の「 意志 」は、たとえ貴方が死んでも、いつかどこかで何かが発芽するための養分になる。
少しずつでいい、自分を取り囲む近代概念を溶かしていこう。
少しずつでいい、これまでの人生でしてきた「諦め」に戻って、「行って 会って やって 話す」ところから始めよう。
日々の全てに 手触り感 を取り戻していこう。
自分に不誠実さが現れてしまったら、素直になろう。
どんな可能性も、「諦め」ることなく、認識の外側を求めて、生まれたばかりの赤ん坊のように、とにかく素直で、ありのまんまであろう。
もしも自然派層まで行って、体現に至らずとも「日本的父性」を少しでも感じとれるようになったのなら、「日本的父性」を育む環境を子どもたちにもたらしてあげてほしい。そして、本稿で描いてきた前提を大地にして、その上にたくさんの草花木を咲かせてほしい。
たとえ自分自身がもう認識の外側の 悦び を感じられなかったとしても、自分自身が誰かの いのち の灯そのものにはなれなかったとしても、自分の子どもや、周りにいる人など、誰かの「希望」であれる人や、誰かが「希望」の灯を感じる可能性を守ることはできる。
どんな仕事をしていたとしても、どんな取り組みをしていたとしても、欲望や認識に支配されたり取り憑かれたりすることなく、懸命に自分が感じる気体性のロマンを探求していくことができれば、貴方は誰かに「元 氣 」や「勇 氣 」といった「 氣 」を与え、「希望を守る」という生き様を体現することができるはずだ。
我々は、まだ本稿で描いてきたような近代の守破離の上に、 日本 独自の何かを作れていない。「社会」を打破し、 日本 的な新たな仕組みをたくさん妄想してほしい。 日本 的な「科学」の「 悦び 」を得られる仕組みを妄想してほしい。そんな仕組みや仕組みの外側で必要となる 日本 的な「教育」の仕組みを妄想してほしい。認識をふわふわにする道具をたくさん生み出してほしい。
あらゆる概念の 脱構築 を乗り越え、大地に根差した新たな妄想を、まだ認識世界にズブズブに入る前の若者たちが思いっきりできる環境を作ってあげてほしい。
我々は無限の可能性を秘めている。単純な回帰ではなく、デジタルネイチャーな未来に、もっと面白い、もっと想像もできない世界線を作ることができるはずだ。「社会」に溢れるあらゆるゲームを超越して、いくらでも、なんでも作れるはずなのだ。
たくさんの失敗を抱きしめて、輝化させる姿を体現して若者に見せてあげてほしい。「父性」を 発揮 して許し、彼らが いのち を生きて「大丈夫」な環境を、この世界の片隅に作ってあげてほしい。
ひとりぼっちの子どもがいるんなら、抱きしめてやってほしい。
せめて自分自身や、自分の子ども、家族の「大丈夫」を生死を超えて守ってほしい。
大丈夫なんだと、言える人に、言わなくても伝えられる生き様の人になってほしい。
なりたいんだ、なるんだと、大地に触れて感じてほしい。
全ては、「父性」から始まるんだ。だが、始まっただけでは恐ろしいだけだ。後で有耶無耶にしてしまえばいい。そんな恐ろしいことが起こらないように、その先へ繋いでいくためには、「日本的父性」が必要だ。体現はできずとも、「日本的父性」への希望の念だけでも感じて抱いてほしい。
「灯(ともしび)」とは、 いのち の光である。
いのち に根ざすこと、それが「異常」である今のこの時代に、「日本的父性」をまとめたこの原稿の描く 風景 が、儚い儚い灯となって、まだ揺らげる者たちに届くことを祈っている。
これは絶望の 日本 への、最後の「灯」だ。
日本 への「諦め」を輝化させるシンプルな「灯」だ。
貴方の閉ざされて満たされた心のもっと外側に広がる、 いのち に届けたい、私の いのち を懸けた「灯」だ。
私は自分の「日本的父性」をもってして、ここにこれを遺し、灯台の灯りを焚く。
私はこれを、私の大切な人に届くことを祈って、そこに私の「日本的父性」を懸けたい。
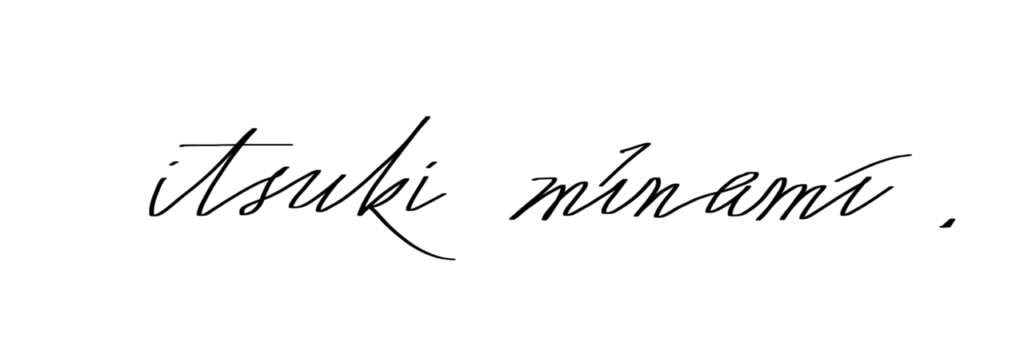
(「おわりに」へ)