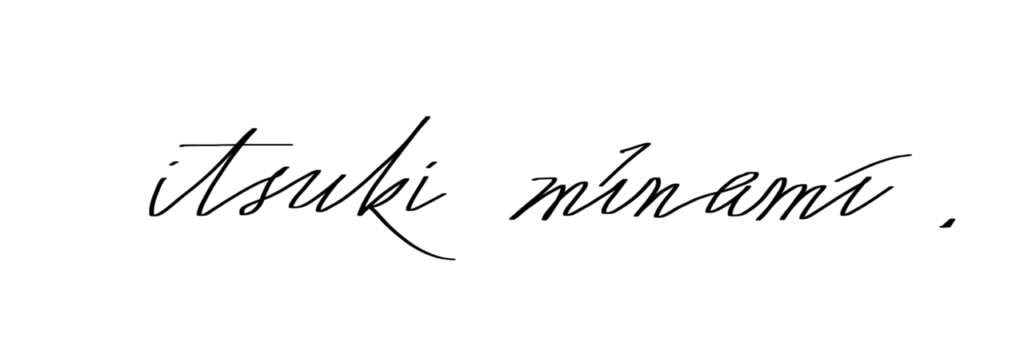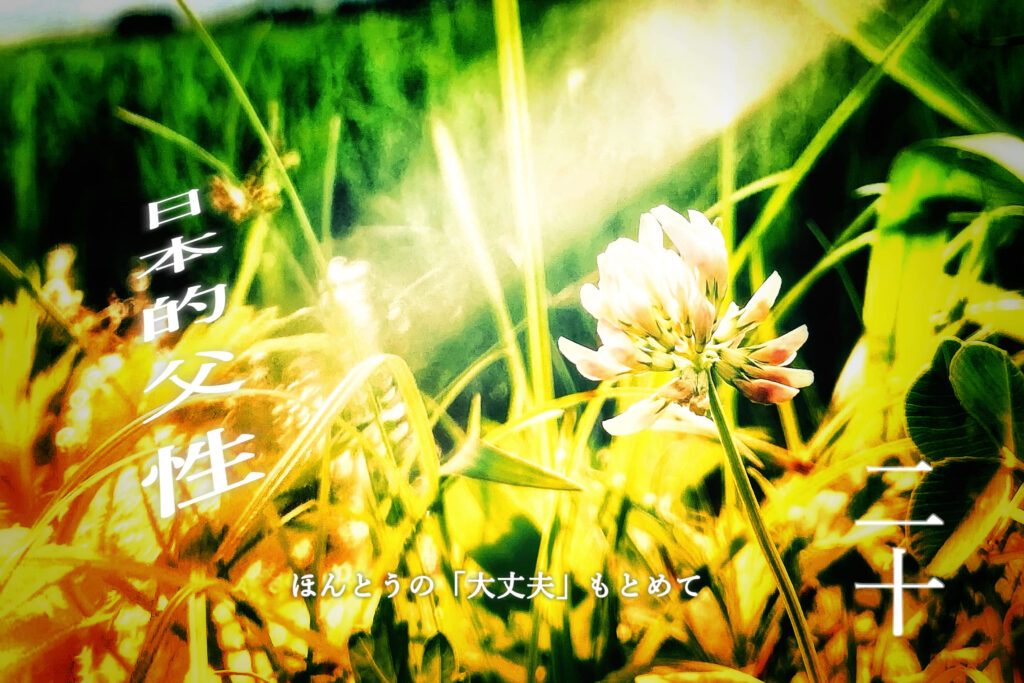
20.第五章「いのちと日本的父性」
『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –
目次
-物化する民藝
守破離の「守」に重要な価値を見出した「 民藝 」という概念について少し紹介したい。
民藝 運動は、1925年頃、思想家の柳宗悦、陶芸家の河井寛次郎、浜田庄司らによって始められた。この運動は、大量生産と工業化が進む中で失われつつあった手作りの工芸品や伝統的な技術を評価し、保存しようとするものであった。
当時の工芸界は、華美な装飾が施された観賞用の作品が主流であったが、この運動の提唱者たちは、名も無き職人によって生み出された日常の生活道具には美があり、これらの工芸品が美術品に負けない美しさを持っていると主張した。
また、各地の風土から生まれ、生活に根ざした 民藝 には「健全な美」が宿っているとし、新しい「美の見方」や「美の価値観」を提示した。
この運動は、 日本 各地の「手仕事」の文化を保護し、近代化や 西洋 化の流れに警鐘を鳴らし、近代的な 「豊かさ」 だけでなく、より良い生活を追求することに主眼を戻すことを目指すものだった。
柳宗悦らが主張する「 民藝 の特性」によれば、 民藝 的なものは、何らかの実用性を持ち、特別な作家によってではなく、無名の職人によって制作された無銘性を持っていたり、民衆の要求に応えるために多数制作される複数性、そして誰もが購入できる程に価格が低い廉価性を持っていたりするものである。これらの作品は、繰り返しの激しい労働によって得られる熟練した技術、労働性を伴い、それぞれの地域の暮らしに根ざし、地方の色や形を 豊か に表現する地方性を持ち、また多くの量を制作するために複数の 人間 による共同作業、分業性が必要であることが多い。さらに、 民藝 は伝統という先人たちの技や知識の積み重ねによって守られる伝統性を持ち、個人の力よりも、風土や自然の恵み、そして伝統の力など、目に見えない大きな力によって支えられる他力性を有しているとされている。
「 人間 」が作り上げた認識が隠していったものに、もう一度立ち返るためには、「 民藝 」にあるように日々の生活の 手触り感 のあるところから、もっともっと多くを感じ取っていく必要がある。
「社会」でそれがどう評価されるかというよりも、手の届く範囲の大切な人たちの生活に根ざし、当たり前のことで意識を割いていなかったことでも、誰かの助けを借り、誰かと協力して、個人の力よりももっと大きなものの影響で育まれてきた伝統や、それによって生み出されてきた侘び寂びたものにそのまんま触って、抱きしめたくなるほどの愛おしさを感じるところから いきもの の「痛み」の感性は回復し、「 意志 」は醸成されていく。
本稿では( 別付:零章の「まえがき」 )から、たくさんの生活の機微に見出せる具体例が散りばめられて描かれている。その全てが、見えなくなった炎の光の揺らぎをキャッチするアンテナを育むために大切なものなのである。すーっと読み飛ばしてしまった些細な文章の背景にある日々の生活環境や風景の機微に根ざした話や、それを醸成してきたもっともっと「大いなるもの」が、きっと認識のもっとその前の感触を貴方に思い出させてくれるはずなのである。そして、そうしたものは、日々の生活の一つ一つの言動や意識から始まるものであって、その一つ一つはたとえ「 意思 」だけであったとしても変えていけることなのだ。
本稿のはじめに立てた「素読とは何か」という問いについても、この 民藝 性の可能性を見つめればよく分かってくるものでもある。「 氣 」の総量が減退し、「意味」や「目的」が無いと身体を動かせなくなってしまっている多くの現代人にとって、この「素読」的な特徴を持つ 民藝 への憧憬を回復することは非常に重要なことでもある。
「意味」や「目的」などの「認識」に囚われているうちは「 民藝 」的な行いを続けていくことが難しい。
「なんでこんなことやらなきゃいけないだろう」と思うような「素読」的な行為も、もしかするとそこには認識不可能な「何か」がたくさん眠っていることがあるかもしれない。
意味や目的を考えるという嗜みに飲み込まれる前に、そのような「認識」を度外視して、そのもっと外側に広がる大いなるものの中で、私たちは生きているということを、もう一度思い出させてもらってこそ、「 氣 」は回復していくのだ。
こうした 民藝 的な行いは、守破離における「守」の重要性を示すものでもある。
何十年も同じものを作り続けてきたかのように見える 民藝 的な職人たちの作業を観察すると、一つ一つの動作が最適化され、力の入れ方や身体の使い方、環境の整え方から意識の使い方に至るまで、奇跡的に生み出された「一回性」を持つ貴重なものであることが分かる。
彼らは全く同じことをしているように見えるが、実際にはその都度「一回性」を持つ 物化 する瞬間に立ち会っているのだ。
それは 民藝 的に物事を「守」り続けていくその先に生まれる可能性そのものなのである。
その瞬間瞬間に、栄誉や名誉などの承認欲求や近代概念のような 虚構 性の強い「意味」への埋没は存在しない。
これは、どこで、どのような暮らしをしている人でも実践できることなのだ。
合抱之木、生於毫末。九層之台、起於累土。千里之行、始於足下。
– 老子:徳経:守微第六十四
-美と直覚
日本 の伝統文化に金継ぎ(金繕い)というものがある。
金継ぎとは、割れて壊れた陶磁器を金や銀を用いて修復する 日本 独特の技術文化である。十五世紀の室町時代に生まれ、特に茶道の世界で大切にされてきた。破片を洗浄し乾燥させ、接着剤で結合し、欠けた部分に金粉や銀粉を塗る。金継ぎで修復された陶磁器は、その歴史や傷を隠すのではなく、美の一部として愛でる 日本 の伝統を感じさせる。
これは、「日本的父性」の源泉を感じさせるあまりにも重要な伝統文化の一つである。こうした文化がこの国には本当にたくさん眠っている。現代において何かの分野にカテゴライズされるものの中にも、それらを横断的に跨ぐものの中にも、カテゴライズされ得ないものでも、この国に根付いてきたあらゆる「一」を 民藝 的に探求したり、「守破離」を続けていくと、そこには「超越」「許し」「大丈夫」を日本的自然観に根ざしたカタチで前提としたり生み出したりしている瞬きを必ずと言っていいほど感じ取ることができるだろう。
また、こうしたものに可能な限り非認識的に、無意味的に向き合い続けることは、私たちの「美」や「 直覚 」そのものを回復・洗練させる力を持っている。「日本的父性」とは、洗練された「美」への「 直覚 」そのものであるとも言える。それは「生き様の美学」と言うこともできるかもしれない。
この「美」への「 直覚 」は、言語化され得ない「違和感」を感じる力のことだとも言える。
民藝 的な職人やおばあちゃんたちは、大地に根ざして育まれてきた「言葉にはできないけどなんか違う」という感覚を多く持っている。こうした感覚を感じ取ることこそが 民藝 の修行における「守」であるとも言える。それは認識的には非合理的で理解し難いことかもしれないし、「絶対におかしい」としか思えないことかもしれない。それでも、そんな薄い認識という名の武器で職人やおばあちゃんに対抗しても、それは自分自身がそういったストレスから解放されるという結果しかもたらさない。彼らはキラキラした言葉や、ドキドキする言葉では何も語らないかもしれないが、私たちはそういった人たちと共にいることこそが「 直覚 」の回復をもたらす可能性を持つのだということについて、もっと自分ごととして捉えなければいけない。
このように「 直覚 」をほんの少しずつでも回復・洗練させていこうとする精神性は、認識のレイアウトの 透過度 を下げたり、気がついた時には認識レイアウトのカタチそのものを変化させる力をも持ち合わせているかもしれないのだ。
この島国の片隅に眠っている「美」のカケラを探しにいこう。
日々の生活の中で「 直覚 」することはありますか?
データからもたらされる統計学的な信号である「直感」ではなく、極めて神秘的な現象である「 直覚 」のことである。
この島国の片隅にある「美」に想いを馳せ、「守破離」へと進んでいこう。その先にはきっと、ゆっくりゆっくりと、貴方の周りにあった固体化されていたものたちが輝化して、「 氣 」が巡るようになっていく未来が待っていることだろう。
-ふわふわしたもの
このように、生活する環境(場所・人・モノなど)を変えること、「守破離」をすること、「 民藝 」的であること、「美」の「 直覚 」を回復し洗練していくこと、認識世界から外側の世界を感じていくために日々の生活からできることは山ほどある。
そうした鍛錬を積み重ねていれば、これまでに経験したことのない「痛み」や「苦しみ」に何度も襲われるかもしれない。
その時には「風のように生き、風のように死ぬ」ところにある「灯」を握りしめるように心に宿してほしい。
そうした「痛み」や「苦しみ」と向き合わなければいけない時には、あまりにも多量の「 氣 」を出力してしまい、「もうだめだ」と思う時が来るかもしれない。
「行って 会って やって 話す」を繰り返しても結局何も見えなければ、きっと貴方はその時には何かしらの「 直覚 」に辿り着いているはずである。
こうした忍耐を要する鍛錬を積み重ねていると、気が付かないくらいゆっくりとしたスピードで、あらゆる固体として認識していたものがふわふわして可愛い存在に変化しているだろう。
そこまで行った先では、きっと、共にふわふわしたものを構想する仲間を探したいと思う人も現れるだろう。きっとその時には、これまでに思いもつかなかったゲームの外側に無限に広がる可能性を具現化することも嗜めるようになっているはずである。
第四章の最後で私はこんな問いを提示した。
「あるいは寧ろもうこの段階で、人々が近代概念を『どっちゃでもええ』と思えるようになる環境が育まれ始めるように、我々が動くことはできないのだろうか。」
私たちは、量子化(EndtoEnd)の技術が実装される時がまだずいぶん先になるとしても、今からでもそれを前提にしたインフラや制度が醸成されるきっかけくらいは生み出すことができるのではないだろうか。
デジタルネイチャーの流れの中で、ソフトウェアやハードウェア両面で「 人間 人間 しい」認識的なものを任せられる生活の道具を作り出せるかもしれないし、新たな概念を構想し、近代概念に囚われない人々が増える流れを生み出せるかもしれない。
私たちにできることは無限にある。
この世界をもっとふわふわにして、「みずから」と「おのずから」が互いに影響しあって相即的に進んでいくような流れが生まれるきっかけを模索しようじゃないか。
もしも万が一、この世界のどこかで今も大地に根ざして風のように生きられている人がいるのだとしても、或いは本稿を真に受けてそうした生活に辿り着く者がいたとしても、現状ではその邪魔をするのは「社会」との接続時である。
制度的なものや法的なもの、資金調達やら書類やら許可やら契約やら何やらを自ら行わなければいけない時、脳みそを異常に近代認識的にしてしまう。
それを繰り返し続けると結局認識スクリーンは分厚くなり、認識レイアウトは球体に近づいていく。
だからこそ、そうした「社会」的な仕組みとの接続を減らすインフラや制度、代わりに接続を行ってくれる生活に根ざした道具を作れば、デジタルネイチャーが発達していく過渡期でも、認識的なものをAIやなにかに任せて、人は元来の日本的自然観に根ざした生き方をしていくということが可能になるかもしれない。
そして、そうしたふわふわに馴染み、熟成されて来ると、幾ばくかの人は知らぬ間に「日本的父性」が 発露 する力を持つようになっているだろう。
そのような「日本的父性」を宿した者たちが、今からほんの数人でも育っていけば、技術的特異点が到来した時に、時代を大きく転換させられるかもしれない。
「生」も「死」も超えた「 意志 」を持ち、何かを背負って生きてそして死んでいける者たちがいれば、きっとその時は訪れるだろう。
そして、彼らが 手触り感 のあるところに根ざして生きていれば、そこには「ぬくもり」が灯っているだろう。
「社会」が変わるとか「時代」が変わるとか「国」が変わるとか、そんなことは偶然と認識の産物でしかないので、大切なのは貴方の手の届く範囲でこの世界の片隅に「ぬくもり」が生まれること、それそのものなのである。
I’m not afraid to die.
Because I know you’ll be there.
With you, I’ll be complete Part of this all
Become everything and nothing
I know I’ll be fine
So fly, fly away and be free
I know I’ll be fine
So shine brighter than ever
-haruka nakamura『八星』
(つづく)