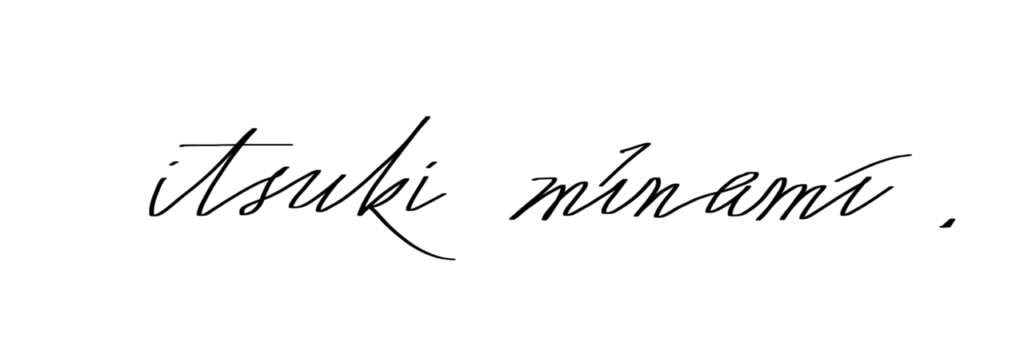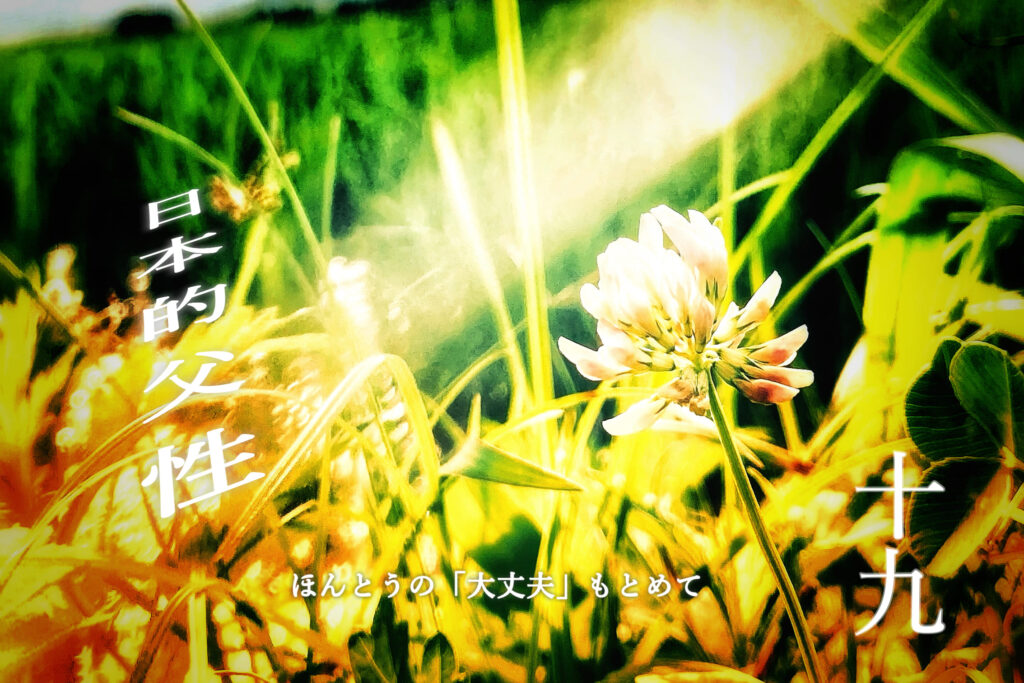
19.第五章「いのちと日本的父性」
『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –
さて、近代概念が不要になるほどのデジタルネイチャーが発酵したその先で、自ずから(おのずから)生まれている新たな概念( 風景 )はどのようなものなのだろうか。
発酵したデジタルネイチャーの「気体性アニミズム」が広がる世界線では、 風景 そのものとして 「ある」 状態で、言語化される必要性がなくなっている可能性も大いにあるため、それが言語的に表されているのかどうかは甚だ怪しい。
一方で、現実的に今、我々がこの流れを変容させる可能性を持つ儚い希望を灯すのだとしたら、何ができるのだろうか。
あなたの一度きりの人生を、あなたの子ども、そのまた子どもたちの いのち の可能性を見て見ぬふりしないのだとしたら、私たちはどうしたらいいだろうか。
認識世界に閉じた人々が大半の現代 日本 では、言語化した概念を生み出すことも重要かもしれないし、言語化せずとも生まれる 風景 を育むためのインフラや流れなどを生み出していくことはできるかもしれない。もしくはそうしたものそのものが生まれるための環境を身の回りから育むことは不可能ではないかもしれない。
それよりかもっとその前に、生き様を見つめ直すところから、私たちは始めなければいけないのではないだろうか。
最終章は、「諦め」の延長に立たずに、 「全」 を生きる可能性へと進んでいきたいと思う。
目次
-「諦め」無い
さあ、認識スクリーンに囲われて選択肢の 沼 に嵌った人々が、「日本的父性」の 風景 に触れていくために、その可能性を探索していくために、まず、とても重要なことがある。それは「諦め」という概念を蒸発させるという作業だ。
「人生は選択の連続だ。」
という、選択肢の 沼 では、常に「諦め」という概念が表裏一体的に存在している。「選択したもの」があるということは、「選択されなかったもの」があるということでもあり、それは、何かを「諦め」るということでもある( 「図1:西洋的認識世界」 )。
「選択」の 沼 が近代の産物であることからも分かるように、我々が現在使う「諦め」という言葉の意味合いは、明治維新以前の 日本 には存在しなかった。
もともと同じ音の言葉では「明らむ」があり、これは昔の「諦」の漢字が表していた意味合いと同じく、「明らかにする。はっきりさせる。」「晴れ晴れとさせる。心を明るくさせる。」というような 風景 を描くときに使われる言葉であった。これが、大正から昭和初期にかけて、「思い切って何かを引き算することで明らかになるものがある」という意味合いが転じて現代的な意味合いに変化して語られることが増えたと考えられている。
そもそも我々が現在使っている「諦め」という概念は、我々 人間 が作り出した認識に伴って生まれてきた概念でしかない。つまり近代以後の「社会」を成り立たせるために要請されて生まれた概念でしかなく、この概念は本来この国では必要とされなかったのだ。
そもそも我々の いのち に「諦め」などという概念は必要ではないし、存在しない。何も「諦め」る必要などないし、そもそも現代的な「諦め」という概念の存在さえ自覚せずとも我々は 「ゆたか」 に生きていけるはずなのである。
平面に並んだ選択肢を選んでいくこともなく、 「全」 に触れて生きていた者たちは、「矛盾」などあって当然のものであり、彼らにとって「何かを選択していく」ということは、遥か遠くまで様々なものを貫いて一筋の線が伸びてゆくイメージに近かったのではないだろうか( 「図8:日本的認識観」 )。
勿論その中途で様々なものを貫いていくので、当たり前のように矛盾は生まれているし、 だがそれは矛盾 などではないのである。
こうした一つの選択が 「全」 へと繋がってゆくことが、元来の「明らむ」の 風景 であったと捉えると、我々は遥か永遠に可能性に満ち満ちているのだということを思い出させてくれはしないだろうか。
平面に並ぶ二つの選択肢が「選択したもの」と「諦めたもの」になるのは認識世界の話であり、元来の 日本 人は、 歩み を進める際、世界に一筋の線を通し、その途中に「選択されたもの」と「選択されなかったもの」があるだけで、両方が一筋の線で貫かれているのだ。
これは時代とともに認識レイアウトが変化して触れられるものが平面になったという証でもあり、こうした感覚を取り戻してまだ見ぬ 「ゆたかさ」 を「諦め」たくないのならば、まずは過去の事象や日常生活に溢れているであろう「諦め」に注意深くあるところから始めなければならない。
あの「選択」は、何かを「諦め」て前に進んだつもりになっていただけで、本当は見たくないものを隠して、満足したかっただけなんじゃないかと、省みてみるところから始めなきゃならない。
私たちは、「諦め」無き世界をもう一度生きることはできないのだろうか。
「奇跡は諦めない奴の頭上にしか降りて来ない。
奇跡ナメんじゃないよ。」
– エンポリオ・イワンコフ『ONE PIECE』
-認識世界からの飄逸
現在、円錐(認識世界)の中で生きている人が外側に出るのは、ほぼ不可能に近いと言えるだろう。いくつか可能性はあるのかもしれないが、それは体験したくてできるようなものではなく、奇跡的なご縁がないとできないため、望んだり願ったりするものでもないと考えられる。意識していようがしていまいが、体験する人はするし、しない人はしない。
何度も描いているように、認識スクリーンがどのようにレイアウトされるかについては、どのような自然環境の中で、どのような環境要因(制度等)や構成要素(概念等)に囲まれて生きているかが大きな影響を与える。つまり、認識レイアウトを変化させたいのなら、それ相応の環境に移り、それ相応の生活を探索していかなければいけない。そこまでしても、自ずから変化の時が訪れるかどうかは、誰にも分からないのである。
だが、一つだけ言えることは、守破離を忘れることなく、「諦め」をとにかく捨て続けていける人は、その可能性も大きくなるということだ。あるいはここまでを読み、その 風景 を心に宿したり、最悪「認識」しているだけでも、いつかその瞬きが訪れた時に、また何かに「自然洗脳」されてしまわずに「 いきもの の 悦び 」を掴んでいける可能性も高くなるのではないだろうか。
そして、たとえどんなに頑張っても自分自身は無理だとして、それでも、そうした生き様を見せ続けることは次の世代に可能性を残すことに確実に繋がるはずだ。
認識論層を長らく生きてきた人は、「守破離」がとても苦手な人が多い。「諦め」を捨て、守破離を続ける生き様を体現することは、とてつもない痛みや苦しみ、虚無感を生む。
単純に満たされた感覚を感じられていたのに、その裏に黒いものが見えてしまうようになる。そうなると人生に「つまらなさ」を感じ、何事も嘘くさくなってくる。
それでも、「諦め」を捨て続け、守破離をし続けると、大半の場合いつかニヒリズム層に突入する。そこまでいくと「死」に直面することになる。それで死んでしまう人も多いが、もしもそれで、先に記述したような環境の変化を起こして自然派層に行けて、それでもその生き様をし続けられたなら、次の世代の可能性を少しでも守れるかもしれない。
もしも子どもたちの いきもの としての可能性をできる限り潰したくないと願うのならば、「諦め」をとことん捨て、住む場所を変え、関わる人を変え、常日頃から足し算よりも引き算にフォーカスしていかねばならないだろう。 いきもの としての「誠実性」を「生」も「死」も飛び越えて大切にし、自分の感情や感覚を満たすようなものから距離を取り、仁義を持って関係を断ち、 西洋 の 「生の原動力」 を元に作られた近代概念から脱して、そうしたものが極力無い環境で生活を始めなければいけない。
だが、そもそも自分が「今、どこにいるのか」に気がつくことが難しい。認識論層からニヒリズム層を経て自然派層に移った時も、ただならぬ 「ゆたかさ」 を感じることができるが、円錐の中から外に出た時にはこれまでに味わったことのない遥かなる 「ゆたかさ」 を初めて味わうことができる。逆に、円錐の外側から中に入ったり、自然派層から認識論層に入ったりしても、 「ゆたかさ」 が失われたことに気が付くことはない。また、円錐の外側に初めからいる人や、外側にいて長い時間が経つ人も、 「ゆたかさ」 に馴染んでいるためにそれを特別認識的に感じることもない。もちろん認識論層にずっといれば、そもそも 「ゆたかさ」 なんて一体何をいっているのかさえ 手触り感 を持って分かるはずがないし、どこか一つの層に永住している人はそれ以外について想像することもできない。 いきもの としての 「ゆたかさ」 は、元来 人間 の勝手な都合で特別認識的に感じるものではないのだ。
それでも、 いきもの が前に進もうとするヒントは、日常の中にあまりにもたくさん溢れている。
例えば、「母性」も「日本的父性」の土には必要な養分である。「母性」 豊か に、誰かの痛みや苦しみに没入することは、それをなんとかしたいと願う原動力を生み出す。この原動力は、出発するために必要な大事なエネルギーになるはずだ。
だが、一度大きな局面で「母性」を 発揮 した 人間 が、「父性」を宿すのはとてつもなく困難なことである。人生の中で「母性」的な大きな選択を一度してしまうと、その快楽性は 意思 の外側で自動化されてしまう。またそれからは、あらゆる「 喜び 」も苦しみも「固体」となって襲ってくるようになる。
本稿でいくら「苦しみに向き合うことが大切だ」と言ったところで、「固体」で襲ってくる苦しみを「父性」に関心のない者が「融解・抱擁・輝化」させることは難しい。そうして積み重なった無数の「固体」(=不発弾)によって塞がれた道は回り道をして通るしかない。
そうした分解されない「母性」的な「固体」は、土に還ることもなく養分にさえなり得ない。「母性」を土の養分にするためには、分解・発酵されなければいけないのだ。
「母性」的な固体を発酵させて土の養分にするためには、まずは自分自身がこれまでしてきた「母性」的な選択を今の何億倍もの努力と向き合い方によって謳歌するところから始めよう。頭のネジを外して後先考えずに謳歌して謳歌して謳歌するその精神性は、「安心安全」なリスクヘッジを少し薄れさせる。
そうして徐々に守られなくなった「固体」は、ようやく分解される時期を迎える。一度始まった分解は周りの環境を殺さない限り続いていく。
そして、何らかの「ぬくもり」に触れた時、発酵が始まる。その瞬間、ようやく「 来る未来 」を受け入れられるようになる。
発酵されたらそれは養分になって、貴方の背中は一回り大きくなるだろう。
そして、これまでの「母性」的な選択によって「諦め」た選択を、もう一度「行って 会って やって 話す」ところから全ては動き始める。その後がどうなるかなんて、きっとそこまで行ってみれば自ずから(おのずから)見えてくることなのである。
その瞬間貴方にもきっと「父性」を 発揮 する可能性が芽生えているだろう。「父性」のその先にどんな「奇跡」が待っているかなんて、想像できるはずがない。
この流れは、円錐の中の認識世界の住人にとっても「母性」的な人にとっても、現実的に日々の生活から起こせる変化のヒントだ。勿論、謳歌の仕方が弱かったら分解は始まらない。だが、得意の認識技術でそんな未来は見ないようにすればいい。「それで分解されるならそれはそれまでだった」と思える人だけが、きっとこうした変化を起こしていくことができる。
もしもそんな未来が怖くて、もう今、目の前にあるものを「満たされる道具」にすることしかできず、謳歌することもできないのなら、それはそれまでということだ。幸福なゲームのような人生は終わったら終了だ。
「一分一秒を悔いのないように生きる。精いっぱい生きる。エブリ デイ マイ ラスト」
– 市川大輔
-守破離と忍耐
ここまで、本稿では何度か「守破離」という言葉が登場している。「守破離」の概念は、主に 日本 の伝統的な芸術や武道、そして職人の技術において使われる概念で、学習と習得の過程を表している。師匠と弟子の関係性や、伝統と革新のバランスを保つための指針として機能していたとされ、口伝や実践を通じて伝えられてきたと考えられている。
この概念は、修行者が技術や芸術を習得する際の三つの段階を象徴している。
まず、「守」の段階では、学習者は師匠や教材から基本的な技術やルール、形式を学ぶ。この段階の目的は、伝統的な方法や技術を忠実に習得することにある。
次に、「破」の段階では、学習者は基本的な技術を身につけた後、それらの技術を超えて独自のスタイルを模索し始める。ここでは、既存の枠組みを超え、新たな技術や表現を試みることが奨励される。
そして「離」の段階では、学習者が完全な独立に達し、自らのスタイルを確立する段階を迎える。
「父性」の中でも特に「超越」の過程と「守破離」はとても似ているものがある。「守」っていたものを「破って(破られて)」「離れていく」流れは、まさに「超越」の工程と瓜二つである。
この「守破離」は、私たちの日常を取り巻くあらゆるものに適応可能なものであり、それは何らかの認識に対抗する手段の一つでもある。
近代的な主体性が存在しなかった 日本 では、全てのものが「みずから」そして「おのずから」起こることであり、「守破離」の中の「守」も「破」も「離」も、「みずから」起こそうとするだけでは起きず、「おのずから」起こるタイミングを待つことが重要であった。
さて、それでは私たちが気が付かないうちに囚われているものは何だろうか。それはまさに第二章で紹介した近代概念の数々や、そうした概念を基盤に据えた近代以後の制度やインフラ、そうした環境で生きる中で育まれた認識の数々なのである。
こうしたものたちに囲まれて生きているが、私たちはそれらを真剣に「守」しているのだろうか。近代概念の数々についてどれだけその歴史や内容に迫ったことがあるだろうか。当たり前だと見過ごしているあらゆる認識について、どれほど真剣にその歴史や内容に向き合ったことがあるだろうか。もしも、思考で考えてみたことがあったとしても、そうしたものが育まれた環境に身を置いて触れて感じるところまで試みてみたことはあるだろうか。こうしたことに全く無関心であれば、それは「守」さえも始まっていないということである。
認識世界の住人にとっては、「守破離」をしてしまうということは、究極まで行けば意味の不在やその 虚構 性(ニヒリズム的絶望)に気が付いてしまうということでもあるため、弱きものや大切なものに 生命 を懸けたいと思うようなことがない限りは、「守破離」は都合の良い時にだけしか行われないようになっている。
情報が民主化され、世の中の大半のことを調べて知ることができるようになったこの時代に、私たちはまず「守」を直向きに行う精神性を取り戻さなければいけない。
その精神性は「行って 会って やって 話す」の回復とも繋がっている。
これまで無意識のうちに作り続けてきたあらゆる「認識」について、一つ一つでいいから、向き合っていくことが「日本的父性」が醸成される可能性を生み出す土壌作りになり、「諦め」無き生き様を手繰り寄せていく。
「自ら(みずから)」と「自ずから(おのずから)」が あわい を成すようなタイミングを見逃さないように、日常から注意深くあらなければならない。
「自ら」それを行おうとしていても、「自ずから」それに導かれる環境やタイミングにいなければ、「守」は始まらない。
例え苦しいことや嫌なことがあったとしても、簡単に「離」れ続けていればただただ固体の認識(=不発弾)を自分の周りにさらに増やし続けていくだけである。「守」も「破」もない「離」は、「楽」をもたらす アヘン である。
さまざまな情報を集めるだけ集めて「新しそうなアイデア」を思いついたと喜んで、すぐに何かを始めていればそれ相応の小さな認識物しかこの世界に生み出さない。いずれそれは誰かの挑戦を阻む邪魔になったり誰かを傷つける凶器にさえなるだろう。
おばあちゃんの無目的的な生き方を無関心に見過ごしていればおばあちゃんはそのうちに死んでしまう。頭のネジを外して向き合い、謳歌する姿勢、忍耐を持って、それでも「守」ろうとする「 意志 」を持つことが全てのスタートである。
「自分の苦しみを苦しみ抜こう自分の悲しみを悲しみ抜こうそれでやっと本当の自分になれるんだ。
自分を変えられる人だけがこの世界を変えられるんです。」
– 坂本金八『3年B組金八先生』
(つづく)