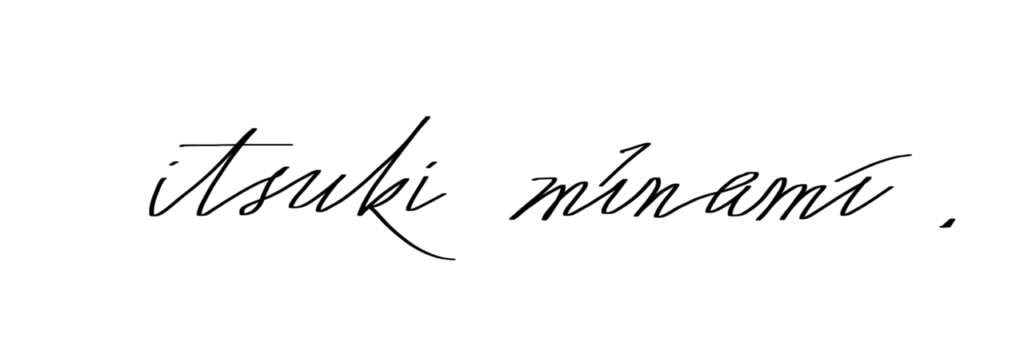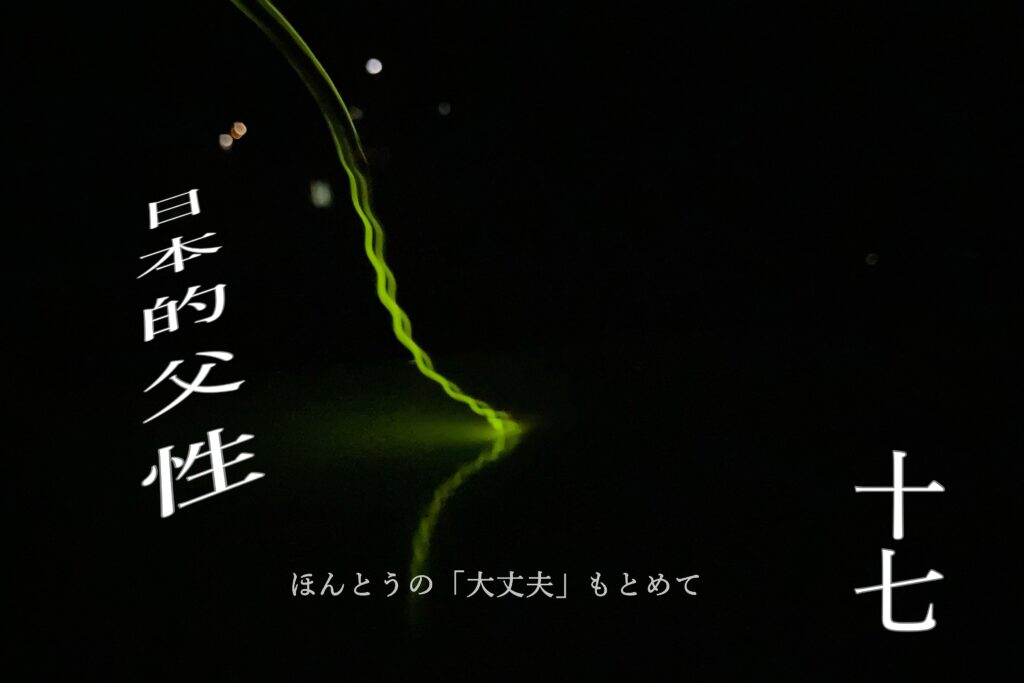
17.第四章「デジタルネイチャーと父性」
『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –
目次
-日本的父性とオーラ
「死」の議論でも語られる「一回性」が、重要な要素となるもので「オーラ」というものがある。
「オーラ(アウラ)」とは、ある対象を前にして感じる畏怖や崇敬などの神秘的な感覚のことだという定義がある。本書で言うところの「 直覚 」する何かの一種だと考えることもできる。
ドイツの哲学者 ベンヤミン は、「オーラ」の重要な要素の一つとして「一回性」を挙げている。それが故に、ベンヤミンは技術的複製の時代に入ると、「オーラ」は失われていくと考察していた。
独自性を持ったものを技術的複製難易度が低い メディア に変換すると、「オーラ」は減少したり失われたりする可能性があるとベンヤミンは示していたのだ。
そして、実際に一日のうちの大半の時間を、技術的複製難易度が低い メディア に身体と意識を向けるようになった我々は、「オーラ」を感じる機会を大幅に失った可能性がある。しかし、我々はそれ以前の時代をもはや「知らない」ため、機会を失ったことにさえも気が付かない。
一方で、デジタルネイチャーに向かっていくにつれて、また以前とは少し違った「オーラ」が戻ってくるのではないかという議論がある。
例えば、近代の大量生産で広がった画一的なデザインや、大衆文化によって育まれた画一的な認識体系などが、ハード・ソフト両面で、再個別最適化していくのではないかという予測だ。これを 「コンピューテーショナル・ダイバーシティ」 ともいうが、デジタルネイチャーな時代に向けてそのような変化が徐々に進んだとして、果たして「オーラ」は本当に戻ってくるのだろうか。
例えば、技術的複製難易度が低い メディア だとしても、個々人に最適化され、電脳化によって知覚器を介することなくリアル・ヴァーチャルな世界の事物に触れるようになった時、そこには以前のように生々しい「オーラ」が蘇るのだろうか。
そうなると、そうした世界の有象無象は「作り物」ではなく、「あるもの」と何ら差異のないものになっていく。
マルチヴァースの生態系は、人類の認識しないところで自動的に生成と破壊を繰り返しながら広がっていく。
もはやその頃には、「オーラ」は認識的には以前のものと何ら大差ない状態に戻っていることだろう。もちろん「そこに何が宿るのか」については、遥かに小さなものになるかもしれないのだが、それに人々が気がつくことは限りなく「ありえない」に等しい。
そうなってくると目を向けたいのが、「日本的父性」である。ベンヤミンは「オーラ」を「空間と時間の織り成す一つの奇妙な織物」と定義し、その存在を「夏の真昼、寛ぎながら、地平に連なる山並を、あるいは見つめている者に影を落としている木の枝を、瞬間あるいは時間がそれらの現れに関与するまで、目で追うこと」 [35] と表現したことがある。
「日本的父性」において、その育まれる過程で一体どれほどの「大地性」が影響を及ぼすのかは前述した通りだ。「大地性」は常に遥かなる「一回性」を持っている。
「父性」の中でも特に、「日本的父性」を宿すものの大きな背中には、「オーラ」が宿る。
先にも書いた通り、「日本的父性」が失われていくのと同じように、「オーラ」も失われてきた。では、「オーラ」が戻ってくるのと同時に、「日本的父性」も戻ってくるのだろうか。
それは限りなく難しいと言えるだろう。
グローバルなサイバー空間において、それが 日本 的な環境である必要なんてさらさら無いし、そこでは「安心」と「安全」が担保されている可能性が高いため、「日本的父性」の復活は愚か、その頃には消滅している可能性が高い。
一方で、限りなく可能性は低いが、サイバー空間やメタヴァースで 日本 の自然環境のようなものが再現されれば、国籍や人種を問わず、「日本的父性」を宿す人が再び現れるかもしれない。だが、もしも「オーラ」だけが戻って「日本的父性」が失われていけば、 日本 人はより「日本的父性」への 直覚 可能性を失っていくことになるだろう。
「オーラ」と「一回性」の関係性に、「死」は否応なしに寄り添っている。
「日本的父性」に見る「オーラ」は、余計なものを削り落としていく生き様に大きく影響を与えられている。
「風のように生き風のように死ぬ」というような「日本的父性」の土壌となる 風景 は、そこで自ずから(おのずから)醸成される「一回性」に従っている。
涼しくて心地よい風が吹く時もあれば、あまりにも痛くてきつい風が吹く時もある。風のように生きるとは、「誰かの言動や何かの現象を真剣に受け止めて痛みや苦しみに苛まれることがなくなる」ということではない。風に直接触れるということは、身体をもって傷つくということでもある。
オーラは直接触れ合う。認識で生まれる痛みや苦しみとは全く異なり、直接風に当たった身体が受ける痛みや苦しみは計り知れない。
だから人は誰かに支えられ、何かに支えられ、生きるようになる。自分には到底敵わない大いなるものの中で生きることは、難しい。支え合い、 氣 を与え合い、あらゆるものの「おかげさま」で生きるしかない。
そのようなことが言葉にするまでもなく当たり前だった時代では、人々にとって「一回性」を拒むことは趣のない嗜みに過ぎなかった。
全ては自ずから(おのずから)起こることであり、その結果、人の心に「生ききる」という感覚が醸成されていくようになる。「生ききって、死ぬんだ」「生ききる」という感覚は、「死」と溶け合っていく感覚にも似ている。「生ききる」とは、「できる限り長く生きる」という意味合いではない。あらゆる一回性を、謳歌し、愛しむという、「 悦び 」そのものである。
そうした「生」や「死」に宿る一回性に、日常から触れ続けることは、 日本 独特の「オーラ」を育むために必要不可欠なものであった。
こうした環境が、デジタルネイチャーな空間で生み出されるかと言えばやはり甚だ怪しい。
魔術化 されたあらゆる事象やそれを織りなすエコシステムは、あらゆる「生」や「死」を孕んだ遥かなる世界には認識できても、いつかの時代の科学技術が発端となって生まれた「同じような感情を持った 生命 体」は、あくまで平面的情報処理の連続によってしか育まれない可能性が高い。
ゴーストにオーラは結びつくため、複製されたものや他の認識物へと変換されたものは、決して本体と同じオーラを宿さない。
現時点ではエネルギーの観点からして、「創造された 生命 」は、超量子的特性を遥か永遠に連なる層にわたって「ある世界」で触れていくことは難しい。
あくまで認識スクリーンの情報処理の連続は、近代認識論の外側から見れば、「何か」を欠如させるのである。
“The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science.”
– “The World As I See It” Albert Einstein, 20th century
-ぬくもりと灯
さて、その欠如していく「何か」とは一体何か、本稿ではそれを「ぬくもり」と呼びたい。「日本的父性」が纏うオーラには、「ぬくもり」がある。
では、そもそも「ぬくもり」とは何だろうか。本稿で使う「ぬくもり」という言葉は、一体どのような 風景 を表しているのかについて、少しそのイメージを描いておきたいと思う。
真っ暗な海の中を、ゆらゆらと彷徨う。見える先は永遠に真っ暗闇である。
冷たい水温、永遠の闇、、、
それに気が付かないようにするために認識技術を 向上 させ、認識スクリーンの 透過度 を下げ続けていく。
もはや目は必要なくなる。ネガティブな感情に出会う度に、目の感覚機能を麻痺させていく。
ほんとうの外界などもうどうでもいい。目を閉じて、認識できる「 喜び 」にだけ、感覚を研ぎ澄ませていく、、、。
こうしたイメージは、 いきもの としては全くどうでもいいのに、社会構造が「世界をどう認識するか」という 西洋 的な 「生の原動力」 を迫ってくることで起こる 「いのちとの乖離」 が生む「息苦しさ」の正体(直覚的風景)でもある。
そんな暗闇の中でも、どれほど寂しくても、絶望的でも、生き続けていたら目の感覚機能が完全に死んでしまう前に「灯」に出会うことがある。
水中からではうまく見えないが、真っ暗闇のその先に、小さな小さな橙色に光る「灯」が確かにある。
「目的」も「意味」もないまま、認識機械を動作させる前に、その灯に感覚を持っていかれる。なぜだろう。最早その時は 人間 ではなく、 いきもの として、そこに向かっている。
その灯に向かって泳ぎ続けていく時に、これまで身の回りに「足し算」し続けてきたあれやこれやがまとわりつき、うまく進んでいけない。
それでも、そうしたものを振り払って進めば、その度に痛みや苦しみが生じる。それでも少しずつ前に進んでいく。
だんだんと「灯」に近づいてくる。
それに伴って、水面もだんだんと近づいて来る。これまで身につけてきたものをいくら振り払っても、「海水」という最も壮大なものとおさらばする瞬間ほど恐ろしいものはない。なぜなら記憶のあるうちでは、海水中でしか生きたことがないからだ。水面から上に出れば、待っているのは「死」だと思っている。というかそうとしか考えられない。恐ろしい。恐ろしい。
まずは片手だけ、水面に出してみる。あたたかい。出した手に、血が巡っていることが分かる。
もう少しで、もっとあたたかいものに触れられる気がする。その瞬間に、「灯」に触れようという「 意志 」が芽生える。
そして、数多の偶然が重なり、数奇な環境作用が発生することによって、ようやく、海の外へ全身を出す。全身に「ぬくもり」が蘇る。心臓が生きている。
そこには、小さな島と、灯台がある。灯台の先に小さな光があって、これがあの時に見た「灯」だったことが分かる。
海水の中に戻りたくなる「 意思 」を「 意志 」が壊そうとするのだが、壊しては生まれ、壊しては生まれを繰り返す。そんな中でも、少しずつ灯台の「灯」に大地を這いつくばりながら近寄っていく。
そしてまた、数多の偶然が重なり、数奇な環境作用が発生することによって、「灯」が遥かに広がり、とうとう身体が「灯」に触れた時、周りにあったはずの海水は一斉に輝化していく。これまで恐怖だったものが、私と同じように「ぬくもり」を感じて、とてつもなく 「ゆたか」 に輝化していく。 「全」 に触れ、 「全」 になる。圧巻で圧倒的なものに解き放たれる。海水もまた自分の一部になって、世界に溶けて輝きに変わる。
本稿における「ぬくもり」とは、「遥か永遠に認識できないもの」を前提にしたものであり、「心がホッと温まること」のみを描く言葉ではない。
「全」 が発する 直覚 が持つ、包み込むような、それでいて風のように心地よい、あたたかさである。
優しくて大いなるものの存在を遥か遠くまで感じさせ、決して「(他を隠すほどの)今」に留めたりせず、「遥かなる過去も遥かなる未来も包み込み、そして時間という概念さえ超越した今」を感じさせるものなのである。
「日本的父性」を宿す者が感じさせる「ぬくもり」は、認識するからあるのではなく、「生きている」からあるのであって、その儚さが「一回性」であり、それは複製もできないし、代替もできないのだ。
では、それなら「創造」はできるのだろうか。今後やってくるデジタルネイチャーな未来で、人はロボットに「ぬくもり」を感じることができるのだろうか。機械が 人間 を超越し、 「全」 なるエコシステムの一部になった時、我々は 生命 機械からも「ぬくもり」を感じて 物化 することがあるのだろうか。
本稿の見解としては、いずれは可能だが当面は不可能であると予見する。
例え 物化 を媒体する メディア が何であっても、それが「一回性」を持つという条件を満たす限り、たいして差異はないのだ。
初めのうちはどんな 生命 機械もある程度の計算を踏めば再現が可能なものであり、「ぬくもり」を持つ 生命 機械は生まれてこないだろう。
しかし、デジタルネイチャーな時代が発酵してくると、その計算指数は限りなく再現不可能なところへ到達するだろう。それは「一即是無限」を前提とした世界線であり、 人間 やその他の生物が生まれるまでの歴史の膨大な量と紙一重か、もしくはそれ以上の一回性を持つ偶然そのものになるのである。
だが、それはあくまでも(認識技術次第では)認識可能な歴史の量なのである。
もし我々が「遥か永遠に認識できないもの」に大きく依拠しているのだとすれば、 生命 機械が純粋な「ぬくもり」を持つことは根源的に不可能だとも言える。「認識できる」「認識してない」の二項対立が存在しない世界線の 日本 においては、 生命 機械はあくまでどこまでいっても「(認識技術次第で)認識できるもの」でしかないのである。
一方で、デジタルネイチャーな世界線に、現代の 日本 のままで進んでいけば、誰一人、例えその メディア が 生命 機械じゃないとしても、 物化 などできないような認識世界の住人が増え続けていく可能性が高い。空っぽな 日本 人は、加速度的に増え続けていく。
そうなると、認識的には限りなく 生命 機械も「ぬくもり」を持つものと感じることができるようになるのである。だがそれは、「輝化」させるものではなく、「水化」させる灯でしかないのだ。その中で失われていくものがあることは、デジタルネイチャーな環境に近づいていけば行くほど、気が付きにくくなっていくだろう。
ぬくもり は、漢字で書くと「温もり」と書くのだが、論語にこんな一節がある。
「子日く、故きを温ねて新しきを知れば、以って師と為る可し」
これは「温故知新」という四字熟語の元になった文だが、ここでは「温」という漢字を「たず(ねる)」と読んでいる。本稿でいうところの「行って 会って やって 話す」や、おばあちゃんの話、後で解説する「守破離」という行い、そして初めに示した「素読」という行為、その全ての重要性がここに集結し現れてくる。
故き(ふるき)ものは、「知る」のではなく、「温ねる(たずねる)」ことが大切で、「行って 会って やって 話す」の中には認識不可能な範囲(=「ぬくもり」)のやり取りが生まれる可能性が高い。
「知らなきゃ」沼、「理解しなきゃ」沼に入る前に、「温ねる(たずねる)」行いを実直に行なってこそ、その先に繋がっていくはずなのである。これは現代人が忘れているとても大切なことなのではないだろうか。
そしてデジタルネイチャーな世界線が近付いて来ると、人々はこうした認識的な中毒性の薄い行いに時間を割くことが難しくなり、より都合の良い新しきものにばかり囲まれるようになっていくだろう。
いずれ人々は感情パラメーターの変動を「温もり」という言葉で表すようになり、「ぬくもり」の無い冷たい冷たい世界は、形骸化した「温もり」及び感情起動スイッチで溢れかえるだろう。
しかし元来、新しきものは「知る」こと、「嗜み」に留めておくことが大切なのだ。
そしてそれは故き(ふるき)を温ね(たずね)た後に向かうべき彩りなのではないだろうか。
ということを、千数百年もの間、日本人は「素読」的に反芻し、身につけていた可能性が高い。
認識的なものに囲まれている限り、感情や感覚を満たしてくれる都合の良いものに人々は呑まれていく。それを食い止めるために人々は「素読」でこうしたことを肌身に染み込ませていたのではないだろうか。 故き(ふるき)を「温ねる(たずねる)」ことで作り上げた認識スクリーンを「融解・抱擁・輝化」する可能性を探り、「氣」をいただき、与え、「大いなるもの」の環境は人々にその重要性を覚えさせていたのではないだろうか。
そしてそこには、これからどんどん忘れ去られていく「ぬくもり」なる何かがあったのではないだろうか。
「誰にでも闇があると思うんです。でも闇の中から光は生まれるまれるんですよね。」
– haruka nakamura
-水中における父性の行方
「風のように生き、風のように死ぬ」とも言える 風景 を醸成したのが日本的自然観だったのだとすると、認識論の延長で提唱される「デジタルネイチャー」が醸成するのはどんな 風景 なのだろうか。
先ほど「水化」という言葉が登場したが、認識世界の住人たちは、「水のように生きる」という表現に親しみを感じやすい。古代中国の思想家、老子はこう言ったとされている。
「上善は水のごとし。水は善く万物を利して争わず、衆人の悪(にく)む所に処(お)る。故に道に幾(ちか)し、居るは善く地、心は善く淵(えん)、与うるは善く仁、言は善く信、正すは善く治、事は善く能、動くは善く時。それただ争わず、故に尤(とが)なし。」
「灯」に触れてあらゆるものが輝化するという奇跡に遭遇することなく生き続けていく人の最も真なるところは、ここに行き着く。
「風」と「水」を分かりやすく表現する 風景 を見てみよう。
「風」に「神風」という言葉があるように、マイナーだが「水」にも「神水」という言葉がある。だが、この両者は根本的にそのベクトルの向きに違いがある。「神風」は、「遥か永遠に認識できないもの」を前提とした現象から「 人間 の認識」へと嗜み的に移ろうが、「神水」は「 人間 の認識」から「今のところ認識できないもの」への「願い」へと移ろってゆく。「風」に主体はないが、「水」には主体的起点がある。「水のように生きる」とは、水のように流れに身を任せて生きていこうとする姿勢のことであり、そこにはあくまでも定点的な主体性が前提として隠れている。
日本 には大小様々な河川があり、この島国の 豊か な自然環境を支える重要な役割を果たしてきた。そうして海から脱出した水の住人たちは、河川などの水からたくさんのことを学び、たくさんの気付きを得てきた。水の住人はあくまでも水からは離れられないのである。デジタルネイチャーな世界線では、こうした水の住人が自己肯定感を得やすい環境が構築されていくことになると考えられる。
あらゆる メディア やインフラが再 魔術化 され、個別最適化が進むことで、マルチヴァースを行き交う「水のように生きる」ノマドの人々は、「都合の良い自然」の中で生きられるようになる。近代認識論の底なし 沼 は、人々をどこまでもどこまでも満たし続けていく。
そうなると、水の住人は「父性」に興味をなくしていくと考えられる。痛みや苦しみは「意味」や「居場所」の移動によって認識変換され忘れ去られていくことがより容易になっていく。「 いきもの 」としての「息苦しさ」以外のネガティブな感情は「母性」ある人々の影響によって「回避」され、認識範囲内から葬り去られていく。
これは「 沼 」なので、あくまで賢明に生きようとすればするほど加速していく自動的な変化なのである。これを人々は「水のように生きる」のだと言い、「あくまでも自然なんだ」と声をあげ続けるだろう。
この流れに「父性」は特別必要とされない。そうなってくると先ほども述べたように機械の方が上手な「統計学的父性」しか残らないだろう。
水の住人にとって「輝化」は認識不可能な現象であり、それを体験する前は恐怖そのものである。その反対に「統計学的父性」における「大丈夫」は「水化」をもたらす。「水化」とは、水の住人にとって、「そのまま流されていけばいい」という、あまりにも「安心安全」なメッセージなのだ。
水の住人は認識を超えた「引き算」に、ただならぬ拒否感を覚える。そんな恐怖をかき消すように、「いいから、消さなくていいから、そのまんま流れたらいいのよ」と教えてくれるのが「水化」なのである。
それが流れて流れて海に行きつき、誰かを闇で囲い込む一部になることも、「自然」だと認識できるようになる。そしていつかまた雨となって循環するという循環思想が、「しっくりくる感覚」をもたらしてくれるのだ。
「恐れ、不安、孤独、闇、それから、もしかしたら希望 希望?真っ暗な海の中で?
海面に浮かび上がる時、今までとは違う自分になれるんじゃないかそんな気がする時があるの。」
– 草薙素子『攻殻機動隊』
(つづく)