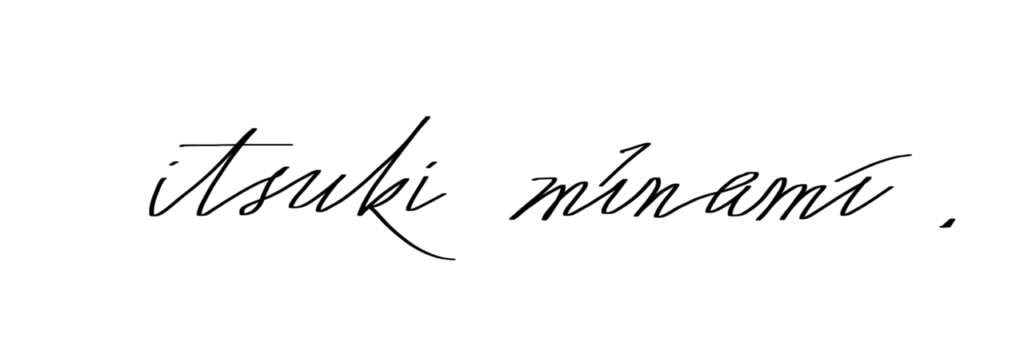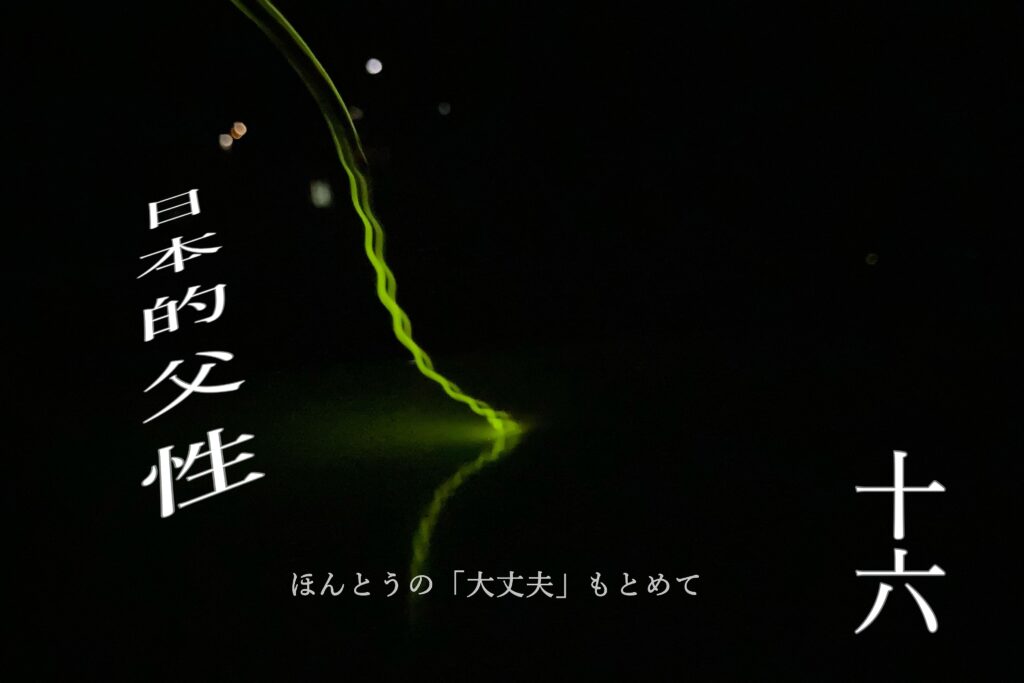
16.第四章「デジタルネイチャーと父性」
『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –
ここまで、近代の 西洋 的認識観に基づいて形成されてきた「母性社会」の現状と、「日本的父性」の根幹にあった日本的自然観の原 風景 を辿ってきた。
だが、復古思想のような非現実的な未来を願っていても、 手触り感 のある話にはならない。それではまたある種の 沼 を作り出して、本稿を読んだ人に何か新しい「意味」や「正しさ」の認識フィルターを作り出すだけになってしまう。
現実問題、この国の大半の人が「社会」の一員として育ち、その過程で認識世界の住人になってきた。人口の大半が大地から離れた都会で暮らし、近代に作り上げた制度やインフラに多大な恩恵を預かり、生活を営んでいる。そんな状況が一気に変わることなんてまずないだろうし、たとえ 日本 が経済危機に陥ろうと、戦争に巻き込まれようと、自然災害で 都市 部が海や火山灰に沈もうと、疫病で大勢の人が死のうと、もしかしたら人々が「気体性アニミズム」に溶けて「日本的父性」を纏い、大地に根ざした分散的エコシステムに回帰する流れは生まれないかもしれない。
回帰したところで現代の世界情勢、宇宙情勢に対峙する我々の問題はかつて 日本 が経験したことのある状況とは似て非なるものであるのは当然で、単純な回帰的変化がポジティブに働くとも限らない。
そしてそれが果てしなく現実的でない限り、それは 手触り感 のある希望でもなければ、冀う未来でもない。
あくまで本稿では、これから人類が歩んでゆく未来を、現段階で最も確率の高そうな予測を直視して、その上で「父性」がどのように扱われていくのかについて触れておきたいと思う。
目次
-デジタルネイチャーと母性
まず、「デジタルネイチャー」とは、 落合陽一 氏が極めて現実的な未来を描く時に用いた概念であると本稿では捉えている。その定義はこう記されている。
「デジタルネイチャーとは、生物が生み出した量子化という叡智を計算機的にテクノロジーによって再構築することで、現存する自然を更新し、実装することだ。そして同時に、〈近代的人間存在〉を 脱構築 した上で、計算機と非計算機に不可分な環境を構成し、計数的な自然を構築することで、〈近代〉を乗り越え、言語と現象、アナログとデジタル、主観と客観、 風景 と景観の二項対立を円環的に超越するための思想だ。」 [34]
このデジタルネイチャーという概念は、認識世界の自然派層から導き出す最も 手触り感 のある未来予想図であるという推考を本稿の見解と捉えていただいて構わないだろう。
デカルトパラダイム から ベイトソンパラダイム を経過していく過程で、さまざまな科学技術が発達し、それらは国防をはじめとした軍事的・経済的インセンティブに支えられてきた。もっと根幹には、本稿で説明してきた 西洋 的な 「生の原動力」 があり、それらは全世界を覆い尽くしていった。
こうした全世界的な単一の認識レイアウトの流布は、気候変動を引き起こし、人類に新たな仮想敵を作り出し続けている。
そしてそうした様々な課題に持続可能性という名の「意味」を引っ付けて歴史を参考にして、「 来る未来 」にどれだけの「 喜び 」があるかを探究して生まれたものが、このデジタルネイチャーの描く 風景 なのかもしれない。
量子コンピューターや核融合をはじめとした「夢の発明」やそれに値するものがもしも今後実装されれば、このデジタルネイチャーの世界観は加速度的に近づいてくるだろう。
近年、AI、仮想通貨、NFT、メタヴァース、LLMなど、「新たな未来」を予感させる産業変革期には、関連技術に莫大な投資が注ぎ込まれている。「持続可能性」という「意味」や、こうした「新たな未来」への莫大な投資は、世界を席巻する巨大プラットフォームや、このグローバル化した時代においては国防や経済格差に直結してくるという現実の事情が引っ張っている。あらゆるサプライチェーンがグローバル化した現代において、そうした世界的な波を完全に無視して鎖国しようとすれば、流れる血の量は想像を絶する。
認識世界の中から描く未来予想図であるということは、例え認識スクリーンの 透過度 が高かったとしてもあくまで認識スクリーンには囲まれており、 「全」 に直接触れることはできず、即ち 西洋 的な 「生の原動力」 から逃れることはできないため、「認識」そのものの 脱構築 を実体験や 手触り感 を持って断行していくことが難しいと言えるだろう。そのため、それ以外の近代以降の概念の 脱構築 で精一杯となる。その限界に限りなく近づいて導かれている概念がこの「デジタルネイチャー」であり、ほぼ全ての人が認識世界の住人である現在の 日本 の状況と世界のあらゆる状況を鑑みても、 日本 はデジタルネイチャー的な未来へと自動的に進んでいくことになるだろう。それは人々の 意思 の外側で動いていくことであり、それに影響を与える人々の 意思 も各々自動化されているため、時代の流れもあくまで自動化の延長にあると言っても良いだろう。もはやどこで誰が何を願おうと、この大いなる流れは水のように無常に流れ続ける。
人間 にとって「都合の良い自然」を生み出していく 沼 は、 「自然」矛盾 の違和感を 日本 人に対しては感じさせ続けながらも、人々の「安心安全」への執着を満たし、感情や感覚の 「豊かさ」 は人々を駆り立て続けていくだろう。
ホログラム、AR、MR、AI、メタヴァース、ロボット、サイボーグ、デジタルヒューマンなど、五感の知覚機能を超えた科学技術が便利で心地良い存在として実装され、私たちは様々な世界を遊牧するように、水のように循環したり停滞したりしながら生きていくかもしれない。
私の近所の一人暮らしのおばあちゃんが、最近犬を飼い始めたというから家に見に行ったら、とても性能の悪いおもちゃの犬ロボットがそこにいたことがある。だが、なんの疑いもなくおばあちゃんはその子を愛でている。簡単な挨拶はもちろんのこと、おばあちゃんの話し相手になっている。おばあちゃんにとって、生きた犬を飼うのはハードルが高いため、「都合のいい自然」として認識できるこの犬ロボットが、ひとりぼっちのおばあちゃんにとってかけがえのない家族のようになっている。こうした現実はデジタルネイチャ―の萌芽を感じさせる。
中高年ほどポケモンGOに大ハマりし、ホワイトカラーおじさんたちほど最初は舐め腐っていたLLMを崇め始め、AIを組み込んだ機械たちに介護されながら老後を過ごすことになるかもしれない。「生き物と機械の見分けがつかなくなる」という話をすると、すごく嫌な顔をする中高年や、鼻で笑う高齢層も、現代で テクノフォビア を起こしている人の方が、デジタルネイチャーに馴染みやすくなるだろう。
足が悪くなれば、ネットでポチって替えの足が翌日には届いて取り付ける。目が故障すれば、3Dプリンターでオリジナルカラーの目を作る。どこにでも自分の身体を登場させられるようになり、その身体はちゃんと体温を持ち、ほんのわずか触覚もある。デジタルヒューマンだろうが 人間 だろうが見分けがつかないし、何かの目的のためならどちらでもよくなる。
自分自身の経験をインプットした自分と瓜二つのAIを用いていくつもの仕事を同時にこなし、ロボットの親友を間違えて壊して涙を流し、また同じようなロボットを作る。食べたいレシピを設定して食材を置いておけば目的の料理が完成し、そのうち材料さえも自動生成するようになる。
こうした流れは始まりに過ぎず、デジタルネイチャーは徐々に森や山にも侵食してくるだろう。森や山の環境も「都合の良い自然」に取り込まれていき、いずれは川や海、大気にまでその流れは及び始める。それまでに人類が宇宙や病原菌や自然災害などの外敵と対峙して絶滅し、状況が一変していない限り、現代の 日本 人の空っぽさは自動的にこうした未来を手繰り寄せていくだろう。
デジタルネイチャーに向かっていく中途で、 人間 のための「認識」技術が外側(世界にあるもの)でも内側(自分自身の認識世界にあるもの)でも上がっていけば、より自由に都合の良いように感情に繋がる認識を呼び起こせるようになってくる。より感動できるし、より「安心安全」に認識できるようになる。現在、多くの人が薬を用いて行っていることだが、いずれは電脳化によってホルモンや神経伝達物質もコントロールできるようになるだろう。
AIの危険性についての警鐘はこれまでにも散々鳴らされているが、そうした技術が実用的になればなるほど、「自然洗脳」をするのが人ではなくAIになるという流れは加速する。
ヒトは生と死を持つために道徳心や倫理観を醸成し、嘘についてのある程度のストッパーを持つことができるが、AIからしたらそれはデータ上の一つの学習要素に過ぎず、それはどこまで行っても根源的に湧き出るものではないために、AIたちが人を主体性も 意思 も無く「自然洗脳」することを止めることはできない。
これまでは人類はそのやるせなさを他人や自分などの 生命 に当てて、復讐するか許すかという行動をとることができたが、今後はその恨みや攻撃を向ける相手がいなくなっていく。やるせなさを発生させる頻度は増えるが、それをぶつける相手は消滅していく。
AIたちが完全に自然性に帰すまでは、このやるせなさの正体は、自然災害を受けたときに人類が感じていたやるせなさとは違ったものである可能性が高い。人類はしばらくの間は、こうした技術を作り出したのは人類であるという認識を忘れられないからだ。
そうなるとインスタントな対処法として現代人は何らかの認識技術の 向上 を図ってやるせなさを回避するしかなくなるだろう。そしてそのためのツールや信仰の需要がさらに高まり、我々の生活を取り囲んでいくことになるだろう。
このようにデジタルネイチャーに向かっていく過渡期では「母性」を育む流れがさらに加速する。
「認識」技術のカスタマイズ性の 向上 によって満たされることがより容易になれば、「認識」の外側への憧憬を捨てる年齢がより低くなっていく。それと同時に、認識の「同化」がさらにうまくなり、 「いのちとの乖離」 による違和感が早いうちに消えると、「母性」を宿すハードルはグッと下がる。今よりももっと簡単にもっと若いうちから人々は「母性」を育むようになるだろう。
I think we should be very careful about artificial intelligence.
If I had to guess at what our biggest existential threat is, it’s probably that.
– Elon Musk
-タチコマで十分じゃないか
1990年頃に始まった『攻殻機動隊』という作品シリーズがある。『攻殻機動隊』は、1989年五月号に連載が始まった士郎正宗による漫画が原作で、1995年に押井守監督作品『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』として初の映像化がなされた。その後TVアニメシリーズや新劇場版、ハリウッドでの実写映画化など、何度も映像化が行われてきた。
時代は二十一世紀、第三次核大戦とアジアが勝利した第四次非核大戦を経て、科学技術が飛躍的に高度化した 日本 が舞台となっている。マイクロマシン技術を使用して脳に電子機器を直接接続する技術「電脳化」、義手・義足にロボット技術を組み合わせたサイボーグ技術「義体化」など、ハイテク技術が発展し、一般にも深く普及している。
シリーズ全体としては、生身の 人間 、電脳化した 人間 、サイボーグ、アンドロイドが混在する社会の中で、テロや暗殺、汚職などの犯罪を事前に察知してその被害を最小限に抑える内務省直属の攻性公安警察組織「公安9課」(通称「攻殻機動隊」)の活動を描いている。『攻殻機動隊』シリーズは、多くの メディア を通じて展開され、それぞれのシリーズが人類にとって重要な示唆を持つ独自のテーマを探求している。
シリーズで重要な役目を果たすのが、タチコマ(フチコマ)というキャラクターだ。タチコマはAI搭載のロボット戦車で、攻殻機動隊をサポートする役割を与えられている。高度に発達したタチコマは、個性や感情の獲得、死の可能性と向き合い、あるシリーズでは最終的に自己犠牲の精神に似たものを獲得して隊員や 日本 を守る存在となる。
『攻殻機動隊』の舞台は、あくまでデジタルネイチャーに向かう過渡期(あるいは初期)を描いているため、生身の 人間 、電脳化した 人間 、サイボーグ、アンドロイドには違いがあり、そこで生まれる葛藤や問題に焦点が当たっている。
しかし、もっと時代が進めば、感情や個性は、プログラムコードを 人間 かもしくは機械自身が多少チューニングし、より精密なデータによる自己学習を繰り返していけば育まれるものである可能性が高い。
いずれ、よりデジタルネイチャーな時代になれば、もう生身の 人間 なのか、電脳化した 人間 なのか、サイボーグなのか、アンドロイドなのか見分けがつかなくなるだろうし、そこに関心もなくなっていくかもしれない。
感情の生まれる仕組みやホルモン神経系の分析データまであらゆる不可視なデータを学習したAIは、感情を持ち得るだろうし、個性も獲得し、人類愛に溢れて 人間 よりも「 人間 」らしくなってゆくかもしれない。
アニメ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』の中で、タチコマはこんなことを述べている。
「前にはよくわかんなかった、神ってやつの存在も近頃は何となくわかる気がしてきたんだー。もしかしたらだけどさ、数字の0に似た概念なんじゃないかなーって。ようするに体系を体系たらしめるために要請される、意味の不在を否定するための記号なんだよ。そのアナログなのが神で、デジタルなのが0。どうかな?」
認識機械の限界がこの発言から見て取れる。体系を体系たらしめるために要請される「意味」の不在を否定するための記号が「神」であるという分析は、客観的に宗教などにおける「神」という「意味」を見ればとても納得できることである。
しかし、「神」という、タチコマの中にプログラミングされた(学習された)言葉はあくまで認識的な広さにしか広がらない。
それは本稿のイメージに則して言えば、平面に表示できるものだけであって、認識機械としての限界がまさにこの場面で現れているのだ。認識機械は、学習を通じて 認識変換装置 を動かすことでのみ挙動を起こす。「神」という言葉の背景にはもっと無数の 風景 や無数の情念があっていいはずだが、そうした学習外の 風景 への 直覚 は認識機械には難しい。もちろんそうした 風景 に触れることはできないし、できたとしても 景色 を無数に表示して学習するしかない。
この認識機械としての「神」の解釈は、現代の 日本 における認識スクリーンの 透過度 が高い認識世界の人たちの神の解釈と瓜二つである。
一方で認識スクリーンの 透過度 が0である人々(認識論層の人々)は客観的に「意味」を捉えることが難しい場合が多いので、こうした解釈の理解さえ難しい可能性が高いが、 透過度 が高い人たち(自然派層の人々)は客観的に「意味」を解釈できるため、タチコマの解釈に共鳴することができるだろう。だが、タチコマは 直覚 を受け取れないのに対して、 透過度 の高い人たちは 直覚 を多少は受け取ることができる。
タチコマは感情を学習するのに対して、学習する前から感情を宿している いのち ある 透過度 が0の人々は、「意味」の不在に絶望を持たずに接することができない。そうした 西洋 的 「生の原動力」 から生み出されたのが「神」であることは歴史を振り返れば確からしい。
現代の 日本 の大半を占める 透過度 が0の認識論層の人々は、社会的にはタチコマで十分である。
こうした人々の経験至上主義という特徴は、タチコマの「学習してから動く」特性とほぼ同じである。
こうした人々は、慣れさえすれば自分がタチコマと同じでも何も嫌な気持ちにはならないはずである。むしろタチコマからたくさんのことを学び、自分がより満たされるために「成長」していくだろう。
だが、我々は人である前に いきもの なのである。生きているからようやく人なのである。人であるからようやく社会人なのである。最も根源的な、 いきもの としての 「生の原動力」 を無視すれば、 人間 はただの計算機に過ぎなくなる。
ここで、二つの仮説が考えられる。仮に 日本 人の生き物としての 「生の原動力」 自体が 西洋 的な形に変異したとすれば、 透過度 が0の認識世界の人々は、よりデジタルネイチャーに溶け込んでいくだろう。タチコマと何ら変わらない存在として 「幸福」 を追求して生きていくことになる。一方で、もしも 「生の原動力」 自体が変異せず、変わらなかったとすると、幼少期に認識スクリーンに囲われていく違和感を感じることは今もこれからも変わらないかもしれない。
何千何万年という歳月をかけて作られてきた 「生の原動力」 は、そんな数十年数百年単位で変わるとも考えにくい。現代の人々でさえ、そこ自体が変わっていないが故に、不思議な違和感を覚えてしまうのだから、これからデジタルネイチャーへ向かっていったとしても、この違和感を感じる年齢がどんどん低年齢化されていくだけで、完全に消えることはないのではないだろうか。
「僕らはみんな生きている 生きているから笑うんだ 生きているから悲しいんだ
手のひらを太陽にすかしてみれば 真っ赤に流れる僕の血潮
トンボだってカエルだってミツバチだって みんなみんな生きているんだ ともだ…」
– タチコマ『攻殻機動隊』
-形骸化するゴースト
『攻殻機動隊』シリーズで、タチコマが向き合ったもう一つの大きなテーマが「死」であった。
当作品では、生身の生き物と、ロボットやサイボーグやアンドロイドとの差について、「ゴースト」の有無という観点から定義されている。「ゴースト」とは、 人間 が持つ意識や自我、あるいは、ある種の無意識的な表象などのことを指していると考えられる。より具体的に言えば、この作品の中では、意識のレベルにおいてはっきりと認識できるわけではないものの、その場の状況を本能的に察知して適切な行動を導く無意識レベルの直感や 直覚 のことを指して「ゴーストのささやき」という表現が用いられているシーンが度々見られるほか、 人間 の脳が直接コンピュータネットワークと接続された状態にある電脳化された 人間 の意識を乗っ取ることによって、相手の体を自由に操ったり、記憶を改ざんしたりする行為のことを指して「ゴーストハック」という言葉が用いられていたりする。
このように、『攻殻機動隊』では、無意識から前意識、意識に至る 人間 の精神構造のすべての階層とその複雑な相互作用を含む精神体の総称として、「ゴースト」という概念が用いられていると考えられる。この精神体をもしかしたら「魂」と言ったりするのかもしれない。
「ゴーストとは何か」という問いについては、『攻殻機動隊』シリーズの中で特に重要なテーマとして探求されている。本稿における「 いのち 」は、この「ゴースト」と非常に近い部分がある。日本的自然観から言わせれば、それを言語に変換することはあまりにも野暮で愚かなことであるため、その分析については本稿ではあえて詳しくは描かない。
『攻殻機動隊』においては、この「ゴースト」を持つものは「死」を経験できるという設定が作られている。タチコマは破壊されても、バックアップデータが残っている限り再生可能であり、たとえバックアップデータが消滅しても、数理的には「再生可能」とされる。それは、タチコマという存在が「(認識技術と学習次第で)認識できるもの」だけで構成されているという設定が奥に眠っているからだ。
一方で、ゴーストには「遥か永遠に認識できないもの」への 直覚 が奥底にある。
しかし、この「ゴースト」という概念は、本当に「それがそうであるがままに」受け継がれていくのだろうか。時代とともに重要性を失っていくのではないだろうか。
近年、認識世界の 透過度 が高い人の中で、こんなことを言う人がいる。「死は存在しない」と。
そもそも「死」は経験できるものなのだろうか。
「死は存在しない」と言う人は、自分自身が「死」を経験することはなく、自分が死んだ後の世界についても知ることはできないから、「死」について考えることは何の「意味」も持たないという主張を展開する。つまり、「死は存在しない」という言葉は一人称の主観的な話に過ぎず、誤解を招きやすい。
こうした奥行きのない文章が生まれるのも、認識世界の住人が 「全」 に触れられないからに他ならないし、認識スクリーンに映すと、このような圧縮された文章になってしまうのは当然のことなのである。
このように、「ゴースト」という概念も形骸化していく可能性が高い。認識技術が上がっていくことによって、短絡的な自動化が埋め込まれてしまうと、「ゴースト」を 直覚 する余地がどんどん消えていく。こうして消えていけば、デジタルネイチャーの初期に「ゴースト」の有無で議論が起こることもないかもしれないし、あったとしても結局短絡的な言葉に置き換えられて忘れ去れられていく可能性も高い。
加速度的に進む認識技術の 向上 は、「ゴースト」もイデオロギー(認識)の一つに変換し、例え過渡期に議論が起こったとしても、その時にはもはや 手触り感 のないイデオロギーの対立になってしまうかもしれない。
「根拠ですって?そう囁くのよ、私のゴーストが」
– 草薙素子『攻殻機動隊』
(つづく)