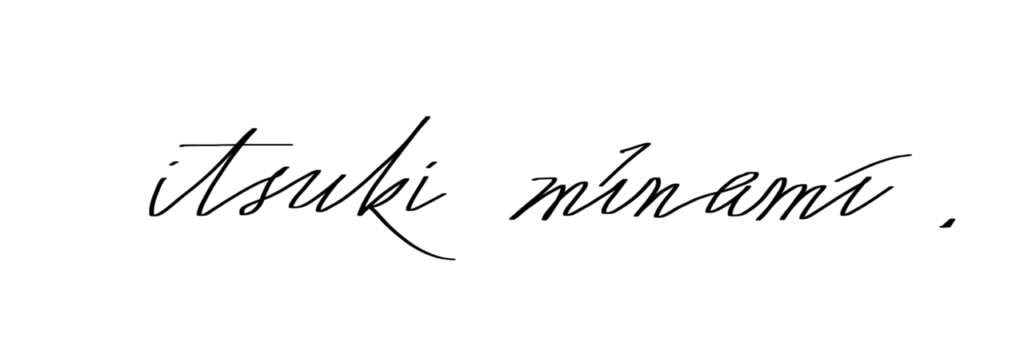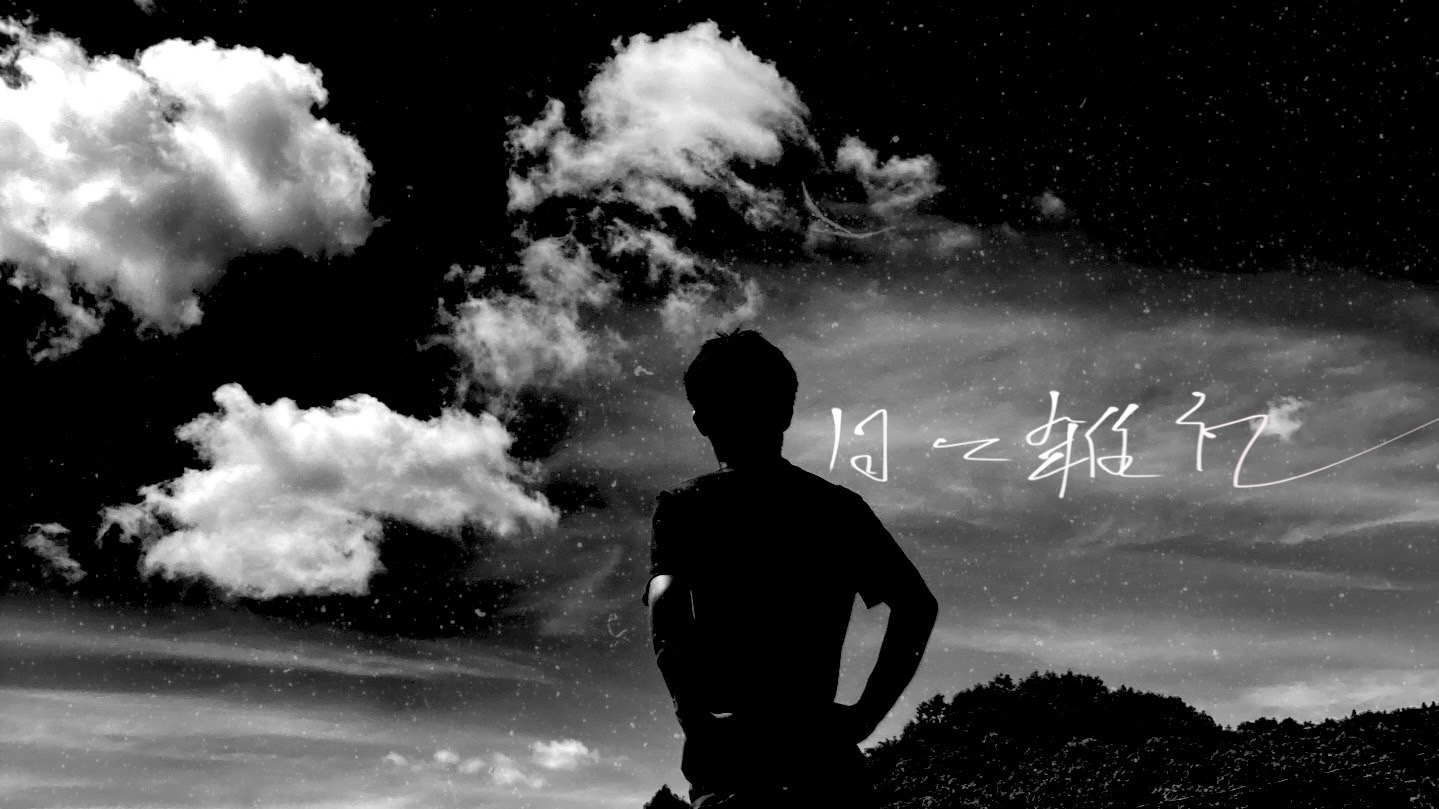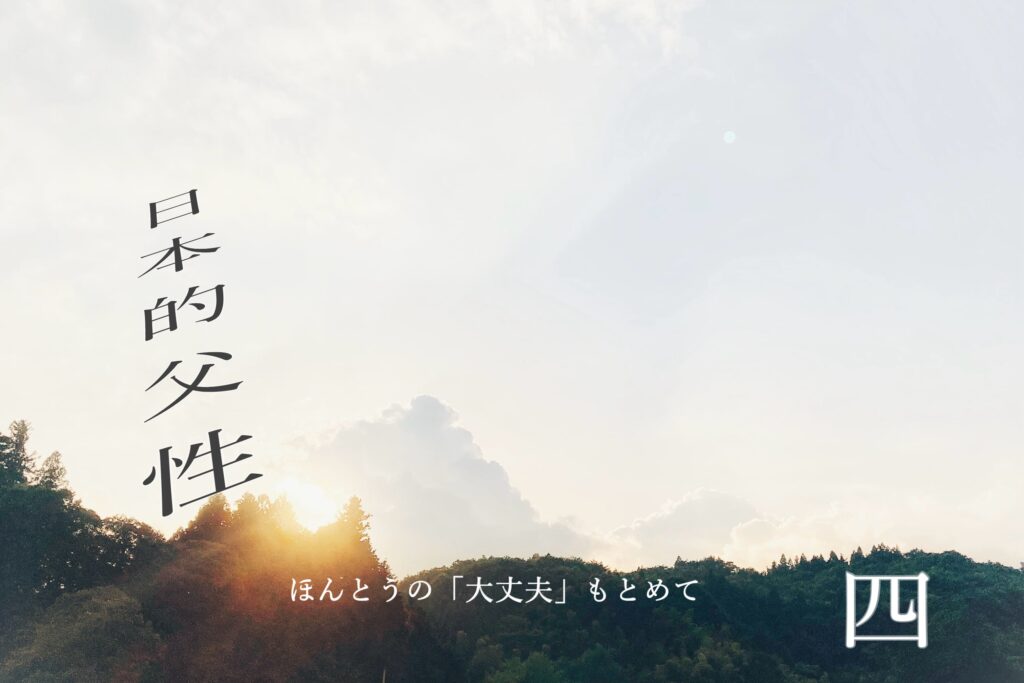
4.第一章「父性とは何か」
『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –
目次
-「父性」という希望
-「超越」という可能性
-「許し」という半クラ
-「大丈夫」という終わらない砦
-「父性」という希望
現代 日本 で「社会」の問題に叫び声を上げる数は数えきれない。そうした問題の原因や解決策として様々な自己啓発の文句が溢れ、オルタナティブに見える活動は乱立している。
そのような「生き易さ」を追求する活動の大半がまた「息苦しさ」の醸成に繋がり、「安心」と「安全」を求める心を承認し、加速させている。
だがしかし、そんな今だからこそ、まずはこのシンプルな概念をここに描きたい。
多くの若者が抱えている「息苦しさ」から、「母性」ばかりが育まれてしまう環境、叫ばれ続けるあらゆる問題に至るまで、その全てを変えていける「希望」として、「父性」という 風景 を、今、ここに描いておきたい。
これから本稿では特に「日本的父性」というテーマに迫っていくが、その前にこの章では「父性」とは何かについての骨格を端的に整理していきたいと思う。
そもそも、
「父性とはなんですか?」
と聞かれてパッと答えられる人がいるだろうか。
文字から推察して、「父親が持っている性質」と答えるかもしれないが、では、ヒトが父親になると共通して持ち合わせる特徴のようなものがあるのだろうか。例えば、「お金を稼いで家族を養う」とか、「家族を守って子孫を残す」とか、そうした具体的な時代が要請する父親の社会的な役割についてはいくつも思い浮かぶかもしれない。
しかし、そうした話は、本稿で描いていく「父性」とは「まったく」と言っていいほど関係が無い。
「父性」を 発揮 するのが男でも女でもそれ以外でも何の関係もないし、若くても年寄りでも何の関係もなく、誰が宿してもいいし、誰もが憧れ、敬い、 悦び 、 発揮 してもいいものなのである。
あくまで本稿は「父親が持っている性質」について考えていくのではなく、本稿で描く 風景 のことを、「父性」という言葉で表してみた(仮)という流れであり、その言葉自体にこだわりは無いのだ。もしももっと最適だと思う言葉が見つかれば、それを是非一般化させてもらいたい。
さて、それでは大きく括った「父性」というものについて、まずはなんとなくその骨格に触れてみよう。「母性」の際もキーワードを三つ挙げたが、「父性」についても構成する重要な要素( 風景 )というのがいくつかある。言葉としてではなく、「 風景 」としてイメージして、心の片隅に残しておいていただきたい。
まず根底で水紋のように広がる普遍要素が「超越」だ。
後にも詳しく書いていくが、ある認識の 「枠(囲い)」 からの超越、あるいは「認識」そのものからの超越こそが、「父性」の表出を最もつき通って描いている 風景 である。
身近なイメージで言うと、人は日常から多く何かにとらわれてしまうものである。そうした無意識下で作り出していた 「枠(囲い)」 が、誰かや何かの影響によって、まるで溶けたり気化したりするように、消えていく体験をしたことはないだろうか。あの感覚は誰かの「父性」によってもたらされていると言えるのである。
次に、「大丈夫」である。
「超越」のみであるとそれは くだらない 啓発や グルーヴ でしかない可能性がある。「超越」の先に同期的に「大丈夫」の姿が見えることがとても重要なのである。
分かりやすいイメージで言うと、「父ちゃんの大きな背中」ではないだろうか。もちろん人によっては、父ちゃんではなく母、兄姉、先輩、夫、彼、先生、動物といったところを想像する人もいるかもしれない。自分にはどうしようもない敵に襲われた時に、自分の前に立って攻撃を全て受け続けている姿や、絶対にこの人はそういった場面でそのようにしてくれるという 直覚 を持てること。その人の「傷だらけの背中」を後ろから見た時の、「安心安全」を超えたあの感覚のことなのである。あれが、「父性」でいうところの「大丈夫」だと言えるだろう。
また、「父性」が生まれる一瞬の過程に必要不可欠な要素として「許し」がある。
「父性」における「許し」はあらゆる「許し」を含んでいるが、それは痛みや苦しみについて見て見ぬふりをせずに、向き合って、ちゃんと痛んで、ちゃんと苦しんで、それでも許そうとする姿勢が特に重要なのである。
「超越」「大丈夫」「許し」、これら一つ、若しくは複数を 発揮 しているもの全てから、「父性」自体については感じることができる。
「父性」は、「超越」「許し」「大丈夫」といった要素を 発揮 することで、人々を「息苦しさ」から解放し、「母性」のみに偏った環境を変えていく可能性を持つ 風景 である。
「超越」は認識の枠組みを溶かし、新しい可能性を見出すことを可能にする。「許し」は痛みや苦しみに向き合いながらも、それを乗り越えていく「勇 氣 」を育み、そして「大丈夫」は、どんな困難な状況でも最後までいなくならない存在があることを示すものだ。
このような「父性」の要素が、現代の様々な問題を変えていく「希望」となるはずだと、私はここで主張しておきたい。
是非具体例をたくさんイメージして、「父性」の感覚を自分の身体に馴染ませていっていただきたい。
“Don’t worry that children never listen to you;
worry that they are always watching you.”
– Robert Fulghum
-「超越」という可能性
「父性」を構成する三つの要素のうち、まずは一つ目の「超越」について詳しく見てみよう。
「 人間 は考える葦である(L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un roseau pensant.)」 [6]
この言葉はパスカルが遺した言葉として有名だが、我々は葦のようにか弱い存在でも思考する力があるからこそ自然界で生き延びていけるという文脈を含んだポジティブな表現である。
しかし、我々はそうした能力を持っているが故に、何かの「思考」や「思い込み」に囚われてしまう不自由さも同時に持ち合わせている。
そうした「思考」や「思い込み」を超越する出来事と出会う体験をしたことがある人は多いのではないだろうか。
例えば「勘違い」という出来事はこの際たるものである。「これはこういうものである」と思い込んでいたが、実際にそれに触れてみると「これはこういうものだが、こういうものでもある」とか、「これがどういうものでもいい」と思えてしまうような体験も、小さな「超越」である。
こうした「思考」に関するものは後発の一つの出来事に過ぎないが、我々はそれよりも前にこの世界を 「認識」して生きている 。
「認識」する能力は、生まれ持ったものと生後の環境要因によって育まれたものが複雑に合わさり、一人一人オリジナルなものが形成されている。我々の一つ一つの「認識」の、その全てが「超越」される可能性を孕んでいるのだ。
例えば、円柱の積み木があったとしよう。これはある角度から見れば「丸」だが、ある角度から見れば「長方形」なのである。「丸」だと認識していたのに、見る場所を変えると「長方形」にも認識できて、全体を見ればそれを総じて「円柱」なのだと認識できるようになる。こうした認識の変異もある意味「超越」の一つである。
この世界のあらゆる「一」はほぼ全て視点や視野、受容体の種類や質、表現方法などを変えることで如何様にでも「認識」することができる。
そうしたあらゆる「認識」を「超越」していくことは我々すべてのひとに与えられた「奇跡」的な可能性なのである。
ここで、「超越」がもたらす変化を具体的にイメージしてもらうために、一つの小話を紹介したい。
かつて、とある小さな村で「越えることは不可能だ」と信じられていた山がありました。その山は、村人にとって未知の世界への境界であり、誰もがその頂を目指すことを恐れていました。
村には、好奇心旺盛な少年トムが住んでいました。彼は毎日、山を見上げては「あの山の向こうには何があるんだろう」と夢想していました。
村の人々は彼に警告しました。「あの山には危険がいっぱいだ。挑戦するなんて愚かなことだ」と。
しかし、トムは諦めませんでした。彼は準備をし、勇気を持って山に挑みました。
道中、彼は疲れ、何度も挫けそうになりましたが、彼の好奇心と決意は彼の 意志 を支え続けました。
ついに、トムは山の頂に到達しました。そこから見る 風景 は、彼が村で見ていたものとは全く違っていました。
広大な平野、遠くに見える新しい村、そして無限に広がる空と海。
彼は、「超越」とは、思い込みによる恐れや疑念を乗り越え、新しい可能性に目を開くことだと悟りました。
トムが村に戻った時、彼はその経験を村人たちと共有しました。彼の話を聞いた多くの村人たちも、新たな世界に対する好奇心を抱き始めました。
トムの行動は、村人たちにも、思い込みを「超越」する勇 氣 を与えたのです。そして、それは村全体に新しい風を吹き込むこととなりました。
トムは、諦めることなく挑戦することで、自分だけでなく、周りの人々の認識する世界をも変えたのです。
“Liebe Deine Feinde und hasse Deine Freunde.
Denn sie sind der Grund dafür,
dass du dich selbst nicht genug liebst.”
– Nietzsche, F. (1883-1885). Also sprach Zarathustra
-「許し」という半クラ
「父性」における「許し」の役割は、 マニュアル車 の運転で言うところの「半クラッチ」に似ている。
マニュアル車では、車の進行速度に合わせてギアというものを手動で変えてあげなければいけない。変えないと速度が全く出なくなったり、エンジンがストップしてしまったりする。ギアを適切に変えるためには、まずはクラッチという足元のペダルを一番下まで踏んであげる必要がある。そうすると噛み合っていたギアが離れて、一時的にエンジンの動力が車に伝わらなくなる。その間にギアを目的のギアに手で動かして変えてあげる。そして、「半クラッチ」という絶妙な位置になるまで、クラッチを踏んでいる足を上げてあげると、離れていたギアが一気に噛み合い、再度車にエンジンの動力が伝わって進んでいくことができるようになる。この絶妙なペダルの位置のことを「半クラッチ」という。
まさに、ある絶妙な位置で、フッと変化を許容できる時が来るのだ。そうすると、以前とは異なる動力がちゃんと相手に伝わっていくようになる。
逆に、この「許し」という「半クラッチ」がうまく機能しないと、状況は変化することなく、そのまま進んでいくことになる。その状態だとブレーキを踏めば止まるが、踏まなければ、下り坂であれば加速して進み続けていくし、上り坂では重力によって止まってしまい、いずれは坂を真っ逆さまに落ちていくことになる。
何かを状況に合わせて変化させようと思ったにも関わらず、「許し」ができないせいで変化は起こらなくなってしまうのだ。
現実を変化させていくために、私たちはこの「許し」をもっと大切に抱きしめていかなければいけないのではないだろうか。
この「許し」が無い「父性」は、エンジンにものすごい負担をかけてしまい、やり過ぎればエンジンごと壊れてしまう。もしくは現実逃避するが如く、突然エンジンごと止まってリスクを回避してしまう。
「半クラッチ」は慣れるまでは非常に難しいものでもあるが、様々な車を経験すると新しい車に乗っても「半クラッチ」の位置を見つけやすくなるように、「許し」も慣れて多様な経験を積み重ねていけばうまくなっていく。
それでは、先ほどのトムの小話の続きを「許し」をテーマに描いてみよう。
トムが山を越えた後、彼は自分の経験を村人たちと共有し、新たな視点をもたらしました。しかし、その変化に対しては、村の中には受け入れる者もいれば拒否する者もいました。
長年にわたって村の伝統を守ってきた村の長老であるジェームズは、特に慎重な性格で、新しい変化に対して強く抵抗しました。ジェームズはトムがよくお手伝いをしていた畑のおじいちゃんの幼馴染でした。実はトムが山に行っている間に、そのおじいちゃんは死んでしまったのです。そのおじいちゃんは山に挑んでいるトムに少しでも役に立てればと自分の飲む限られた飲み水を制限して、トムに渡すための水を溜めようとしていたのです。
おじいちゃんの死後、それを知ったジェームズはトムに対して激しい怒りを持つようになりました。
山から帰ってきたトムは、ジェームズのところへ何度も何度も足を運びました。何度追い返されても、彼はジェームズのもとへ通い続けました。その姿を見たジェームズは遂に話だけでもしてやろうと考えるようになりました。
ジェームズは、自分の考えとは異なるトムの視点に対して最初は批判的でしたが、トムはジェームズの意見を丁寧に聞き、彼の経験と知識を尊重し、ジェームズが村の安全と伝統を守ろうとする気持ちを理解し、彼に感謝の意を示しました。
この対話を通じて、ジェームズは徐々にトムの視点を受け入れ始めました。彼は、トムの冒険がもたらした新しい可能性を認識し、自分の抵抗が村の成長を阻んでいることを理解しました。
そして、彼はトムに対する「許し」の気持ちを抱くようにもなり、トムの提案する新しいアイデアを支持するようになりました。
トムとジェームズの「許し」は、村にとって大きな変化の始まりでした。彼の態度の変化に触発され、他の村人たちも新しい考え方を受け入れるようになりました。この「許し」が、村の統合と発展に大きく貢献したのです。
その後人々は、トムが踏破した山に亡くなったおじいちゃんの名前をつけて呼ぶようになりました。
このように、「超越」があっても「許し」というギア変換が行われなければ次のレベルの変化(「父性」でいうところの「大丈夫」)はもたらされない。そうなると、その「超越」はただただ空回りをするだけのものになってしまったり、現実を壊すだけのものになってしまったりする。
今、この息苦しい「社会」の様々なところでこの「許し」が必要とされている。
クレームを言う側も、偶像としての「クレーマー」を気にして行動する側も、「許し」に対して希望の念を持てば、新たな可能性がたくさん切り開けていくのではないだろうか。
年長者から若者への「許し」、逆も然り、人と人の関係性における「許し」、起きてしまった出来事に対する「許し」、様々な「許し」を感覚的に掴み、 発揮 していくことで、ようやく我々はその先へ 歩み 始めることができる。
“The weak can never forgive.
Forgiveness is the attribute of the strong.”
– Gandhi, M. K. (1958).
-「大丈夫」という終わらない砦
では、「大丈夫」とはなんだろうか。
普段の生活でも、「大丈夫」という言葉を使っている人は多いのではないだろうか。例えば、誰かが新しい挑戦や難しい状況に直面しているとき、不安を和らげるために「大丈夫」と伝えたり、事故や怪我など、緊急事態において人々を落ち着かせるために「大丈夫」と伝えたりもするだろう。あるいは自分自身に対して、特に自信がないときや困難に直面しているときに、自分を励ますために「大丈夫」と言い聞かせることもあるだろうし、誤解や小さな衝突が起こった際に、相手に対して気にしないことを伝え、関係を修復するために「大丈夫」と言うこともあるだろう。
このように私たちは様々な場面で「大丈夫」という言葉を用いているが、ここでいう「大丈夫」は、そうしたあらゆる「大丈夫」がもたらす心の機微に関わるすべてのポジティブな要素を集めていったもののことである。
トムが山を踏破する数ヶ月前、干ばつに見舞われた小さな村では、水不足が人々の生活に深刻な影響を及ぼしていました。
ある日、村で小さな子どもが森で木に登ろうとしていて、高さに怖気づいてしまいました。トムはそっと近づき、子どもの手を取り、静かに支えました。彼の存在だけで子どもは勇 氣 を得て、木の上まで登ることができました。トムは何も言わず、ただそこにいるだけで、「大丈夫」という安心感を伝えていました。
また、村の農作業で苦労しているおじいちゃんがいたとき、トムは彼の手伝いを始めました。彼はおじいちゃんに手を差し伸べ、不器用ながら一緒に作業を進めました。この行動は、おじいちゃんに対する彼の配慮と支援を示し、言葉を超えた「大丈夫」のメッセージを伝えていました。
トムが日々村中でみせるこうした一つ一つの行動は、水不足で大変な状況であった村にも小さな希望を生んでいました。
しかし、ある時からトムは「絶対に超えることはできない」と言われ続けていた山に通い始めるようになったのです。彼は黙々と何度も山へ行き、登頂を目指していました。彼が村人たちのために動くことを辞めて、山に行くようになった理由を理解できない村人たちは、「トムはどうかしてしまった」と言って彼の行動を非難するようになりました。
水不足はさらに深刻化し、村人たちは日々集まってその場しのぎの対策を考えて実施していましたが、そこに参加せずに山に登ってばかりいるトムに怒りをぶつけるようになりました。しまいにはトムに嫌がらせをする人も現れ、人々は山に通うトムの姿を見て笑い、子どもたちは石を投げつけました。
それでも、トムは山に登り続けました。そしてついに、山を超えることができたのです。彼が持ち帰った「絶対に超えられない山を越えられた」という奇跡は、苦しむ村人たちに希望を与えました。しかし、彼が山に登り続けていたのには、もう一つの重要な目的がありました。
彼は、森の中で子どもの木登りを助けていた時に、古い小川の痕跡を発見していました。更に、おじいちゃんの畑を手伝っている時に、小川の跡が畑まで来ているのを発見し、おじいちゃんから大昔には山から水が流れてきていたことを聞きました。トムはこの小川の跡が山へと続いていることに気づき、山に水源があるかもしれないと考えました。
しかし、トムはこの考えを村人には伝えませんでした。彼は、もし水源が見つからなかった場合、村人に与える安心感が虚しいものになり、既に危機的な状態にあるのに、より大きな絶望を招くかもしれないと懸念したからです。
しかし、登頂を果たしたトムが村に帰ってきた時に手にしていたのは、その輝かしい超越の話だけでなく、水がいっぱいに入った水筒でした。ついに、トムは山の頂で新しい清らかな水源を見つけたのです。
彼は慎重に村に戻り、水源の発見を村人たちに報告しました。当初は彼の発見を聞いても信じる者は少なかったのですが、彼が持ち帰った水を見て、彼の行動の真意を理解した村人たちは心を動かされざるを得ませんでした。
トムの行動は、村の危機を救うだけでなく、村人たちに「大丈夫」という安心感を提供し続けていたことを示していました。彼が保身に走ることなく心に留め続けた「大丈夫」は、最終的には村にとっての救いとなり、彼の真の意図が理解されたとき、村人たちもまた、誰かの「大丈夫」でありたいと願うようになりました。
「バカな息子をーそれでも愛そう…」
– EDWARD.NEWGATE『ONE PIECE』
(つづく)