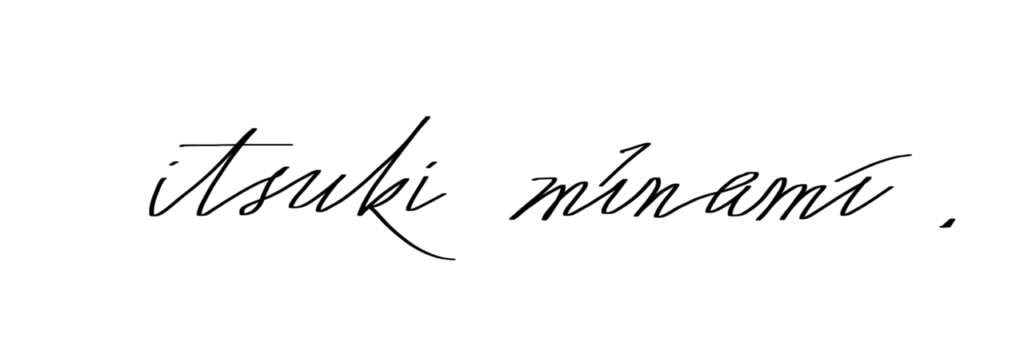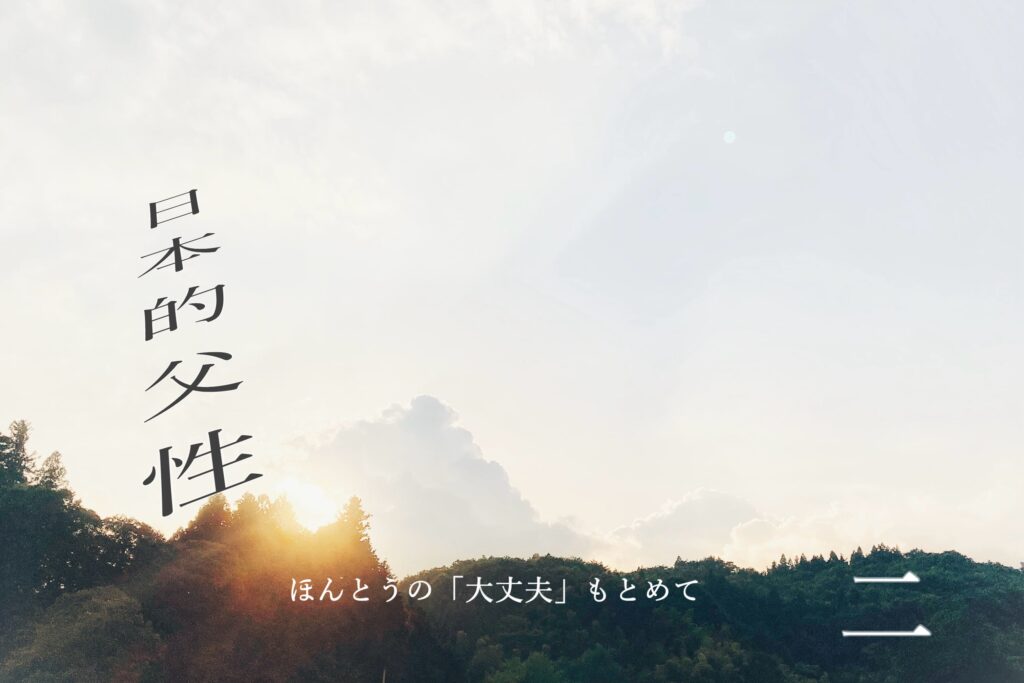
2.第一章「父性とは何か」
『日本的父性』- ほんとうの大丈夫もとめて –
目次
-息苦しき社会
今この時代に「父性」という概念を描くことで、どのような変化が生じるのか。その可能性は計り知れない。人と人とのコミュニケーションのあり方、組織や制度、住環境や生活様式、そして心の機微に至るまで、私たちの営みに深く影響を及ぼす可能性を秘めている。
仮に本稿の内容が広く共有されず、大きな変化が起きなかったとしても、「父性」の感覚を心に留めた人やその周囲の人々が、少しでも「息をしやすく」なったり、そんな変化がこの世界のどこかで起これば、それだけでとてつもない成果だと私は考えている。
では、現代の「社会」は本当に「息をしにくい(息苦しい)」のか。そして、それは一体誰にとっての「息苦しさ」なのか。この問いの真意について、これから丁寧に紐解いていくことになるが、まずは「息苦しさ」の具体的な事例を挙げながら、その輪郭を浮かび上がらせてみたい。
私は幼少期から、「ルールの多さ」に疑問を感じる経験を幾度となく重ねてきた。幼稚園の園庭で野球をしたいと思い、プラスチック製のバットを持ち込もうとしたところ、先生は「危ないからダメ」と許可しなかった。何とかして野球をしたかった私は、新聞紙を丸めてバットとボールを作り、工夫を凝らして野球をしようとしたものだ。こういった制約がクリエイティビティを生むことも今となってはよく分かるのだが、同時に、こうした「制約」の背景にある「社会」の病理に目を向けることの重要性を、私はその後同じような経験を重ねるたびに強く感じるようになっていった。
小学校に上がると、私のクラスの担任の先生は「あだ名禁止!みんなで『さん』付けで呼び合おう!親しき仲にも礼儀あり!」という方針を掲げていた。近年、一部の教員の間で「あだ名禁止」の方針が広がっている。その理由として、「あだ名がいじめの温床になる」「あだ名で傷つく子がいるかもしれない」といった考えが挙げられる。このような制約は、子どもたちのクリエイティビティさえも消してしまう「ルール作り」なのではないだろうか。
公園には「バットや硬式ボールを使った野球、サッカー、ゴルフなどは禁止です」と書かれた看板が並び、最近では「犬の散歩禁止」の看板まで都会の公園に増え始めている。空き地は次々と駐車場に変わり、公園では子どもの遊びすら制限されている。こうした変化が、子どもの外遊びやスポーツ人口の減少に拍車をかけている。
一部の学校では、ツーブロックの髪型を禁止する校則が今もなお残っている。東京都教育委員会教育長が、東京都予算特別委員会で議員の質問にこんな答弁をしたことも話題になった。
「その理由は、外見等が原因で事件や事故に遭うケースなどがあるため、生徒を守る趣旨から定めているものでございます。」 [2]
また、「防犯ブザー」の普及も象徴的だ。平成以降、都会の小学生がランドセルに防犯ブザーを付けるのは当たり前になった。しかし、これは「子どもを守る」ための施策であると同時に、地域社会の教育的役割が衰退したことの表れでもある。
この 都市 化が進んだ「社会」にあって、自分の子であろうと、地域の子であろうと、何か悪さをした子どもを叱れる大人が減り、叱られる経験をして育つ子どもも減っている。人と人との距離は広がり、ただの「怒り」を影で呟くことが増え、曖昧な「責任」から逃れるために新たなルールが次々と作られていく。
世間では「老害」という言葉が飛び交い、人付き合いが苦手な子どもたちは引きこもり、メタヴァース上の「安心安全」な世界に居場所を求める。面倒事にはルールを設け、距離を取り、見えないようにして、 デジタル遊牧民 と化した彼らは、そのうち現実世界での呼吸さえ不要になっていくのかもしれない。
「ゼロリスク症候群」という言葉だけでは収まりきらないほど自動化された人々のこうした動きは、もはや彼ら自身の意識の及ばないところで進行している。
「モンスターペアレント」という言葉は広く知られているが、教師たちが子どもの 生 の営みに向き合う前に、何かへの「恐れ」や「囚われ」からルールを設けている様子は、子どもたちに伝わっている。教師たちは先の教育長のように聞こえの良い言葉を並べてその理由を説明するが、幼い頃の私の目には、それがいわゆるポジショントークにしか映らず、「責任」から逃れるための方便としか感じられなかった。時には、教師たちが過剰反応気味に作り上げたクレーマーやノイジーマイノリティの偶像を感じることも多かった。
「誰一人取り残さない」「ダイバーシティ」「インクルージョン」といった時流に乗った言葉を振りかざしながら、「誰からも文句の出ない仕組み」を追求する大人たちの姿に、まるで性能の低い最適解計算機械みたいだと感じたのをよく覚えている。
教育現場以外でも、こうした「社会」の正義を振りかざして生きている人たちや、彼らの発する「情報」に右往左往している人たちはたくさんいる。そんな大人に囲まれて育った多くの子どもたちは、より多くの「情報」を得て、更に洗練された解像感の高い話を語り出す。
このような「ルール作り」に限らず、 都市 化、核家族化、地域社会の衰退などによって生まれ、デジタル化によって加速度的に進む「叱られる勇氣の喪失」「絶望を覚悟する勇氣の喪失」「それでも消えない いのち との付き合いの喪失」は、あらゆる場面にその影響を及ぼしている。
目に見える大きな犯罪や社会現象だけでなく、一人一人の暮らしの隅々にまで、 いのち の「息苦しさ」として表れているのだ。おそらく、あなたが今抱えている問題の根底にも、この流れが潜んでいるはずである。
私、本当は目撃したんです 昨日電車の駅階段で
ころがり落ちた子供と つきとばした女のうす笑い
私、驚いてしまって 助けもせず叫びもしなかった
ただ怖くて逃げました 私の敵は 私です
−中島みゆき『ファイト!』
-生き易い社会
では、本稿で言う「息をしやすい」ことと、「生き易い(いきやすい)」ことはどう違うのだろうか。
「安心」と「安全」を重視し、たくさんの選択肢が用意され、痛みや苦しみを減らしていくためのインフラが増え続け、「個性」が尊重されて「権利」が守られていくような「社会」は、 生命 がその寿命をできるだけ長く全うするためには、ポジティブな方向に進んでいる「社会」だとも言えるだろう。
たくさんのレールが用意され、苦しまずにすむ生き方ができるように、様々な制度や技術、概念等が日々整えられ、更新されていく。「誰一人取り残さない」という標語の下、皆が「平等」にその恩恵を受けられることを願う人が増えている。そうした「社会」では平均寿命は伸び続け、経済的にもある程度 「豊か」 な暮らしを送れる人の数は増えていく。後でも詳しく書くが、テクノロジーの発達によってそうした流れは急激に加速し、今後も進み続けていくだろう。
現代の社会で、偶像としてのリスク(責任)を恐れて行動するようになった人に、
「人を殺してはいけないのですか?」
と聞くと、多くの場合こんな答えが返ってくる。
「ダメです。絶対にダメです」
その理由を尋ねると、
「ダメなものはダメだからです。」
という答えが大半を占める。しかし、「正当防衛」の話題を持ち出すと、
「法律で認められているなら仕方ないかもしれませんが、とにかく人を殺すのはいけないことだと分かっていることが大切です。」
現代社会では、倫理観や法律により「人を殺してはならない」という常識が広く浸透している。
では、殺人のハードルがより低かった江戸時代以前の人々は、一体何だったのだろうか。彼らには倫理観や道徳心がなかったのだろうか。彼らはただムシャクシャしたら人を簡単に殺してしまうような、恐ろしい人たちだったのだろうか。侍はただの殺人鬼だったのだろうか。それ以前の時代の人々は、平生からいつ殺されるか分からない恐怖に怯えながら生きていたのだろうか。
現代のように「社会」を作り、「法律」で人々を厳しく統制していなかった時代では、一体何が人々の殺意や欲求を抑制していたのだろうか。
もし仮に、万が一、江戸時代以前の方が現代よりも殺人率が高かったとしても、彼らよりも現代人の方が怯えながら日常を生きているということはないのだろうか。もし仮にそうだとしたら、「生き易い」とは一体何なのか、という疑問が湧いてこないだろうか。
もし仮に、「 生の悦び ( いきもの としての根源的な 悦び )」 が、「長く生きること」ではないのだとしたら、この「生き易さ」を追求し続ける流れは「 いきもの ( いのち を宿した存在) 」としてポジティブなのだろうか。
もし「 生の悦び 」が、その時代その時代の「社会」で用意された 「幸福」 の形にほとんど関係ないとしたら、「社会」で 「幸福」 になることが「 いきもの 」としてポジティブなのだろうか。
「社会」を生きる「 人間 」 としてどれだけポジティブであっても、私たちは何よりもまずヒトであり「 いきもの 」なのだ。
どれだけ長く、どれだけ「安心安全」に生きられるようになったとしても、「 いきもの 」としてネガティブなら、元も子もないのではないか。
こうした文脈から生まれたのが、「息をしにくい」という表現なのだ。
つまり、「 生の悦び 」を得られず、「 いきもの 」としてネガティブな状況が生み出す、身体的・精神的な違和感・痛み・苦しみなどを「息をしにくい(息苦しい)」と表現するということである。
言い換えれば、どれだけ「生き易い」環境であっても、「息をしにくい(息苦しい)」状況はあり得るし、逆もまた然りで、どれだけ「息をしやすい」状況であっても、「生き難い」状況もあり得る。この二つは、ある程度根源的なところで影響し合ってはいるが、決して相関関係はないのだ。
日本 人にとっての「 生の悦び 」の分析については後でゆっくりと描いていくが、少なくとも現代の「社会」では「 人間 」としてのよろこび(=「 喜び 」と表す)を得ることが最重要視され、「 いきもの 」としてのよろこび(=「 悦び 」と表す)は考慮されることがない。
今この瞬間も、多くの人が様々な問題に向き合い、現在と未来のどこかで誰かが少しでも「社会」において「生き易く」なるように活動している。それは大変尊いことかもしれない。しかし、ほとんどの人に無意識のうちに植え付けられている「社会をより良くする」というベクトル自体が、「 いきもの 」としての「 悦び 」とは何の相関関係もないかもしれないという点を探求する人はどこにもいないのではないだろうか。
天長地久。天地所以能長且久者、以其不自生。故能長生。
-老子(『老子』七章)
-氣の減退
この「息をしにくい」という状況は、「 氣 」という観点から見てみると、より分かりやすいのではないだろうか。近年、 日本 人の「 氣 」の減退について、様々なニュースや話題が取り沙汰されている。
鬱病のような状態にある人は、子どもや青年でもかなりの割合で存在し、小中高生の自殺者数は統計を取り始めてから右肩上がりになっている。
さらに言えば、こうしたデータには表れないような、「何もやる気が起きない」「何にも興味が湧かない」といった状態にある人や、自傷行為や自殺未遂に及ぶ子どもは、数え切れないほど多い。
各地の児童精神科は予約しても数ヶ月から一年待たなければならない状況が頻発している。増え続けている不登校児のおよそ半数が「無気力・不安」を原因として挙げているというアンケートもある [3] 。
身体的な人との深い関わりを持つ機会が減り、ある程度以上の苦しみを避けるための 人間 関係に関する知恵や制度などが発達したことで、「 氣 」を使って何かに立ち向かうことに慣れていない人が増え、その分、他者から「元 氣 」や「勇 氣 」などの「 氣 」をもらう機会も減ってきている。
不安やストレスなどがあっても、何かに取り組もうとするには多くの「 氣 」を必要とするため、「 氣 」を使わずに 満足 感を得られる方法があればそちらに流れていきたくなる。
こうした流れの中で、「 氣 」を使うことなく「 満足 感」のようなものを得るためのサービスへの需要は急激に高まり、技術やインフラは加速度的に進歩している。そうしたものに多くの時間を費やすことで、感情や欲求は満たされているのに、「 氣 」はそれほど動いていないという状態が生まれる。不思議な感覚に思えるかもしれないが、今、多くの若者がそうした状態に慢性的に陥っている。
そうなると、「 氣 」が溢れることもなくなり、様々な変調が精神や身体、行動に現れ始める。突然「 氣 」を出し過ぎる環境に置かれて一生懸命頑張っても、そこにちゃんと「 氣 」をくれる人がいないと、すぐに空っぽになってしまったり鬱のような状態になってしまったりすることも多い。
ただ、この「変調」も、周りが皆同じような状態であれば、自分の「 氣 」が減退していることにも気づかず、違和感を覚えることさえなくなっていく。知らず知らずのうちに認識できる 環世界 を都合よく変化させ、デジタルデバイスを見つめる時間に多くを費やして認識的に「 満足 感」を得てしまえば、さらに「 氣 」が湧いてこなくなるという負の循環は、これからロボットやAIの技術が発達すれば、ますます加速していくだろう。
この「 氣 」の減退は若者だけの問題ではない。四十〜六十四歳の中高年の引きこもりの数は六十万人を超えるとされ、その数は四十歳以下の合計よりも多くなっている [4] 。鬱病の患者数も年代を追うごとに増加し、四十代周辺が最も多いという状態になっている [5] 。
このように「社会」に馴染めなかった者や、居場所を見つけられなかった者、大きな痛みや苦しみを背負った者たちは、家にひきこもったり、薬で精神を安定させたりして、何とか 生命 を繋いでいる。
一方で、こうした「社会」の中でポジションを取り、「社会」という仕組みを支えてきた中高年や高齢者も、その多くが「 氣 」をあまり使わない生活スタイルを送っていることが多い。「仕事」と「生活」を切り離して考えている人も多く、「仕事」での「 氣 」の消耗を除けば、「生活」の面ではほとんど「 氣 」を使わずに済むような時間の過ごし方を見つけ出そうとする人も多い。子どもや他者に対して多くの「 氣 」を消耗するような「本 氣 」のぶつかり合いをせず、思考と理解を変えることで困難を乗り越えてしまうパターンが増えた。デジタルネイティブでない世代でも、デジタルデバイスに一日のほとんどの時間を費やすようになり、「 氣 」を循環させる機会を減らしている。
このように「 氣 」がなくても楽しめる世界はとても「生き易く」、時間が経つのも早い。
職場や 人間 関係での「 氣 」をすり減らすような痛みや苦しみも、「社会」の制度や風潮が変わることで簡単に避けようと思えば避けられるようになった。
多くの「 氣 」を消耗せずに生きている親や大人を見て育つ子どもは、「 氣 」に対する耐性がなくなり、今や「本 氣 」を「集中力を上げること」でしかないと考える若者も多くなっている。
また、もし「 氣 」というものを、本来ヒトはあらゆる生きとし生けるものから受け取り、与え、循環させていたのだとすると、コンクリートに囲まれた環境で暮らすようになった人々は、「 氣 」に触れる機会をあまりにも多く失ってしまったのではないだろうか。
このように人々の気が付かないところで「 氣 」が減退し、わずかばかりになった「 氣 」を消さないために、より「生き易い」「社会」を作っていく流れは加速している。「 氣 」が自由に多量に飛び交えない、つまり「 空氣 」の薄い世界は、 いきもの として「息をしにくい」環境を醸成することに繋がっているのではないだろうか。
道生一、一生二、二生三、三生萬物。萬物負陰而抱陽,沖氣以為和。
-老子(『道徳経』第四十二章)
-失っていく「大丈夫」
「社会」が「生き易く」なっていくということは、「 人間 」が痛みや苦しみを味わうリスクを減らしていくということでもある。
エネルギー面を含めて、車や電車、飛行機など、物理的な移動を容易にする技術やインフラが発達したことで、遠く離れた場所へ行くことも容易になり、ある地域でうまくいかなくなれば他の地域へ移ることさえ難しくなくなった。
また、同じ「社会」に属する「社会人」同士の関係は、損得や論理で調整したり断ち切ったりできる関係だとも言えるだろう。そのため、「社会」が最重要視される環境で育てば、あらゆる関係性にその感覚を当てはめることにも違和感を持たなくなりやすい。SNSの普及により、「フォロー」や「ブロック」などのボタン一つで 人間 関係を整理していると感じる人さえ増えてきたと言われている。
総じて、 人間 関係でうまくいかなくなれば、簡単に関係を断ち切って 気 の合う人のもとへ行く、付き合っていくということが、昔の村社会が残る時代に比べて格段に容易になった。
まるで「関係を続ける」と「関係を断つ」の二択から、どちらかをポチッと押すような感覚で、誰かに「関係を断つ」「縁を切る」と言ってしまえる人が増え続けている。このような関係性の「ゲーム化」は、現代の「社会」の隅々にまで広がっている。
誰かと関わる中でストレスを感じたり、ネガティブな感情や不安、疑問が生まれたとき、それでも向き合い続けようとするためには、特に 共感 性が高く想像力が 豊か な人ほど、あまりにも多くの「 氣 」を使ってしまう。
世の中のあらゆることは、視点や視野、表現方法次第で「良く」も「悪く」も捉えられる。しかし、人はどんな人でも、一つの視点に縛られたり、何らかの認識に夢中になったりすることがある。それを解きほぐすために人が 意志 を持ってできるのは、実際に「行って 会って やって 話す」ことで、固まった認識を超えていく可能性を探るということだけなのかもしれない。
しかし、「社会」が「生き易く」なればなるほど、こうした「 氣 」を大量に使う「我慢(忍耐)」とも呼べる行為の重要性を感じない人が増え続けているのではないだろうか。
こうした流れの中で「 いきもの 」としての「 大丈夫 」を感じて生きていける若者が減り続けている。
親は簡単に「離婚」だの何だのを二人の間で決め、学校や友人たちとは仲間外れにならないように空気を読もうとし続けるしかなく、近所との付き合いはほとんどないから、 生命 を懸けて助けてくれる人なんてどこを探してもいない。あるいは、そうした状況にいつなってもおかしくないような環境で育つ子どもたちの多くは、「 いきもの 」としての「大丈夫」に一度も触れたことがなく、「縁を切られないように」「関係を断たれないように」と怯えながら生きることが、無意識のうちの行動原理になっている。
「救いだ」「居場所だ」と思った人には異常なほど没入し、「一生の愛」を幼い頃から囁き合う。親を 満足 させるために自分の人生の時間を使うことに何の違和感も感じず、「社会」の指標を盲目的に受け入れて、決められたルールの中で従順に思考し、行動し続ける。
そんな「怯え」から生まれる行動を素直に繰り返していると、そうした素直さを嘲笑うかのように、簡単に「関係を断つ」経験を突きつけられる時が来る。
「一生一緒にいようね」と「本 氣 」で語り合ったはずの恋人に、突如、認識や感情の変化を理由に「関係を断つ」と言われてしまったり、一生懸命取り組んでいたチームで突然「お前はいらない」と言われてしまったり、友だちだと思っていた人に仲間外れにされてしまったり、家族だと思っていた人が突然いなくなってしまったり、そうした突然の縁切りの不誠実度合いは、相手がどれだけ実際に「行って 会って やって 話す」ことで いのち と向き合おうとしたのかというところに尽きるとも言えるだろう。
恋愛の話 は分かりやすい例えに過ぎないが、突然の縁を切る行為は、それが不誠実なものであればあるほど、簡単に人の心を破壊する可能性を十分に孕んでいる。こうした無自覚の破壊行為は、「 氣 」が薄くなった現代では、恐ろしく尖った槍となり、 生命 の精神(心)を抉るように突き刺し、貫いてしまう。
その人との関係がより「 いきもの 」と「 いきもの 」の関係に近く、この行為がより不誠実なものであればあるほど、そこで生まれる痛みは大きくなる。ひどい場合は、もはや「痛い」とか「苦しい」とかの次元ではないところまで行ってしまう。
こうした「 地獄 」を体験させられると、「自分の命を絶つ」か、「誰かを殺す」か、「痛みを感じなくするための技術を 向上 させる」のいずれかの選択を無意識のうちに迫られるようになってしまう。
時が経って考えなくなるのを待ったり、誰かに話してみたりして自分自身の認識を変化させ、こうした「 地獄 」から逃れるパターンが大半であり、痛みや苦しみへの感受性が鋭い人ほど、幼い頃からこうした認識を変化させる技術を磨いており、「 地獄 」から逃れるための手段をたくさん持っていることも多い。自傷行為を繰り返したり、新しい意味や目的に没入したり、忘れたり、寝て考えないようにしたり、薬に頼ったり、欲望を満たし続けてみたり、その手段は無数に存在するだろう。
だがそれ以前に、そうした「 地獄 」が生まれる可能性を持つような関係性をそもそも作らない人が増え続けている。「恋人」「上司」「友だち」など、様々な「社会」で作られた 「枠組み」 で誰かとの関係性を認識することで、あくまでも「社会」的な「 人間 」と「 人間 」の繋がりにしておくことができる。
そうすることで突然「縁を切る」ということが起こっても、そこまで傷つかないように割り切れる。決して「社会」に存在する 「枠組み」 の中に閉じ込められないような、あくまでもオンリーワンな「 いきもの 」と「 いきもの 」の関係性を、そのままに大切にできる人は非常に少ない。また、普段はそうしておくことができても、都合が悪くなった途端、何らかの 「枠組み」 に圧縮して加工してしまう場合も多い。
さらに言えば、ある一定以上ネガティブな感情が湧いてこないように認識の仕方や行動の仕方、感覚器自体を無自覚に変化させているパターンも非常に多くなっている。
その一方で、「関係を断つ」「縁を切る」という行為が必要になる場面や、あくまでも誠実に働く場面も存在するのではないだろうか。
例えば、相手が「関係を断たれるかもしれない」「縁を切られるかもしれない」という覚悟を持って、それでも断行した行為に対して、「関係を断つ」「縁を切る」と返すのは、あくまでも誠実な行為と言えるかもしれない。
あるいは、先ほどから描いているとおり、「行って 会って やって 話す」ことを丁寧に行った末に、「関係を断つ」「縁を切る」に至るとすれば、それは無自覚に精神(心)を破壊する道具にはならないかもしれない。
もしもここまで描いてきたことが本当に起こっているのだとしたら、「生き易い」「社会」を極めていく流れは、「 氣 」の減退に繋がり、「息苦しい」環境を生み出し、人々が「 いきもの 」としての「大丈夫」を感じられる機会を奪い続けているのではないだろうか。
減退して僅かばかりになった「 氣 」を、「大丈夫」のない環境は揺るがせ、そして恐ろしく不誠実な行いによって簡単に消し去ってしまう。
簡単に 生命 を終わらせる力を持つようなそうした「 地獄 」に出会うリスクを回避するために、人と人との関係性はより軽薄化し、「 氣 」の入出力量は減り続けるというループは止まるところを知らない。
今後、感情や感覚を十分に満たすことができて居心地の良い環境は、現実空間からサイバー空間へと拡大していく。これまで「社会」でそうした環境を見つけられなかった者たちも、サイバー空間や拡張現実空間で心地の良い「生き易い」場所を見つけることができるようになっていくだろう。
君の行く道ははてしなく遠い だのに なぜ 歯をくいしばり 君は行くのか そんなにしてまで
君のあの人は 今はもういない だのに なぜ なにを探して 君は行くのか あてもないのに
-ザ・ブロードサイド・フォー(藤田敏雄)『若者たち』
(つづく)